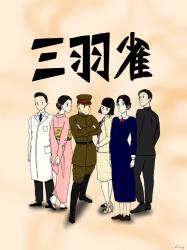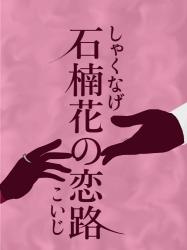小学校1年の私は、辞書を手にして1ページずつ小さな手で捲っていった。
少し厚い表紙の裏には凡例か辞書の引き方が書かれていた気がする。
そして記念すべき1ページ目は題字と編纂した人の名前など、そしてその次の次くらいからが辞書の中身の始まりである。
最初の単語から隈なく読んでいく。
小学校に上りたての少女の柔らかく新鮮な脳みその中には、目にする単語とその意味が刷り込まれていくのであった。辞書を「あ」の段から順に全て読むという時点で既に辞書の一般的な使い方を大きく逸脱しているが、正しく辞書を使おうとしてもそれができないのが私である。
大学生になった今でもその傾向がある。
本を読んでいると知らない単語に出会う。
高校までは授業中や課題に「この単語の意味を調べましょう」ということがあった。
スマートフォンを使うことが許されていればインターネット上の辞書でサッと引くのだが、それができない場合はたちまち困ったことになる。
私は小中一貫校に通っていたのだが、小中学校では電子辞書が禁止され国語辞典でも漢字辞典でも、英和・和英でも紙辞書を使いなさいと厳しく教えられていたので電子辞書は一切持たなかった。
そして高校に上がった時のこと、なんと私以外の生徒は全員、電子辞書を持っていたのである。
外国人の先生が持つ英語の授業で皆の机の上は教科書とノート、そして電子辞書と大変整然としていたが、見事に私の机には教科書とノート、さらに和英辞典と英和辞典という本だらけ状態である。
机の左上に和英辞典、英和辞典、そして筆箱を載せて出来上がったエンパイア・ステート・ビルディングを見て先生が一言、
「電子辞書持ってナイの?」
と。私は持っていないと答えるほかなかった。
少し厚い表紙の裏には凡例か辞書の引き方が書かれていた気がする。
そして記念すべき1ページ目は題字と編纂した人の名前など、そしてその次の次くらいからが辞書の中身の始まりである。
最初の単語から隈なく読んでいく。
小学校に上りたての少女の柔らかく新鮮な脳みその中には、目にする単語とその意味が刷り込まれていくのであった。辞書を「あ」の段から順に全て読むという時点で既に辞書の一般的な使い方を大きく逸脱しているが、正しく辞書を使おうとしてもそれができないのが私である。
大学生になった今でもその傾向がある。
本を読んでいると知らない単語に出会う。
高校までは授業中や課題に「この単語の意味を調べましょう」ということがあった。
スマートフォンを使うことが許されていればインターネット上の辞書でサッと引くのだが、それができない場合はたちまち困ったことになる。
私は小中一貫校に通っていたのだが、小中学校では電子辞書が禁止され国語辞典でも漢字辞典でも、英和・和英でも紙辞書を使いなさいと厳しく教えられていたので電子辞書は一切持たなかった。
そして高校に上がった時のこと、なんと私以外の生徒は全員、電子辞書を持っていたのである。
外国人の先生が持つ英語の授業で皆の机の上は教科書とノート、そして電子辞書と大変整然としていたが、見事に私の机には教科書とノート、さらに和英辞典と英和辞典という本だらけ状態である。
机の左上に和英辞典、英和辞典、そして筆箱を載せて出来上がったエンパイア・ステート・ビルディングを見て先生が一言、
「電子辞書持ってナイの?」
と。私は持っていないと答えるほかなかった。