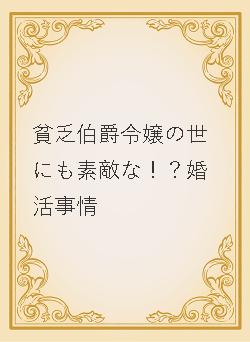「おお、騎士団長殿。つまみ食いに来たか?」
からかう口調に、思わず顔をしかめる。幼い頃のことがあるせいか、どうしたってヒューバートには勝てない気がする。
「ユーリの仕事ぶりを聞きに来たんだが」
「ああ、お嬢ちゃんか」
お嬢ちゃん?いつもながらの言い回しに、再び顔をしかめたものの、実際にヒューバートから見れば、ユーリも自分も王太子ですら、子どもにしか見えないのだろうと、喉を出かかった文句を飲み込む。まあ、ルイスもこの口調を咎めないのだから、私がとやかく言うこともない。
「もうすっかりここに馴染んでいるぞ。最近は、調理の方も手伝ってくれてる。なかなか使えるな」
腰の低いユーリのことだ。慣れてこれば愛想の良さもあって、多くの人に受け入れられる人物なのだろう。かく言う自分もそのうちの1人だと気付く。
ユーリのことは、早い段階から信頼できると確信していた。さらにあの剣を持つ姿勢は、確信を一層強めた。申し分のない人物なのだろうな。
からかう口調に、思わず顔をしかめる。幼い頃のことがあるせいか、どうしたってヒューバートには勝てない気がする。
「ユーリの仕事ぶりを聞きに来たんだが」
「ああ、お嬢ちゃんか」
お嬢ちゃん?いつもながらの言い回しに、再び顔をしかめたものの、実際にヒューバートから見れば、ユーリも自分も王太子ですら、子どもにしか見えないのだろうと、喉を出かかった文句を飲み込む。まあ、ルイスもこの口調を咎めないのだから、私がとやかく言うこともない。
「もうすっかりここに馴染んでいるぞ。最近は、調理の方も手伝ってくれてる。なかなか使えるな」
腰の低いユーリのことだ。慣れてこれば愛想の良さもあって、多くの人に受け入れられる人物なのだろう。かく言う自分もそのうちの1人だと気付く。
ユーリのことは、早い段階から信頼できると確信していた。さらにあの剣を持つ姿勢は、確信を一層強めた。申し分のない人物なのだろうな。