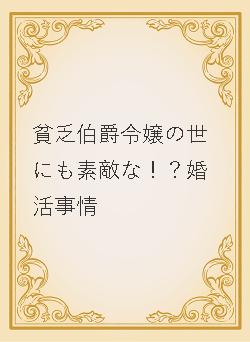「見てください!いくつかの料理のレシピが完成しました!」
そう言って、誰にでもわかるように絵でまとめたレシピを見せると、そこにいた全員が「ほおう」と唸った。
「必死で何かやってると思っていたけれど、これを作っていたんですね」
感心したように言ったのは、調理場ではたらくアビーだった。
「ちょっと貸してみろ」
ヒューバートは私の作ったレシピを、まじまじと眺めている。
「あんた、これを見て作れば、私もあんたぐらい美味しく作れそうじゃないの」
モーリーンも横から覗き込んで、感心している。
「そうさなあ……一度、お前らでこの通りに作ってみろ。なあに、不味かったら手直ししてやるさ」
早速、夕飯で一品だけ試してみれば、そこそこの料理が完成した。味を見て、ヒューバートも満足そうに頷いている。実際に料理したアビーは、そんなヒューバートを見て、涙ぐんでいるのは見間違いじゃないと思う。
「なるほどなあ、これならお偉いさん達にも堂々と出せるレベルだ」
絶対的な料理長であるヒューバートからお墨付きをもらい、アビーをはじめとした調理員は嬉しそうにしている。
「ユーリのおかげだな。よし、これからも頼むぞ」
「はい。任せてください」
やっと一つ、ここにいていい理由を得たようで、心が少しだけ軽くなった。
そう言って、誰にでもわかるように絵でまとめたレシピを見せると、そこにいた全員が「ほおう」と唸った。
「必死で何かやってると思っていたけれど、これを作っていたんですね」
感心したように言ったのは、調理場ではたらくアビーだった。
「ちょっと貸してみろ」
ヒューバートは私の作ったレシピを、まじまじと眺めている。
「あんた、これを見て作れば、私もあんたぐらい美味しく作れそうじゃないの」
モーリーンも横から覗き込んで、感心している。
「そうさなあ……一度、お前らでこの通りに作ってみろ。なあに、不味かったら手直ししてやるさ」
早速、夕飯で一品だけ試してみれば、そこそこの料理が完成した。味を見て、ヒューバートも満足そうに頷いている。実際に料理したアビーは、そんなヒューバートを見て、涙ぐんでいるのは見間違いじゃないと思う。
「なるほどなあ、これならお偉いさん達にも堂々と出せるレベルだ」
絶対的な料理長であるヒューバートからお墨付きをもらい、アビーをはじめとした調理員は嬉しそうにしている。
「ユーリのおかげだな。よし、これからも頼むぞ」
「はい。任せてください」
やっと一つ、ここにいていい理由を得たようで、心が少しだけ軽くなった。