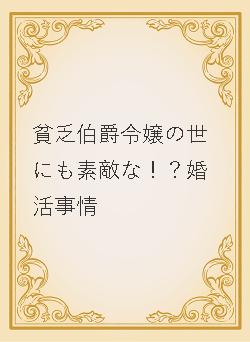「いいんじゃないか」
一通り笑い終えると、ふと真面目な顔をしてそう言った。
「料理はな、ただ習慣としての食事ってだけじゃない。誰かを喜ばせたい時、元気付けたい時、祝ってやりたい時、いろんな意味がある。お嬢ちゃんはいつもそうやってお菓子を作っているぞ」
レモンの蜂蜜漬けに始まって、孤児院への差し入れ、我が子へのプレゼントと、ユーリの作る様々な物を思い起こした。
そうか。そこには常に、彼女の想いが込められていた。人々がユーリを支持するのは、彼女のそういう面を感じているからだ。
早速、その日からヒューバートにパン作りを習うことになった。
とはいえ、立場上、そんな姿を誰かに見られるわけにはいかない。もちろん、子ども達にも。
「最近、公務が忙しい」
と、白々しくももっともな言い訳をしながら、夜遅く、ヒューバートの元へ通った。文句の一つも言われても仕方ないのに、ヒューバートは何も言わずに、親身になって付き合ってくれた。
もちろん、香ばしい香りをさせたまま、ユーリの眠るベッドに潜り込むわけにはいかない。特訓の後は、必ず湯あみを済ませて戻るようにした。
一通り笑い終えると、ふと真面目な顔をしてそう言った。
「料理はな、ただ習慣としての食事ってだけじゃない。誰かを喜ばせたい時、元気付けたい時、祝ってやりたい時、いろんな意味がある。お嬢ちゃんはいつもそうやってお菓子を作っているぞ」
レモンの蜂蜜漬けに始まって、孤児院への差し入れ、我が子へのプレゼントと、ユーリの作る様々な物を思い起こした。
そうか。そこには常に、彼女の想いが込められていた。人々がユーリを支持するのは、彼女のそういう面を感じているからだ。
早速、その日からヒューバートにパン作りを習うことになった。
とはいえ、立場上、そんな姿を誰かに見られるわけにはいかない。もちろん、子ども達にも。
「最近、公務が忙しい」
と、白々しくももっともな言い訳をしながら、夜遅く、ヒューバートの元へ通った。文句の一つも言われても仕方ないのに、ヒューバートは何も言わずに、親身になって付き合ってくれた。
もちろん、香ばしい香りをさせたまま、ユーリの眠るベッドに潜り込むわけにはいかない。特訓の後は、必ず湯あみを済ませて戻るようにした。