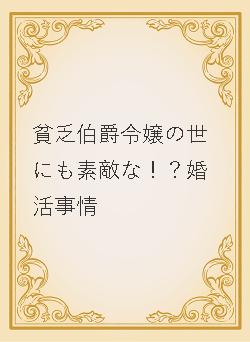庭の中ほどで足を止めると、ルイスは私の片手を取っておもむろに片膝をついた。それはまるで、幼い頃絵本の中で見た王子様そのもののようだ。
「ユーリ、私が唯一そばにいて欲しいと思ったのは、ユーリだけだ。いつも、どんな時も、私と一緒にいて欲しい。私の妃になってくれないか?」
嗚咽が漏れそうになって、口元を押さえる。
答えはもう決まっている。
「私が隣にいて欲しいと望むのも、ルイスだけ。いつまでも、あなたの隣にいさせてください」
ルイスはとろけるような笑みを浮かべると、私の手にそっと口づけをした。そして、ゆっくりと立ち上がると、そっと唇を合わせて力強く抱きしめた。
「やっと、私のものになってくれたな」
「もうずっと前から、私はルイスのものよ。
でも、知っての通り、私はこれからも孤児院へ遊びに行きたいし、調理場の仕事もしたい。もちろん、剣も握っていたい。だから、いつも目を離さないでいてね」
「もちろんだ」
END
「ユーリ、私が唯一そばにいて欲しいと思ったのは、ユーリだけだ。いつも、どんな時も、私と一緒にいて欲しい。私の妃になってくれないか?」
嗚咽が漏れそうになって、口元を押さえる。
答えはもう決まっている。
「私が隣にいて欲しいと望むのも、ルイスだけ。いつまでも、あなたの隣にいさせてください」
ルイスはとろけるような笑みを浮かべると、私の手にそっと口づけをした。そして、ゆっくりと立ち上がると、そっと唇を合わせて力強く抱きしめた。
「やっと、私のものになってくれたな」
「もうずっと前から、私はルイスのものよ。
でも、知っての通り、私はこれからも孤児院へ遊びに行きたいし、調理場の仕事もしたい。もちろん、剣も握っていたい。だから、いつも目を離さないでいてね」
「もちろんだ」
END