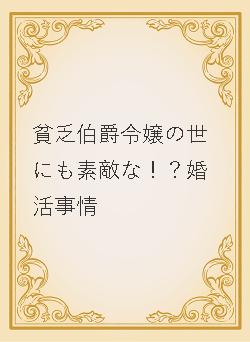「私だから?」
「そうだ。女性に嫌悪感を抱いてしまう私が、唯一側にいて欲しいと思ったのは、ユーリだけだ。そのためなら、言い伝えだってなんだって利用してやると思った」
混乱する頭に手を添えると、こむぎが励ますように体を擦り付けてくる。
「しかし、この話は王家以外の者には聞かせられないことになっている。長老達や貴族達に、ユーリを認めさせるためにはどうしたらよいのかと考えていた。けれど、私が何かをするより先に、ユーリ自身がそれをやってのけていた」
「私が?私はなにもしていません」
「いや。君が普通にしていること全てだ。自ら働くことを厭わない。知識を惜しみなく授ける。騎士達と共に自ら剣を握る勇ましさ。孤児院へ幾度となく足を運び、作り物でない愛情を注ぐ優しさ。自分の命を差し出してでも、他者を救おうとする勇敢さ。そして、自らの身を自身で守る強さ。
この国の民は、そういうユーリの姿を見て、ユーリだからこそ、王妃になって欲しいと願った。その証拠に、日を開けず、何通もの文や嘆願書が私の元へ届けられている。ユーリを王妃にと」
「そうだ。女性に嫌悪感を抱いてしまう私が、唯一側にいて欲しいと思ったのは、ユーリだけだ。そのためなら、言い伝えだってなんだって利用してやると思った」
混乱する頭に手を添えると、こむぎが励ますように体を擦り付けてくる。
「しかし、この話は王家以外の者には聞かせられないことになっている。長老達や貴族達に、ユーリを認めさせるためにはどうしたらよいのかと考えていた。けれど、私が何かをするより先に、ユーリ自身がそれをやってのけていた」
「私が?私はなにもしていません」
「いや。君が普通にしていること全てだ。自ら働くことを厭わない。知識を惜しみなく授ける。騎士達と共に自ら剣を握る勇ましさ。孤児院へ幾度となく足を運び、作り物でない愛情を注ぐ優しさ。自分の命を差し出してでも、他者を救おうとする勇敢さ。そして、自らの身を自身で守る強さ。
この国の民は、そういうユーリの姿を見て、ユーリだからこそ、王妃になって欲しいと願った。その証拠に、日を開けず、何通もの文や嘆願書が私の元へ届けられている。ユーリを王妃にと」