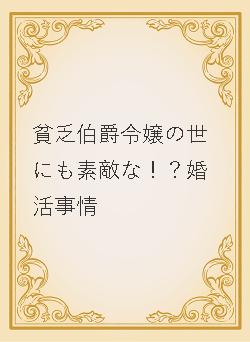つい先ほどまで、この腕の中にユーリがいた。その柔らかさ、温かさ、自然な甘い香りに惹きつけられるように、彼女に触れ、口付けを交わした。
自分が女性に対してこんな想いを抱くようになるとは、思ってもみなかった。手の届くところにユーリがいれば、無意識のうちに触れたいと求めてしまう。
甘い余韻に浸りながら、今夜の夜会を思い起こしていた。
私が本当は王太子であると知った時、ユーリはどう思ったであろうか。
可愛さと美しさの同居するその小さな顔は、驚きであふれていた。
もともと大きな瞳はさらに見開かれて、少し厚みのある唇はわずかに開いたままになっていた。
ホールにいたどの令嬢よりも飾り気がなく、華美でないドレスを着ていたのにも関わらず、一目で彼女を見つけられた。ユーリは、会場でただ一人、美しく輝いて見えた。
自分が女性に対してこんな想いを抱くようになるとは、思ってもみなかった。手の届くところにユーリがいれば、無意識のうちに触れたいと求めてしまう。
甘い余韻に浸りながら、今夜の夜会を思い起こしていた。
私が本当は王太子であると知った時、ユーリはどう思ったであろうか。
可愛さと美しさの同居するその小さな顔は、驚きであふれていた。
もともと大きな瞳はさらに見開かれて、少し厚みのある唇はわずかに開いたままになっていた。
ホールにいたどの令嬢よりも飾り気がなく、華美でないドレスを着ていたのにも関わらず、一目で彼女を見つけられた。ユーリは、会場でただ一人、美しく輝いて見えた。