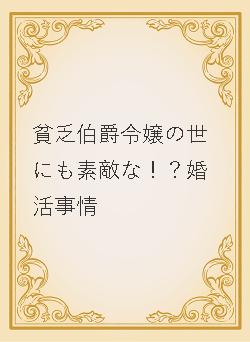「ルイス様。本日持ち込まれた分です」
執務室で渡されたのは、お妃候補の資料だった。どいつもこいつも、真っ先にあるのは親の地位。それがなんだというのだ。
陛下に代わってこの国の実権を握って以来、私のしてきた仕事には自信を持っている。政略的婚姻など必要ないほどに、自分の立ち位置も確固たるものにしてきたつもりだ。
「ふん。捨てておけ」
「ルイス様。そういうわけにもいきません。そろそろ本格的にお妃様を選出していただがないと」
「必要ない。自分の隣にいて欲しいと思う者は、自分で見つける。ただ綺麗に着飾っただけの令嬢など、私には必要はない」
「ですが」
「くどい。下がれ」
こちらに聞かせるようにため息を溢し、資料を手にした長老が、不満をあらわに下がっていく。
お妃選びは、複数いる長老の主導の元進められていく。が、彼らにある程度意見は言えても、最終的に決定するのは、王太子である私自身だ。自分が頷かなければ、お妃は決定されない。
これまで、持ち込まれた誰にも興味が抱けなかった。
生涯、自分の隣にいて欲しい人。描こうと思っても、全く思い描くことができなかった。
だが、今は違う。空白だった私の横には、ユーリの姿が見える。初めて欲しいと思った。
執務室で渡されたのは、お妃候補の資料だった。どいつもこいつも、真っ先にあるのは親の地位。それがなんだというのだ。
陛下に代わってこの国の実権を握って以来、私のしてきた仕事には自信を持っている。政略的婚姻など必要ないほどに、自分の立ち位置も確固たるものにしてきたつもりだ。
「ふん。捨てておけ」
「ルイス様。そういうわけにもいきません。そろそろ本格的にお妃様を選出していただがないと」
「必要ない。自分の隣にいて欲しいと思う者は、自分で見つける。ただ綺麗に着飾っただけの令嬢など、私には必要はない」
「ですが」
「くどい。下がれ」
こちらに聞かせるようにため息を溢し、資料を手にした長老が、不満をあらわに下がっていく。
お妃選びは、複数いる長老の主導の元進められていく。が、彼らにある程度意見は言えても、最終的に決定するのは、王太子である私自身だ。自分が頷かなければ、お妃は決定されない。
これまで、持ち込まれた誰にも興味が抱けなかった。
生涯、自分の隣にいて欲しい人。描こうと思っても、全く思い描くことができなかった。
だが、今は違う。空白だった私の横には、ユーリの姿が見える。初めて欲しいと思った。