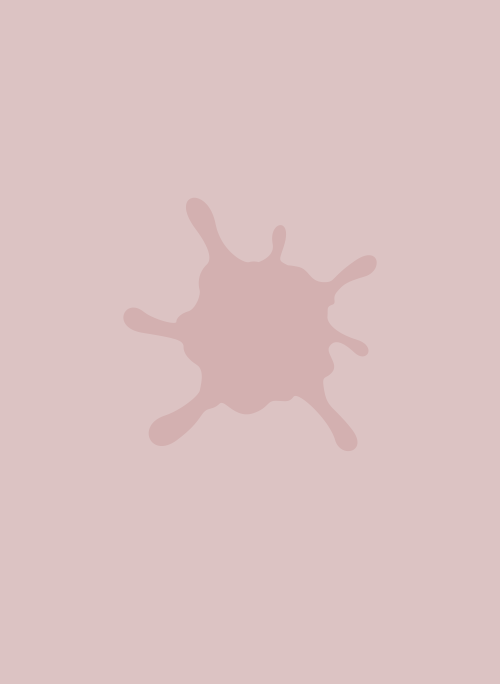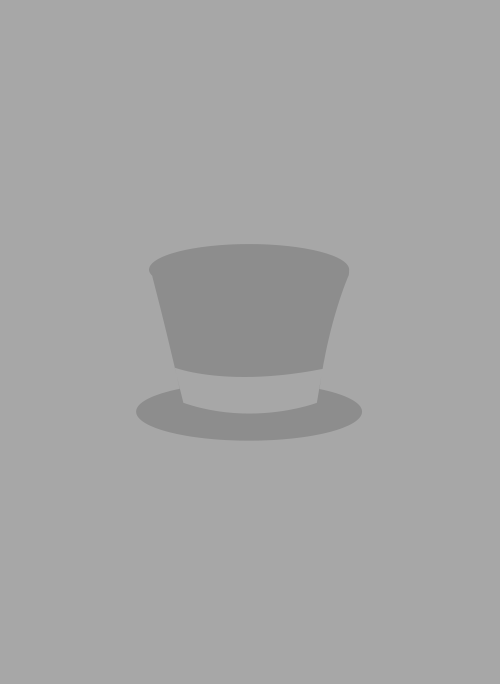「…」
紗波は無表情のまま、その子猫の行動を五秒ほど眺めると、白い手を伸ばした。
…ふわりと、子猫の頭に触れると、細い毛が手の平を包む。
ゆっくりと手を動かすと、子猫は気持ちよさそうに目をつぶり、床に寝そべった。
紗波が撫でるのをやめ、手を離すと、名残惜しそうにつぶらな瞳で、紗波の目を見てくる。
紗波が手を伸ばすと、子猫は嬉しそうに一声 鳴いた。
紗波は床に座り込んだまま、子猫を撫で続けた。
目はいつしか闇に慣れ、月の光は優しく美術室に差し込んでいる。
時刻は、十時三十五分ほど。
紗波が暫くの間、子猫を撫でていると、コツン、と、足音が聞こえた。
子猫の黒い耳が、ピンと立つ。
その足音は、時折 止まっては、また近づいてきた。
きっと、警備員だろう。
紗波は慌てず、床から立ち上がると、机に歩み寄り、その下に置いている暗幕を掴んだ。
ゴワゴワとした手触りの暗幕を被ると、机の下に潜り込もうとして__チラ、と子猫の方を向いた。
子猫が、何か言いたげに、紗波をジッと見ている。
目を逸らさず、紗波はその光る瞳を見つめ返した。
「…ミャー…」
紗波は、暗幕を引きずりながら子猫に近寄り、抱き上げると、一緒に机の下に潜った。
子猫に暗幕を被せ、息を押し殺す。
コツ、コツと足音が近くなり、やがて、美術室の前で止まった。
美術室の扉が開く。
紗波は、祐輝と、警備員から隠れたあの日の事を思い出した。
子猫の身体が触れる。