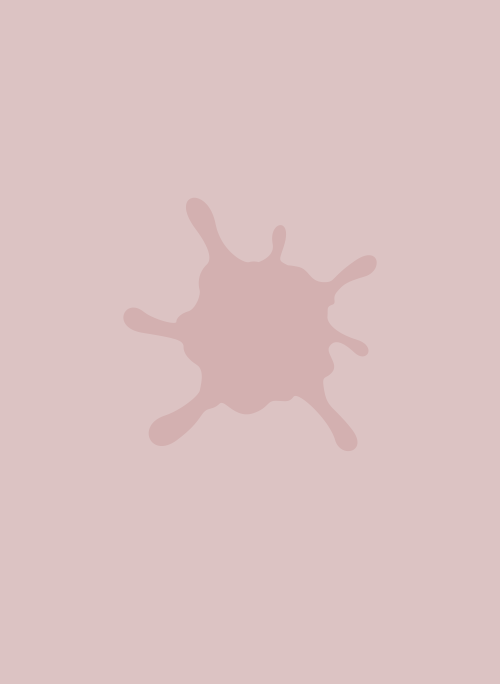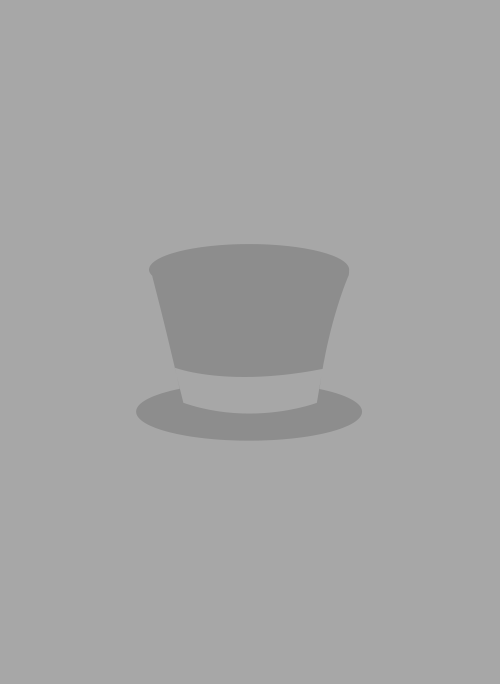「…ん…?」
ふくらはぎに何かが触れる感触がして、紗波は静かに目を開いた。
目の前は真っ暗で、物がよく見えない。
ぼんやりと物が浮かんで、窓から微かに差す月の光で、ここが美術室だと理解した。
まだ、ふくらはぎに、心地良い感触の何かが触れている。
紗波は暗闇に目が慣れるのを待ってから、その感触の正体を見るため、座り込んで後ろを向いた。
その瞬間、ふくらはぎに、冷たいザラリとした何かが当たって、濡れる感覚を感じた。
ゾク、と少し鳥肌が立って、紗波はふくらはぎを見た。
そして、その正体を見て、安堵する。
「…猫…?」
そこに居たのは、小さな小さな、一匹の黒猫だった。
「…ミャー…ン」
小さな黒猫は恐る恐るという風に鳴き、白く光るまん丸な瞳で、紗波の瞳をジッと見つめた。
紗波が窓側に目を逸らした。
猫は、目を合わせる事を嫌い、目を合わせる行為は『喧嘩を売る』という事になるからだ。
黒い子猫は、まだ、紗波の横顔を見つめている。
どこから来たのか、紗波が子猫と目を合わせる事はせず、美術室の中を見回した。
さぁっ…と、少し生温い風がどこかから吹いてくる。
目を凝らせば、一番端の窓が、開いているのが見えた。
あそこから来たのだろう。
子猫は、敵ではないと安心したのか、軟らかくか細い声で
「…ニャー…」
と鳴き、紗波の紺色のスカートに、身体をスリスリと擦り付けた。