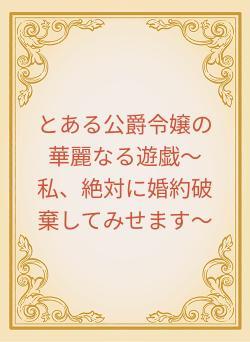家に帰ると、お母さんは、すぐさま受験の結果をみんなに話したらしく、いつのまにかに、家にたくさんの人がお祝いに来てくれていた。
最初は、驚いた私だけど、お父さんはもちろん、みんなもすごく喜んでくれて、
「よかったね」
そう言われるたびに、私は、お礼の言葉を言って微笑みを浮かべた。
―…そうこうしているうちに、気がつけば、さっきまで感じていたあの虚無感は、跡形もなく消えていた。
―――…
その夜、
ようやく、受験勉強から解放された私は、自分の部屋でゴロゴロと、くつろいでいると、
「ねーちゃん、本当にこれでいいの?」
突然、部屋の中に入ってきた旭が一言そう呟いた。
「ちょっと、入ってくるなら一言声ぐらいかけなきゃダメでしょ!」
私は、思わず、そう言い放ち、視線をそらす。
だって、
“真生くんにもう、会えなくなるよ?”
なんだか私には、旭の目が、そう訴えかけているように見えて、
すごく、胸が締め付けられるような気持ちになったから。