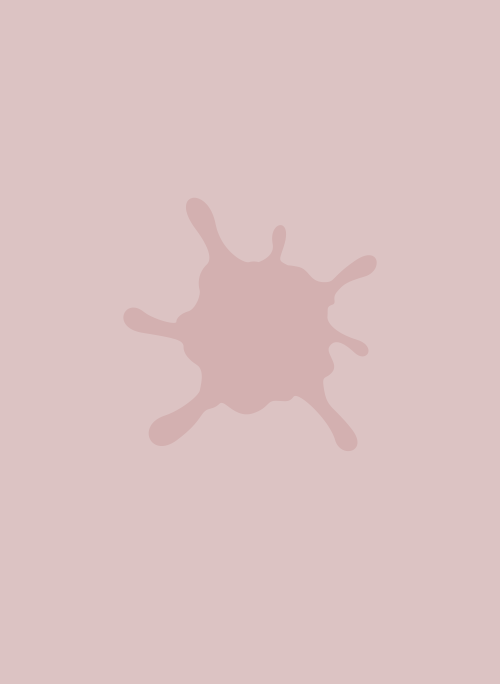その霊は、夢の中にまで入り込んでくるときもあった。
桜は眠るのがだんだん怖くなってきた。
子供のころのように、現実に起こったことが夢の中にまで入ってきて、そこでも現実のように追いかけ回されたり、殺されたりすることが度々あった。
その場合、目覚めた時には汗だくで、心臓はばくばくしていることが多い。そして、夢で良かったと胸を撫で下ろすことがほとんどだった。
大学生になった今では昔のように見ることはほとんど無くなったが、
あの時は夢の中にまであの女が入り込んで来て、
いつもそこで私を足下から引きずり込もうとするところで、恐怖に目が冷めるようになった。
天井を凝視する。
エアコンの効いた部屋はひんやりと冷たい。
耳を澄ませば、ベランダに置いてある室外機の回る音しか聞こえない。
しかし、室外機の横には血まみれの女が立っていて、
こっちをじっと見ていることになんて、部屋の中にいる桜には全く気付かなかった。
その手には指が一本も無く膨れあがり、血と肉と骨が見えている。
白目を向いた目は力無く、黒目にいたっては目の後ろの方へ隠れてしまっている。
ぽかんと開けている口元からは、血の混じったよだれと、
長い舌が顎のところまでダラリと伸びていた。
ゆらりと一度横に揺れた。
桜の部屋の前では、飼っている黒猫がベランダに目を向けたまま姿勢を低く保っている。
部屋の中に踏み入れない猫は賢明だ。
台所と部屋のぎりぎりのところにかわいらしい前足を揃え、耳を後ろに倒し、
瞬き一つしないで真っ黒い目をベランダの外のナニかへと向けていた。