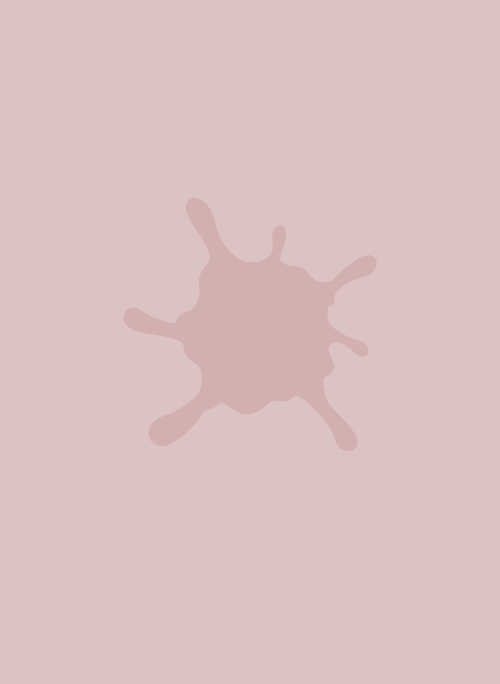「飲んで」
あざみが差し出してきた生臭い袋は暗闇の中で見た限りだとただの袋にしか見えない。
ぬめりのあるテカりに面食らうもだんだん息苦しくなり、視界もぼやけてきて頭も痛くなってきた。
「早くして、もう時間が無い。コッチに来るまでにコレを飲まないと」
「...だから...それはなんなの。君はいったい何を飲ませるつもりなの」
恐怖以外に感じるものがあるだろうか。
目の前にはこの世のものじゃない化け物がいて、その手にはよく分からない袋をぶらさげている。更には自分にその中身を飲めと言ってきているわけだ。
それが飲みたくなるようなおいしい飲み物なんかじゃないってことくらい大梯にだって分かる。
狭くなる視野は聴覚まで狂わせ、聞こえるはずのない叫び声が耳の奥にこびりつく。
その声が富多子のものだと理解するのに時間はかからなかった。
「助けたいなら...」
手を伸ばせば届く範囲にあるあざみの顔は楽しそうに笑っていて、魅入る。
袋の上部と下部は結ばれているが隙間からポタリポタリと液体がこぼれ落ちる。
上部の結び目をほどいたとき、ぶにゃりと鈍い音を立てて、ゼリーが揺れるようにぶるんと左右に揺れた。