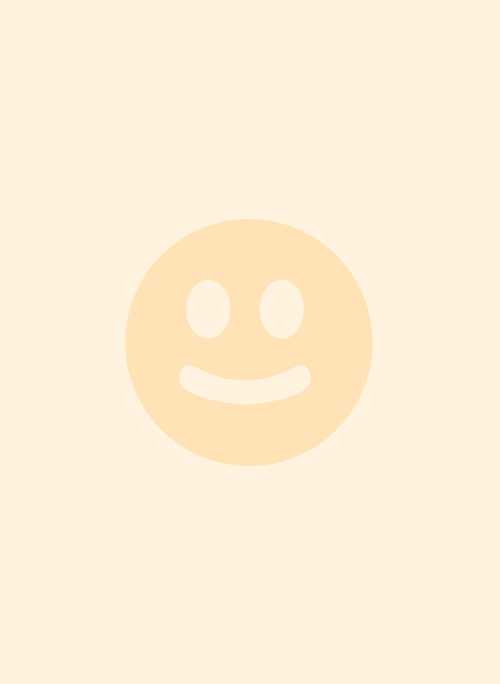さすがに、言いすぎたかもしれぬ。
しかし春芝を窺ってみると、彼は完璧に悪人扱いされたにもかかわらず、犬も食わぬ様子で屋台の並ぶ道を一望している。
「確かにそこは、おめえの言う通りかもしれねえな」
「な、なんでだい」
「俺あよ、どこへ行ったってそうなのさ。
そこに居るだけで、場の空気を暗くする」
春芝は開き直ったのか、言い含めようとしているのか、そう自虐した。
「悪魔ってのはよ、懊悩と悪心の象徴なんでい。
人に苦をもたらし、その苦による懊悩を喰らう」
「旦那も春芝も、意地は悪いけどそんな奴には見えないぜ。
物言いや態度は気にくわないけどな」
けっ。
春芝は破落戸さながらに刺々しく小石を蹴った。
「俺たち悪魔はよ、生まれながらに悪しきものとしてみなされるんでい。
特に、俺あ」
「お前は?」
「俺は特に、性根の腐った野郎なのさ。
地獄における、魔王に次ぐ高位の者。
悪さの度合いも並の比にならねえ。
人はみんな言うぜ。
誰よりも懊悩を好み、誰よりも人を陥れた奴だとよ」
菊之助は静かだ。
春芝を無視しているわけではない。
ただ春芝の言葉ひとつひとつを静聴し、独り考え込んでいる。
「だからな、菊之助よ。
人がちょっとでも焦ったり苦しんだりしたのを見るとよ、いけねえと分かっていても、その懊悩を喰いたくなっちまうんだ。
本能ってやつだな。
妖花屋で仕事を請け負った野郎どもが逃げまとう様を眺めるのも、楽しくってしかたがなかったぜ。
苦情はうるさいけどな」
「だからお前はあの時、笑ってたのかい」
「おうよ……」
春芝が認めたのを境に、菊之助は春芝の前に出て、どしん、と春芝に衝突した。
しかしその衝撃で、攻撃を仕掛けた菊之助のほうが転倒した。