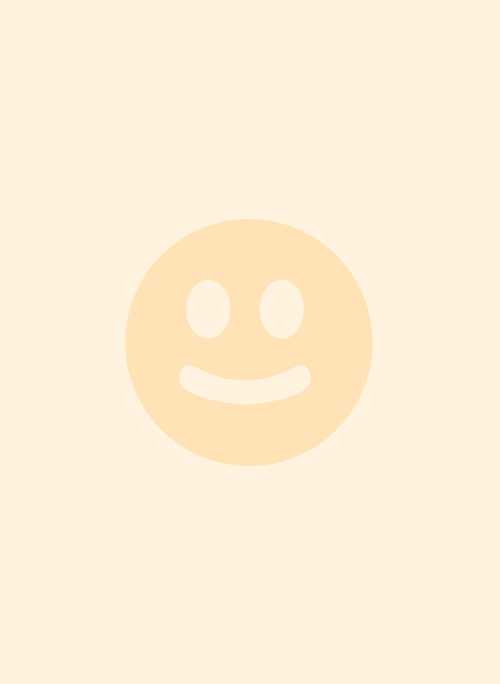*
春芝は眼球のみをせわしなく動かした。
右目は天を仰ぎ、左目は修験者へと向けられている。
「おい。
おめえ、段田か菊之助だろ。
そろせろ手え放せよ、猫みたいに掴みやがって」
「うるせえやい。
お前にゃ、ちょうどいいだろ」
修験者は地面に唾を吐いた。
「おめえ、菊之助だな。
おおかた段田が魔法で化かしてんだろうよ。
残念だが、俺にゃお見通しだぜ。
いや、視覚で見破ったわけじゃねえが、この江戸で俺を知ってんのは、おめえか段田くらいだからな」
品のない行動と言動からして、春芝はこの修験者が、少なくとも段田ではないと確信したらしかった。
修験者は春芝を放した。
修験者の体はみるみるうちに透けてゆき、その中から菊之助が現れる。
菊之助はそして、もの言いたげに振り返った。
「なんでい」
春芝が低く問うた。
「お前があの人に何を言ったのかはしらないけど、相手が嫌がってるのを分かってたなら、すぐにやめろよな」
菊之助はあの茶屋での一件を指しているのだろう。
「俺が嫌がらせをしてたと?」
「言い方は悪くなるけど、そう見えた」
「お前なあ、俺が完全に悪だって言いてえのか。
他人の事で、ああするなこうするなと抗議してきやがってよ」
春芝の言うことは、間違ってはいない。
しかし、菊之助はしかと見ていた。
百合が複雑な面持ちになった途端、春芝が美味い餌をもらったとばかりに、笑んだのを。
「そうとまでは言わないけどなあ……。
お前は、悪い事をしてるように見えた」
「理由があるのかよ」
「ある」
菊之助は出端を挫かれながらも、誰にも屈さぬ勢いで春芝に抗った。
「お前、怖い顔で笑ってたろ。
お前はなんだか、人が苦しんでるのを見て喜んでるみたいだったぞ。
いつも通りじゃなかった」
言った菊之助が、なぜか辛そうな顔になった。
事実は述べてやった。
しかし、人とは行動を起こしてから初めて後悔するものなのか、
(……言い過ぎたかな)
と、悔やんだ。