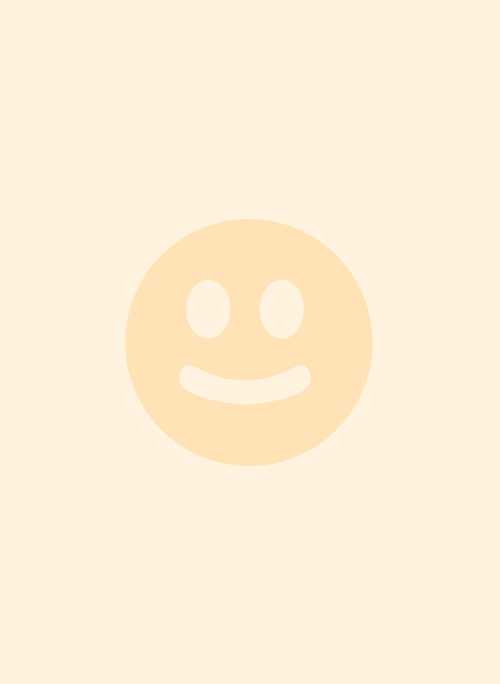「まあ、生きた鳥を?
まさか朝餉も食べずに、腹ぺこでここへ?」
それで空腹ゆえに目が回り、鳥さえ生きながらに取って食いたいという欲に駆られたのなら、まだうなづける。
「朝餉なんざ食わねえよ。
食わなくたって平気だ。
ただ、朝っぱらから段田の野郎がうるさいから、たまらず逃げてここに来たんでい。
あ、段田ってのは、俺の連れなんだが」
別に訊いてもいないし、教えてほしいわけでもなかったが、どうやら男の悪口と雑言が堰を切ったらしい。
日頃の鬱憤晴らしとばかりに、愚痴の濁流が迫り出す。
「あの野郎あ、いつだってやかましいんでい。
昼夜を問わず妖の話ばかり。
酷い時にゃ喋り通しで一睡もさせねえ。
全くもって自分勝手な野郎でよ。
ああ、ついでに野郎あ、弟でも兄貴でもねえからな」
糞味噌な悪口である。
喧嘩するほど仲が良いといわれるが、百合は菊と争ったことなど一度もないし、争って嫌われたくもない。
「おめえも、うるせえのは嫌いだろ」
男は百合に同意を求めてきた。
「そうでえすねえ……」
百合は相槌を打つ。
妹の菊も、決して静かな娘ではないが、百合は菊と喧嘩をしたことも、菊を叱ったこともない。
男はそんな百合の、僅かに淀んだ瞳を覗いていた。
「……わかったぞ。
おめえ、あんまり人に怒れないだろ」
男の一言に、百合は肩を竦ませた。
「どういう、ことです?」
「おめえさ、周りの奴に嫌われたくねえんだろう。
誰が見たって、優しい女になろうとしてる」
百合は目の色を変えた。
真剣な男の瞳孔を、突き刺さんばかりに見つめる。
人を苛めて、悦楽しているような眼ではなかった。
沼の底を思わす、無表情である。
「おめえが誰に、どう思われたくて大人しくしてんのかは、俺の知るところじゃあねえがな。だがよ、本当にそいつに離れてほしくねえなら、不満をぶちまけてやることも大事だぜ」
男はそう言い、辛辣に笑ってみせた。
勘定もできない人に言われたくなどない。
その言葉が喉をよじ登って口から出ようとするが、百合は固く唇を結ぶ。
いけない。
いくらなんでも、相手は客である。
しかし男の愉悦を含んだ表情を見ると、百合はなぜか、抑えきれなくなった。
「……あなたは、あたしの」
あたしたちのなにを分かって、そう言っているの?
つい男の前に鬼気迫る勢いで歩み出かけ、百合はふとその場に留まった。
きちちっ------と、愛らしく風流な小鳥のさえずりが聞こえる
歩行をやめた百合に続くように、冷静だった男が咄嗟に天を仰いだ。