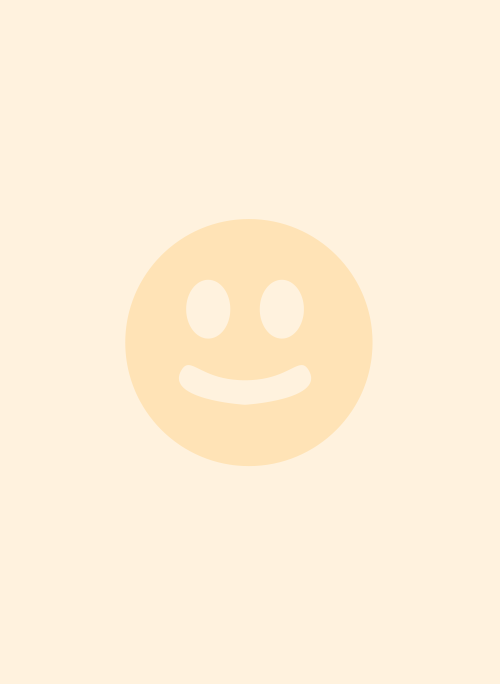「あんた、またお父(とう)の刀持ち出したのかい?」
百合がなにやら不穏そうに顔を曇らせた。
菊之助は心の臓の拍動を鎮めようとして息を止める。
だが氷のごとく冷たい汗が頬を伝う。
日が高いうち、菊之助が何をしていたのか。
それを百合に言うわけにはいかなかった。
「だ、だって、今は亡き、父ちゃんの刀だもの。
知ってるか?持ち主のない刀は死んだも同然なんだ。
だから、俺が持ってないと」
どんなでたらめだよ、そりゃあ。
己の口から並べた嘘八百に、菊之助は額を押さえて呆れたくなる。
持ち主のない刀は死んだも同然、などと。
歴史上の偉人の格言を引用したような物言いだったが、勿論これは菊之助が咄嗟に口走ったことなので、そのような云われはない。
刀の事になどさして興味もないのか、百合はざくざくと野菜を切る。
「でもねえ、ちっとは町娘らしい恰好をしたらどうなの」
百合が言った。
「どうしてさ」
「あんたは娘だろう。それなのに男みたいに刀まで持って。
嫁のもらい手がなくなっちまうよ」
「まさか。俺が嫁入りだなんて、狐の嫁入りよりも面妖だぜ」
それに嫁入りの心配をしなければならないのは、菊之助ではなく、娘盛りな百合のほうである。
(俺が嫁入りだなんて)
菊之助は自嘲した。