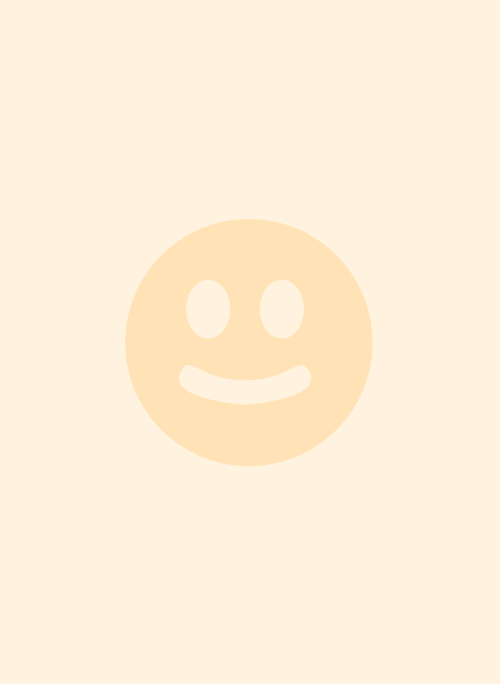「じゃあ、最初から口入れ処なんかにするんじゃなくて、妖怪退治屋として店を構えておけばいいじゃないか」
「口入れ処として妖花屋を構えたわけは、私の契約者を選定するためさ。妖を前にして平気でいられる人を捜していた。それで、ここを訪れた浪人の中で、君だけが仕事を成功させた。だから私は、君を契約者に選んだという事さ」
そして契約者が決まった今、もう浪人を集める必要もなくなり、本命である、妖怪退治を生業とする店へと切り替えた、というわけだ。段田と一緒に妖怪退治に向かう人間が一人いればいいのだから、他に誰かを使う必要はないらしい。
だいたいの話を聞き終えた菊之助は、ぽんと拳を掌に乗せる。
「なんだあ。じゃあ旦那は俺意外に誰かを使う気なんて、さらさらなかったってことか」
「そういうことだよ」
自分の思惑通りに事を運べたからか、段田は鼻を高くしている。
そう言われると、菊之助は高揚した。自分の確たる居場所を持ったような気分になる。
(なんだかやる気が出てきたぞ)
お調子者の菊之助は、すっかりやる気満々である。
しかしそこで段田が、
「まだ仕事は入ってきていないぞ」
と菊之助のやる気の腰を折る。
「それまで茶でも飲んで待っていたまえ」
段田が言うなり、自分の手で棚から湯呑を取り出し、それに茶を注ぎ始めた。いつものように湯飲みが勝手に浮いたりはしない。
「どうぞ、お侍様」
段田はからかっているのか、心にもない事を口にして、男女問わず骨抜きになる笑顔で菊之助に湯飲みを渡す。
小さく礼をして、茶を口に含むと、それはいつもの湯のように薄い茶ではなく、茶屋に出ているような味の濃いものだった。
「ん」菊之助は瞬いて、茶を飲みほした。
いつも薄い茶しか出さないのに、今日の段田はいつになく優しい。
「すっかり飼いならされてやがる」
美味い茶に喉を潤す菊之助に、春芝は膝に頬杖をついて呟く。
すると。
「あのう……」
暖簾を分けて、丸い目をした町娘が入ってきた。もちろん見知らぬ娘だ。
客人と思しい。
「お待ちしていましたよ」
段田は早々に立ち上がり、あたかも町娘自身を待っていたかのような語調で迎える。
客人らしき町娘は、妖花屋の中の奇妙な装飾と、艶やかな美貌の段田に目を奪われている。
「あの、妖退治をしてくださるというのは、ここでございましょうか?」
菊之助と違って、町娘は腰が低い。
「間違いはありませんよ。ようこそ、妖花屋へ」
うなづくや、段田は目を輝かせて部屋の奥へと振り返る。
“仕事だ、菊之助”
段田の嬉々とした眼差しは、菊之助にそう伝えているようだった。
「------おう!」
短く太い返事をし、菊之助は鯉口に触れた。
かちりっ、と刀の鳴る音が、妖花屋の中で小さくこだまするのだった。