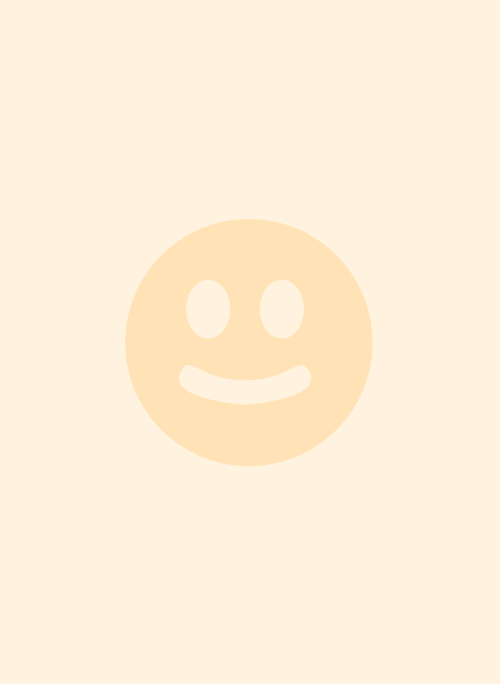これはさすがに忘れてはいない。段田が契約の代償として、菊之助の何を欲しがっているのかを。
菊之助と百合の許へ、段田がじりじりと歩み寄る。春芝は姉妹を挟み撃ちにするように、二人の傍に移る。
段田は胡散臭い笑みを浮かべていた。
「初めまして、菊之助の姉上の百合どの」
名を呼ばれて、百合も剣呑な目つきで立ち上がる。
「そういうあなたは、誰?」
「口入れ処・妖花屋の者------段田李音と申しまする。以後、お見知りおきを」
段田は公家の姫君のように礼儀正しい。しかし作ったような笑みと形式的な挨拶が、かえって余計にいかがわしい。
そんな怪しげな笑みのまま、段田は続ける。
「可愛い妹には傷ついてほしくない……。あなたの深くも過剰な愛には恐れ入ります。しかし菊之助は、愛するあなたを救うために私に命を差し出した」
聞き捨てならぬ話と思ったのか、百合は凛として身構え、段田に問う。
「どういうこと?」
「目で見て察することは難しいでしょうが、私と、あちらに立つ禿の男。我々は人ならぬ化生の者にございます。我らは菊之助の魂を貰い受けるという条件で妹君と手を組み、貴女を救い出すために戦ったのです」
段田は恩着せがましい。自分は半ば己の欲望で串刺し公と戦っていたくせに、よくそんな事が言えたものだ。
菊之助は不満げな瞳で段田を射る。
この美貌の男が何を言いたいのか。
この一件の騒動についてほとんど何も知らない百合にも、なんとなく察しがついた。
百合は咄嗟に段田の前に立ちはだかる。
「殺すなら、あたしを殺しなさいよ」
「人聞きの悪い事を言わないでもらいたい」
段田は顎を上げる。
その直後、百合の手首を春芝が強く掴んだ。百合は力ずくで振り解こうとしたが、春芝の手は微動もしない。
「なにすんのさ」
「黙って見ていな」
抗議する百合を鎮圧し、春芝は段田と対峙する。
「早く終わらせろよ。この女が煩いからな」
春芝は言う。菊之助を殺したところで百合は鎮まらないだろうが、段田は躊躇なくうなづく。
春芝を振り払おうともがいている百合を見ていると、菊之助は申し訳ない気持ちになった。百合を救うために、悪魔に命を引き渡したのに、よりによって百合の前で死ぬことになろうとは。
しかし、命を乞うわけにはいかない。
約束は約束であるし、彼ら悪魔たちのお蔭で百合を救い出せたのだ。
「ごめんよ、姉ちゃん。旦那との約束だから」菊之助はすまなさそうに眉を下げた。
「男に二言はねえんだ」
そう言って、菊之助は段田の前に踏み出した。男に二言はない、というが、菊之助は男のふりをしていても女である。
「あんた、娘じゃないか」
百合に言い返されるが、菊之助はたまらず聞かぬふりをする。
「……さあ、煮るなり焼くなり好きにしろ」
菊之助は凛々しく段田の前にそびえ立つ。
絢爛かつ艶やかな表情の悪魔は、腰を曲げ、じっと菊之助の瞳を覗き込む。
「怖いかい?」
段田が優しく訊く。
「怖いもんか」
猪口才な口を叩くが、菊之助は震えていた。いくら気丈であっても、死ぬのは怖い。なるたけ、どんなふうに魂を取られるのかは想像しないように心掛けるも、やはり考えてしまう。
「なら、いい」
段田は言うなり、さっと菊之助に腕を伸ばした。
ぷすり、と軽い音がして。
菊之助は首の後ろで一つに括った髪に、何かが刺さるのを感じた。思わずそこに手をやる。刺さっているのは、硬質な棒だ。先端には丸い珠らしき物も付いている。
触っただけでも、それが何なのか解った。
これは簪である。
引き抜き、手に取ってみてみると、それは黒い珠に奇怪な花が描かれた玉かんざしであった。
作りや見た目は、決して華やかではない。簪全体が黒で統一されているのは美しいが、その珠に描かれている花が不気味だ。桔梗にも似たその花は血のように赤く、二本の雄しべにはそれぞれ眼球がついている。
(これは)菊之助はこの花に見覚えがあった。
妖花屋の掛け軸に描かれていた、あの花である。
段田は菊之助から離れ、下駄を鳴らして百合の前までやってくるなり、そこに片膝を突いた。
「約束通り、菊之助の命は頂戴いたしまた。------今より、あのおなご侍は、我ら妖花屋の一員です」
百合はもちろん、菊之助も目をぱちくりとさせた。
「なにしろ、妖花屋は人手不足ですからねえ。猫の手も借りたいぐらいですから、こんなにも腕の立つお侍がいてくれたら心強い」
段田は顔を菊之助のほうにやって、ふふん、と皮肉っぽく笑う。腕が立つなんて思っていないんだけれどね、とばかりの、小馬鹿にした笑みである。
そして段田は踵を返し、菊之助を通り越してその場を去ろうとする。
「ちょ、ちょいと待ってくれよ」
遠ざかってゆく段田を、菊之助は呼び止めた。
「じゃあ、旦那たちは、俺の魂を取らないってことなのかい」
「うむ。そのかわり君には、死ぬまで妖花屋で働いてもらう。その簪は餞別だ」
「なんで簪、なんだ?」
「君がおなごだという証拠さ。もう他の口入れ処に行かせてやるつもりはないからね。君が男を装う必要もない」
私たちは知っている上で、君を使おうと思っているのだからね。
段田はそして、びしりと菊之助を指差した。
「明日からは、酉の刻までに妖花屋に来てもらう。遅れたら、お仕置に地下にある書庫の片づけだ」
段田は菊之助を扱き下ろす気でいる。
「そういうこったな」
春芝は百合の手を放し、さっさと歩き出した段田に続いた。後頭部で手を組み、気怠そうに欠伸をする。
空はいつの間にか、浅い藍色へと変わり、宵の空が白んできている。そういえばそろそろ夜明けだ。
段田は肩がこったのか、二の腕を回している。
「さあて、春芝よ。夜が明ける前に帰るとしようか」
「舞踏会はもうお開きだな」
「いやはや。本当に愉快な舞踏会だったよ」
弁天島から遠ざかってゆく二人は、あたかも本当に舞踏会に言ったかのような口ぶりである。僅かな明かりに照らされた地面に、二つの影が揺れる。どちらの影も歪な形状で、とても人の形には見えない。
呆然として彼らを見送っていた菊之助は、ふと段田が寄越した簪に視線をやった。芳しい蜜の香りが、その簪から漂っていたのだった。
“妖花とは、苦労した人の骸に咲き、甘美な蜜を作る花”
あの掛け軸に描かれた花について、いつぞや段田が説明していた気がする。
菊之助は暫時その簪を見つめて、再び一つに括った髪へと差し込んだ。
***
翌日から、江戸は本格的な秋を迎え始めた。山は赤、黄、茶、橙に彩られ、江戸のあちこちに植えられた楓が、夕暮れの太陽にも劣らぬほど深い赤に染まっている。
しかし、秋の始まりとはいえ、まだ日中は長閑で暖かい。温暖な風が妖花屋の暖簾を掻き分け、中へと入ってくる。
段田は、相変わらず奇怪な道具が飾られた部屋の隅で、まだ寝るには早い申の刻から、ごろりと寝そべっているのだった。
妖たちは、早くもヴラドの消滅を察したのか、一夜にして山からなだれ込むように江戸に舞い戻ってきた。神隠し騒動も、いづれは根拠なき“人の噂”に呑み込まれ、その真相は当事者のみぞ知る話になるだろう。
そしてまた、黒煙の化物ではなく、妖が人を騒がせるようになる。妖たちの悪戯で困り果てた人間が、妖花屋に仕事を持ってくるのだ。
「なんだか暇そうだな、ダンタリオンよ」
階段に腰を掛け、春芝ははぐはぐとカステラを食べている。
「うるさいのがいないからねえ」
段田は怠惰な猫又のように大欠伸をし、傍に置いておいた絵巻を開く。百鬼夜行絵巻である。
「なんだよ、おめえ、あんな男みてえな小娘に惚れたのか?」
茶化す春芝を、段田は「単細胞め」と舌を見せる。
「私が愛しているのは妖だけさ。それ以外は愛する理由がない」
「ならば、どうして菊之助をここに留めることにした?あの程度の剣士なら、江戸の中にもいるだろう」
春芝が、なにやら探るように追及してくる。
ふむ、と段田はしばし考える素振りをする。
どうやら小娘を妖花屋に留めておこうと思った理由が、自分自身でもよく分からないらしい。
「人の“情”に生きる人間は、妖ほどではないが興味深いと思ってね」
人の情に生きる人間------菊之助の事を指しているらしい。
すると、「む」と春芝が戸口を凝視する。
「------旦那!春芝!」
噂をすれば、菊之助が暖簾を跳ね除けて妖花屋にやってきた。剣呑にも、菊之助は襷をかけ、頭に鉢巻を巻いている。さらにはいつも通り首の後ろで一つに括った髪に、あの不気味な簪を挿している。
「えらく元気だなあ、おい。道場破りでもしに行くのかよ」
春芝は菊之助の気合いの入った服装に、半ば呆れている。
「ああ、姉ちゃんがやってくれたんだ。女だからってなめられるんじゃないよ、ってさ」
以前の百合は、女だからこそ大切にしようという姿勢だったのに、一夜で随分と考えが変わったものだ。
「そんなことより。旦那、妖花屋の暖簾が大変な事になっちまってるよっ」
菊之助は騒がしい。
段田は億劫そうに、重い身体をのっそりと起こす。
「大変なこと、とは?」
「暖簾に書いてあった“口入れ処”の文字が消えちまってるんだ。これじゃあ妖花屋が何の店か分かりゃしないよ」
身振り手振りで伝えた菊之助だが、段田も春芝も驚かない。なんだそんなことか、とばかりの索漠とした空気が妖花屋の中に広がる。
「------菊之助よ。それは私が故意にやったことだ」段田が言った。
「なんだって?」
「ここはもう口入れ処ではない、ということさ。今日からは妖怪退治屋だ。小さく書いてあったろう、暖簾の端に」
「はあ……?」
菊之助は口をあんぐりと開け、肝を潰す。
妖怪退治を生業とする店など、聞いたことがない。妖怪退治で稼ぐ、という事自体はあり得るかもしれないが、それを稼業として店を出すなど前代未聞だ。