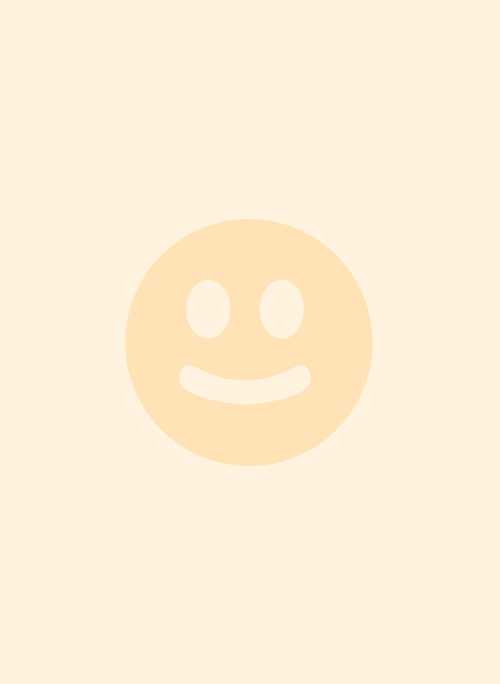目の端には、人の目に見えないのをいいことに、稲荷寿司をかっぱらって食う化け兎が映る。
妖というのは気楽でいい。
「妖、ねえ」
人外なる妖の事など考えている場合ではなかろうに、菊之助はふとして妖にまつわる記憶を思い起こした。
まだ幼き頃だったろうか、長屋の天井からぶら下がってきた猿にも似た妖を、面白がって鞘の先で突いたのだ。
『おい、痛いぞっ。やめぬか小僧っ』
しゃがれた声で叱責を受けても、菊之助はきゃはきゃはと妖を鞘で連打するだけだ。
これには妖のほうが降参して天井裏へと逃げて行ってしまったのだった。
『お菊ったら、宙を突っついてなにしてるのさ』
百合は当時そう言った。
どうやらあの妖は菊之助にしか視えなかったらしい。
後に知ったことだが、妖の姿を目に映す人間は数人に一人はいて、そう珍しいことではないそうだ。
だから菊之助のような者は、この江戸にだってごまんといるはずだと、手前の長屋に住む元気な老獪が教えてくれた。
余談だが、菊之助は妖が視えて得したことなど、ただの一度もない。
それに、
(そんなことよりも、仕事を探さなきゃなあ)
子供侍の菊之助に任せられる仕事は非常に少なく、あちらこちらの口入れ処を回って探す必要がある。
面倒だ。
通っていた口入れ処は、八丁堀から北上した場所にある。
菊之助はそこから南下して、日本橋のほうの町へ移動することにした。