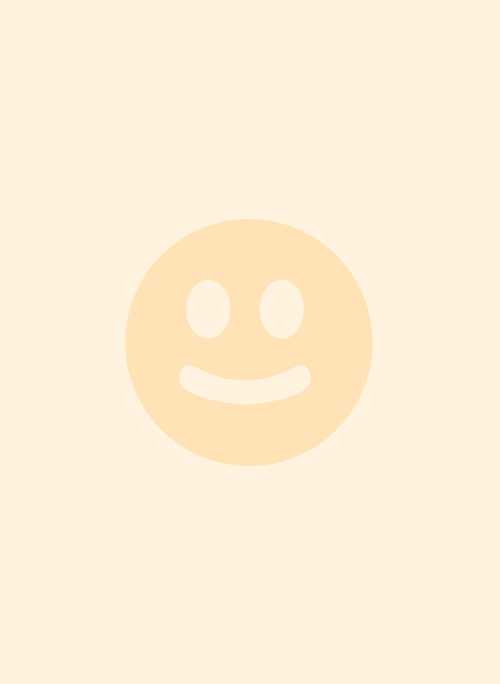*
「ううむ……」
病に伏せたような呻き声をあげて、菊之助はようやく、六百本に及ぶ素振りを終えて脱力した。
出来たばかりの肉刺が潰れて痛む。
それでも刀を振った数だけ、僅かながら力がつく。
自分たちは、柳生十兵衛だとか宮本武蔵だとかのように、図抜けてすばらしい剣の天稟を持ってはいないのだから、強くなりたくば、こうして暇なときに木刀を振る他はない。
(一昨日のちびすけ)
しんとした昼前の長屋に帰し、菊之助はあの、兄を攫われた小僧の哭するさまを思い浮かべた。
凄惨そのものであった。
(だれだって親しい人が消えりゃ、寂しくなるってもんだ)
あの小僧も、形も得体も分からぬ怪物に兄をかどわかされて、さぞ、怖かったろう。
そして今は、心細いだろう。
菊之助は眉間に皺を作った。
自分にとっての最悪の悲劇とは、考えずとも知れている。
(あの化けもんが。
一人や二人攫ったくらいじゃ、飽き足らねえってことか)
黒煙が人を攫う瞬間を小僧が視たのだから、確かだ。
しかし黒煙自体が原因だとすると、百舌や南蛮風の男はどうなるのか。
南蛮風の男が襲い掛かってきたという、毛女郎の証言。
百舌に呑み込まれたという、猫の証言。
二つとも『黒い煙』という言葉で繋がりがあるが、その二つに何の関係があるのか。
考察の深みにはまるほど、菊之助は頭痛に苛まれた。
(俺にわかるわけがないじゃないか)
首を垂れて、菊之助は竃の下から砥石を引き出した。
それに刀を当て、丹精して研ぐ。
大雑把でがさつな菊之助だが、好きこそものの上手なれとはよく言ったもので、己の刀を磨く作業にだけは、ぬかりなく取り組めた。
研ぎ澄まされた刃を光らせる。
菊之助は太い眉をしかめたままだ。
(俺あ、この剣で……)
姉ちゃんを守っていくんだ。
菊之助の手にある刀は、浪人の侍だった父の形見であり、菊之助の家族を養ってきたものだ。
だが刀を持っているだけのか弱いおなごの身では、百合を人外のものの手から守れるはずがない。
だから今まで鍛えてきたのだ。
あの化物に勝てるかどうかも不明瞭なのに、菊之助は断固として思うのだった。