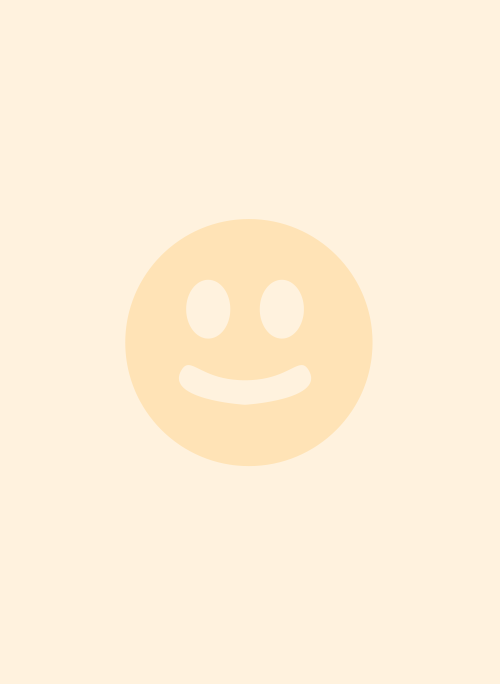*
提燈が一つや二つしか灯っていない道はいつも以上に暗い。
ぽつんと周囲を照らしていた湯屋の明かりさえ、姉妹が数丈も進むとすぐさま闇に埋まった。
湯屋に来た頃はまだ暮れ六つ。
そこから大して時間は立っていないはずだった。
しかし、日はとうに沈みきっている。
さわわ、と暖風が菊之助の無造作にはみ出た前髪を躍らせる。
今は夏の終わりがけ。
秋分にはまだ早い。
風が暖かいのもごく自然である。
しかし風を受けた菊之助は、だだくさに束ねた黒髪の下に触れた。
鳥肌が立っている。
しかも予兆もなく、だ。
------菊之助は分かった。
この鳥肌は寒さゆえに出るものではないと。敵の毒刃がこちらに狙いを定めた瞬間にできるものだ。
毛女郎の時もそうだった。
この緊張が体中を走り抜ける。
(何か来るぞ)
江戸の人々は夜でも元気だ。
特に呑んだくれの浪人が道端をふらついていることが多い。
しかし、この道はその浪人さえもいない。
人は居ない、が、誰かの気配がする。
「何だか、ちょいと静かだね」
百合が言った。
「うん……」
菊之助が低く返事をする。
菊之助も百合も、この状況を不穏と察したと思われる。
「誰もいないのかしら。
ねえ、お菊……」
声をかけて、百合は息を詰まらせた。
暗黒に包まれた妹。
しかしその眼はいつになく剣気に煌めいている。
山犬が如く五感を澄ますそのさまは、あたかも、戦に赴く武士のようであった。