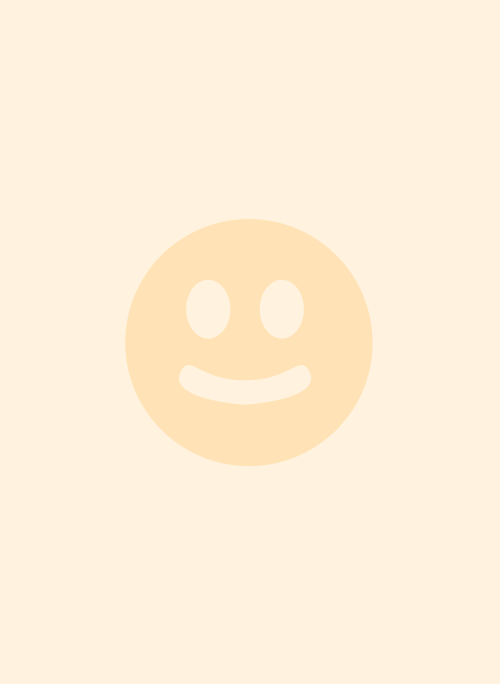「言っとくがよ、俺あ誰かのために江戸を歩き回ってたんじゃねえ。
俺あ、ただ、おめえのつまらん夜話から逃れるために店を出た。
怪物の正体を探ってたのは、そのついでさ」
「つまらないとは何だ」
「つまらねえだろうが。
しかも、おめえの話はいつまでたっても終わらねえ」
「あんたには分からない美学ってやつさ」
段田は虫の居所を悪くした。
そんな段田を、勝手に言ってやがれ、と捨ておいて、春芝は虚空を駆る雀三羽を黒目で追った。
「……雀、茶屋にもいたぜ。
町のいたるところで、そいつを見かけた。
きちきちって鳴いてる、ちっこくて可愛い雀だ。
眼をぎらぎらさせて、町中を飛び回ってやがる」
「それ、雀じゃなくて百舌だろう」
「そうかよ」
春芝は肩をそびやかす。
曰く―――。
今朝に妖花屋を出て江戸の町をそぞろ歩きしている間、春芝はその鳥を三回も目撃したのだという。
「ははん。
春芝、あんたはその百舌が神隠しの元凶と踏んだな」
「見た目はただの鳥だがよ、あいつあ、なんだか執拗に人ばっかり眺めてたぜ」
それはあたかも、獲物の虫を捉えるような眼で、人を見おろしていたのだという。
これだけでは証拠にならぬが、人外のものには図抜けた洞察力が備わっているのか、春芝はすでに確信しているらしかった。
あれはただならぬものである、と。
「神隠しをしているのは、黒煙を取り見た男と聞いたが」
段田が言いながら、小脇に抱えた書物の頁をめくる。
「ルシファーの悪い予感は、よく的中するからね。
信ずるに値する、かもしれない」
「当たろうが外れようが、そいつのせいで人がどうなろうが、俺の知ったことじゃねえぜ」
ルシファー、もとい春芝は腕を組んで吐き捨てた。
「だが人間は悪魔の私腹を肥やすための、煩悩と苦悶の源。
絶滅されちゃ困るからな」
だから、いざとなったら、その敵を容赦なく叩き潰すつもりでいる。
そう春芝は告げる。