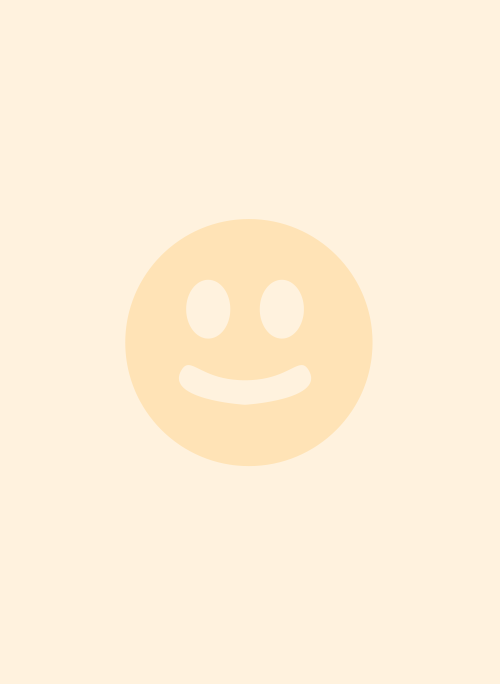「だいいち、俺がそこらをほっつき歩いてて、お前に何か不都合でもあるのかよ」
「不都合はあるね。
まず、依頼人が来ても私では対応できない。
私は普通の人には視えないからね。
あと、あんたの性質の問題もある。
前にいた国でも、それで問題を起こしただろう」
春芝の、《人に苦を与え懊悩を喰う》という性質には、前科があるとみえた。
痛い所を突かれたようで、春芝は眉をひそめてのけぞった。
目を泳がせ、この状況を打破し、段田を黙らせる方法を探っている。
そして、
「俺がよく外に出てくのも、そもそもの原因はおめえだろうが」
びしりっ、と春芝が段田を指差した。
段田は、証拠はあるのかねと言いたげに顔を背けて、意地悪く吐息をついた。
「私は何もしていないね」
「しらばっくれるんじゃねえ。
毎夜毎夜と怪しげな書物を持ってきて読んでは、にやにやとしやがってよ。
いや、それだけならいい。
ついには俺を起こして、この妖はな、とか。
妖の事ばっかり、一人でべらべらと喋りやがる。
そういうのを迷惑ってんでい」
「それのどこが迷惑だというんだ」
段田は言うが、菊之助からしても夜通しで喋りかけられるのは、迷惑この上ない。
「どう考えても、あれは安眠妨害だろうが。
だから俺あ、ちょくちょく妖花屋から出て行ったんでえ」
菊之助は段田と春芝、どちらの味方にもつく気はなかったが、こればかりは春芝に同情した。
他人の趣味の話で幾夜も叩き起こされるなどという事があっては、一度くらい独り静かに夜を過ごしたくもなるだろう。
己の思想を他人に押し付けるな、といつぞや段田は説教してきたが、段田の方こそ自分の趣味を同胞に押し付けて困らせているではないか。