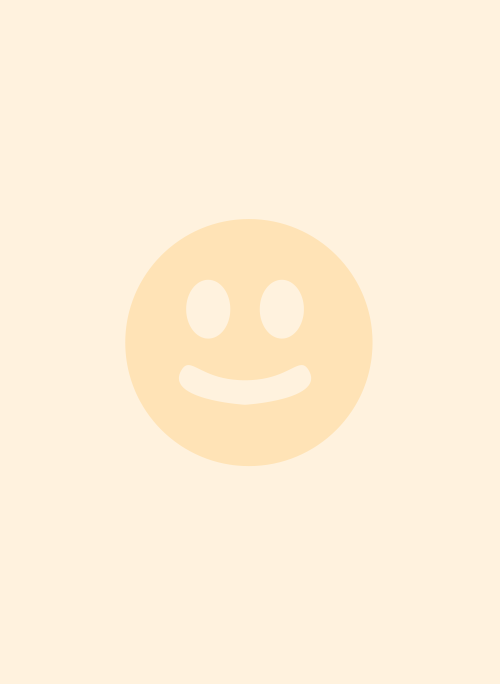「なあ姉ちゃんよ。そっちこそ、もう二十になるんだし、いい男が見つかったっていいんじゃないか?」
百合は、何の冗談か、とばかりに口元に手を当てて含み笑いをした。
「何を言い出すかと思えば、あんたはどこの父親だい」
「ほら、姉ちゃんはもう立派な女だぜ。俺ももう十六だしよ、日雇い仕事もできる。
姉ちゃんが無理して働いて、養うこたあ……」
「あたしゃ無理なんかしていないよ。茶屋で働くのも楽しいし、嫌な事なんざ、これっぽちもないね」
そういう心配はもっと大きくなってからしな。
百合は自分よりも頭一つ分ほど背が高い妹に言うのだった。
菊之助がこのように切り出したことは一度や二度ではない。
物騒な仕事をし始めてかれこれ二年間、一心に妹ばかりを気に掛ける姉に、菊之助は心苦しささえ覚えていた。
そしてもう一つ。
(まだ子供扱いかよ)
菊之助は内心で舌打ちする。
齢十六ともなれば、大人と同じく働いていて当然である。
もっとも、家を守るのが枠目である女は働くことを強いられない。
が、この姉妹の場合、支えてくれる父も夫もいないので働かねばならないのだ。
姉ばかりに家を任せるのは、菊之助としては非常に不愉快だ。
それこそ、子供扱いされるのと同じくらいに。
「俺は大人だ」
言い募ったが、萎んだ声が出た。
それは百合にさえ届かない。
彼女は竃の様子を見ているだけだった。
「ああ、そういえば」
ふと百合が顔を上げた。
「日雇い仕事って言ったけど、危なっかしい仕事だけはしないどくれよね」
ぎくり。
百合に痛い所を突かれ、菊之助は目を泳がせた。