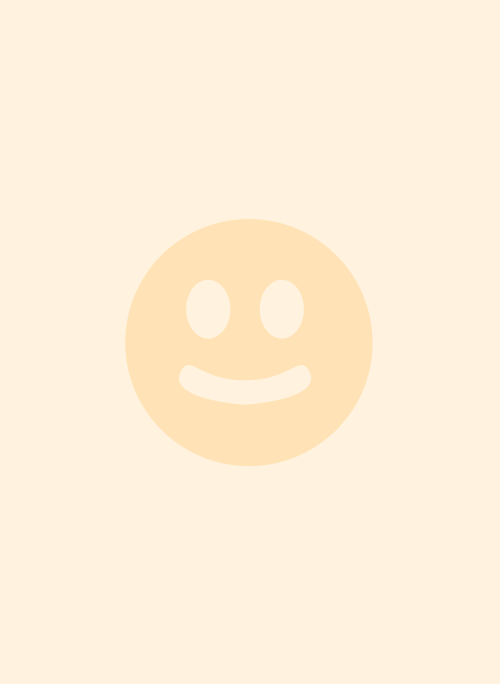*
その少女が十一になる頃、だったろうか。
「お百合、お菊!」
顔面蒼白で長屋の戸も叩かず入ってきたのは、近所の長屋に住む指をくわえたまだ三つの小僧・蓮兵衛と、その母だった。
「どうしたの?」
起床した少女の姉・百合が、蓮兵衛の母となにか話をし、そして、はっと手で口を塞いだ。
それがぼんやりと、騒々しい声によって目を覚ました少女・菊の視界に映っていた。
わんぱくな菊は、浪人の父の刀に憧れて、ずっと昼に木刀を振り回し、つい先ほどまで疲れて昏睡していたのだった。
百合がこの世の終わりとばかりの面になり、長屋を飛び出した。
姉ちゃん、どうしたんだよう。
うつろな状態で、何があったかも考えずに、菊もよろよろと百合たちを追った。
そうして辿り着いたのは、小さな自身番所。
その番所の前で、真紅の池が広がっている。
「ああ……」
百合がそこに崩れ落ちた。
血の池の出所であろう人は、うつ伏せに倒れているので、顔が分からない。
しかし顔が見えずとも、百合も菊之助も娘であるから分かった。
色褪せた藍の小袖に、同色の袴。
月代髷がほどけて、髪が一筋、また一筋と血だまりに浸る。
にわかに上げられた手が握っているのは、刀。
「お、おとう」
やっとのことで百合が言葉を絞った。
血の池に転がっている屍こそ、菊たちの父親である。
人手不足の番所で雇われ、こき使われていた、浪人の父だ。
俺はな、これでも剣の腕はあるんだぜ、などと言っていた彼が、胴をざっくりと斬り下げられ、死している。
誰が殺したのか。
番所に集まった者は皆、
「辻斬りにやられちまったか」
と、口をそろえた。
ある者は両目を押さえ、またある者は残された子供たちに寄り添った。