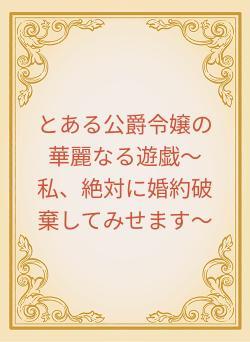「ダンスの時間などもう少ししたから行けばよいではないか?カローナ姫、あなたはすでに私の妃なのですから」
「いや、そういう訳には…」
彼女の必死な言葉にもシルヴィはそう言って耳をかそうとはしなかった。
…っ、もう無理!一発殴ってやりたい!
そう考えて、思わずギュッと、握った拳をさらに握りしめた時。
彼女とシルヴィの間に誰かが割って入り、カローナを自分の背中に隠して守ってくれる。
「…!?だ、誰だ貴様は!」
シルヴィが驚いたように声をあげた。
すると。
「はじめまして。私は、カローナの友人のルイと申します」
…!?