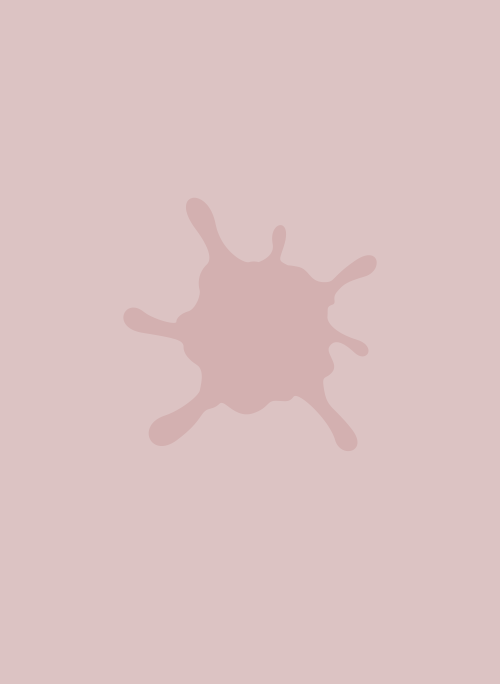「そちらの世界のイギリス王室御用達って言われている紅茶だったんですけど、お口に合いませんでしたか」
白く骨張った長い指で自分の前に置かれている(私の)マグカップを持ち上げようとした。
……それ、本気の紅茶? いやいや、本題の元がずれてる。
違うでしょ。紅茶みたいなものの本題に入ってどうする。
てかこんな場所でイギリス王室御用達ってピンとこないけど、高そうなイメージ。
しかし、それだけでおいしそうって思う私は、不思議なことに徐々に「紅茶を飲みたいかもしれない」と頭がシフトチェンジっていうどうしようもない頭のつくり。
だけどここはひとつ私が望んでいる本題に入ってほしいと思うのもある。
「あ、ちょっと待ってね」
伸ばされたアンジュラの指よりも素早くマグカップの奪取に成功した。
「だから、飲まないなんて言ってない。これ熱いから冷ましてるの」
「……」
そうでしたか。と、行き場の無くした指を、またもピアノの鍵盤を優しく撫でるように小指から順に折り曲げて、ローブの中に戻した。
その仕草……癖なんだ。
死神にも癖ってものがあるんだ。
なんか、不思議とほっこりする自分がいた。