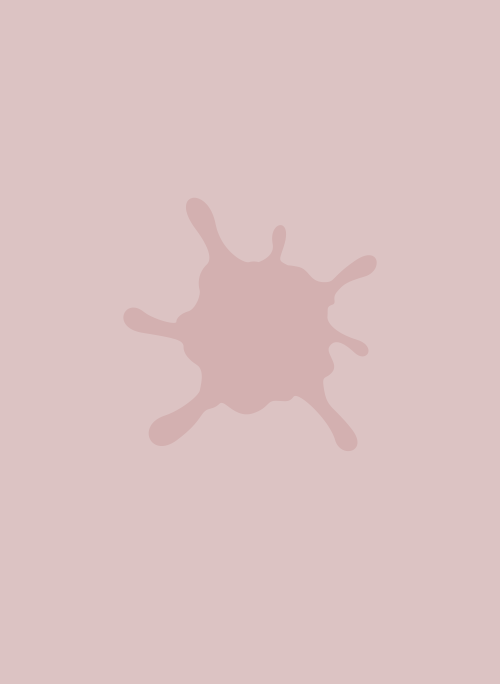「ですから、その気持ちは無かったことに。それが一番です」
「何それ! 無かったことにとかできるわけないじゃん。どうしたらそういう結果に結びつくの? だって私たち、合うんじゃないの? 今アンジュラそう言ったよ。私だってそう思うし、だったらそれじゃぁこれから一緒に! あの仕事だって私ぜんぜん平気だし……」
「……ですから、私はあなたのことなんてなんとも思っていないんですよ」
「嘘だ! 本当に?」嘘だ。
「はは。嘘じゃありません。本当に、」
「本当に?」なに?
「面倒くさいんですよ。あなたがいると」
グサッときた。ドキッとした。
面倒くさい。面倒くさい。面倒くさい。面倒くさい。面倒くさい。面倒くさい。面倒くさい…………
頭の中にその言葉がずっと回ってる。
あれ? なんだ? 目が霞む。
ぱちぱちと瞬きをしても霞が取れない。
手でごしごしこすっても、余計白く霞んでいく。
「早かったですねぇ、もう少しかかると思っていましたが。何も変じゃありません。薬が効いてきただけです」
薬?
そうだ。
あの小瓶の中の薬、紅茶に落として、それ私飲んじゃったんだ。
「……なんなのこれ」
「目が覚めたら何もかも綺麗に忘れています。ここのこともここでの出来事も」
「待ってよ、そんなのやだよ、何勝手に決めてんの!」
「大丈夫です。こうやって話していることも全て忘れています」
「アンジュラも私のこと忘れちゃうの?」
「私ですか? まさか。私は覚えていますよ」
「そんなのズルいよ」
慌てて立って、アンジュラの方へ歩こうにも体が重すぎて立ったまま動くことすらできない。
「ほらね、体が重いからですよ」くすくすと笑う。
待って待って! まだ言いたいことたくさんあるし! 話したいことだっていっぱいある!
更に霞がかってはっきりしなくなってきたアンジュラの顔、でも、クスクス笑うその顔だけは最後まで残って、
ぐにゃりと視界が揺れて、かろうじて目に映っていたアンジュラの顔もぼやけてきて、濃く白く霞んだ視界に、耳の奥がきんきん鳴って痛い。
両手で耳を塞ぎ瞼を閉じた。