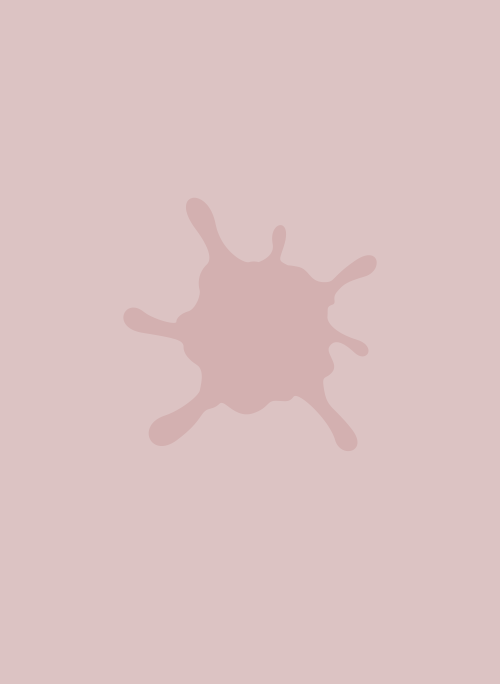「この管に繋がれているから私はまだ生きていられるの。でもそれも長くないみたい。私が自分の体に戻るためには私が私であって、私に成りすましている人が自分の本来行くべきところに行く決心をしてくれないとならないの」
「でも私は……あのサークルにいたし」
「いた? 本当にいたの? それなら仲間の名前教えてもらえるかな。そうしたら私も信じられる。私に成りすましているのがあなたじゃないって分かるよ」
「それは……今はまだ思い出せない」
「緑さん、お願い」
「私は……サークルにいた」
ここまでかたくなに拒絶するくらいにアンジュラサイドは壮絶なんだ。
ここまで拒まれると、本当はルーインサイドにいちゃいけない人間がいたのにこの先のことを見せたルーインに矛先を向けたくなる。
「おまえの家にでも行けば分かるんじゃないか? そんでそこで答えが出んだろ」
ルーインは天井付近でふわふわ揺れながら間延びした声で言う。
それには何も答えない綠さんはいまだベッドに横たわる意識の無い私をじっと見ていた。
「じゃぁさ綠さん、私と一緒に行ってみない? 本当に綠さんがもうこっち側の住人になっているってことを確かめに行ってみよう」
それで確実に死んだということが分かったら、自分のしでかした罪を認め、自分のいるべき場所に行ってくれると願いたい。
「……あなたと一緒にですか」
「女同士、ここにいる二人の変な男は置き去りにして」
明るく、努めて明るく提案した。
しばらく考えてからこくりと頷く綠さんを見て心の中でガッツポーズをする。
変な男とは何事かと唸る二人を軽くいなし、自分の家の場所は分かるのかと聞くとはっきり覚えていると力強く言った。
やっぱ綠さんは記憶がちゃんとある。徐々に無くなっていくのは私だけだ。
これがどういうことなのか、何か落とし穴があるような気がしてならないけど、ひとまずここは綠さんを説得することが最優先だ。