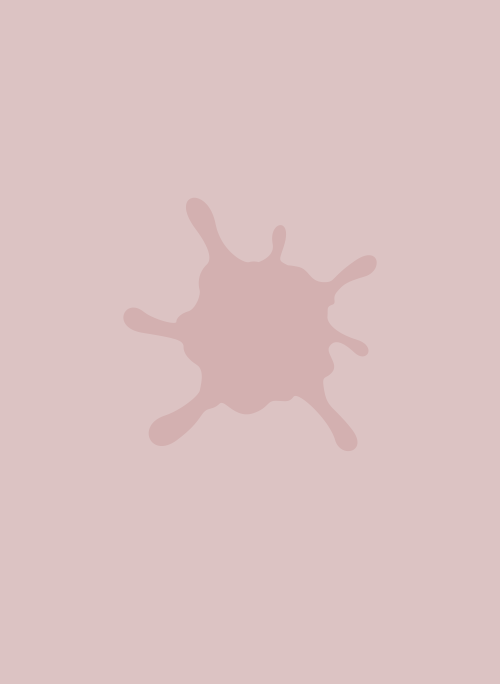「シェーンを幸せにできるのは、私しかいないと思いますが」
「お前にそれを言う資格はねーだろ」
話を遮り祐哉は席を立つ。
「それはどうでしょうか。シェーンはかならず私の元に返ってくると思いますし、
ご両親もそれを望んでいます。勿論私も・・・」
「無理だ。俺がいる以上お前に勝ち目はねーよ。
俺には自信があるからな。二度とあいつの前に現れるな」
睨むように目を捉え、脳の奥に刻み込むように言う。
「あなたにシェーンが幸せにできるというんですか?
彼女の育ってきた環境を知らないあなたに?」
声が強くなった。
「・・・環境なんてどうにでも変えられるんだよ。強い意志さえあればな。それがあいつにはあったから、わざわざ住んだこともない日本にまで来たんだろうが。
全く知らねー国で自分の力で生きて行こうと思ったんだろうがよ。
それを分かってやれねーお前には、何も語る権利はねーんだよ」
「わたしは・・・」「無理だ」
「桃華には、俺が似合う。そもそもなんだよシェーンて。あいつは日本人だ。
それに、俺じゃなきゃあいつはダメだ。お前じゃない。
お前は桃華のことなんてこれっぽっちも考えてない。考えてるのは自分の出世と周りの目、それから自分のステータスだろうが?
あいつはそんなのこれっぽっちも望んじゃいねーよ。
分かったらとっとと国にでも帰んな」
ぴしゃりと言い切り、話を切った。
マークは何も言えず、そこに座ったまま祐哉が出て行くのを、
感情のない目で追うことしか出来なかった。
何も言えないマークは、ただただ祐哉の圧倒的な強さと自信に何を返していいのか分からなかった。