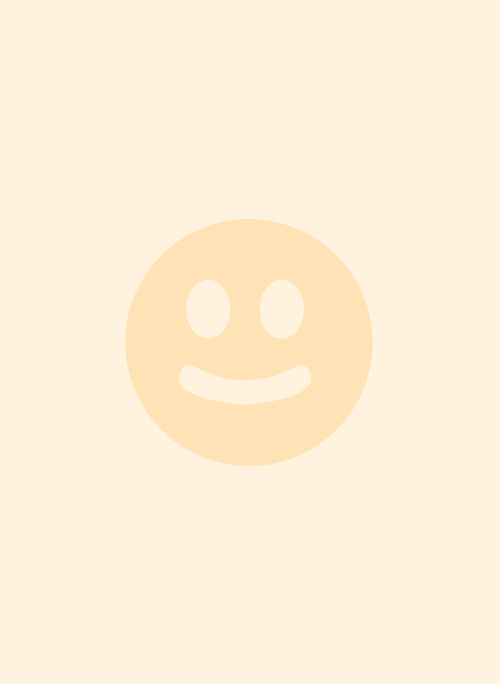あいつは気に入らねえ。
水上唯斗は何度となくそう思うのだった。
何が気に入らないかと問われると、それがなかなか答えに困る。
まずどれから悪いところを言ったらよいのかと―――順序に迷うほど欠点が多い。
ではそれは誰か―――この唯斗のご近所であり、
外法師の破落戸一族の末裔、鬼門雅晴である。
見た目もスタイルも悪い、口も悪い、頭も悪い、性格も悪い。
それなのにどこか義理堅いあの図体だけが大きいあの女を、女子は気に入っているらしい。
悪い噂を聞かない。
しかし、この水上唯斗は大嫌いである。
唯斗は、今時女子の理想となりつつある、いわゆる『王子様系男子』の模範らしからぬ容姿であった。
麻色の長めの髪の毛に、小さな顔は抜けるように白く、身長もそれなりにあり、目も大きい。
もちろん、その甘いマスクは女子生徒に人気がある。
その上、この男は表面上は女に優しい。
だから、彼に惚れぬ女は、彼が通う学校にはまずいない。
―――というのは、彼の盲点であった。
あの鬼門雅晴たる外法師めだけが、惚れ落ちなかった。
「―――あのさ、俺と組まねえ?」
肩肘を壁に突き、鬼門法師を追い込むように唯斗が問うた件の日は、曇天だった。
「どういうことだよ」
「俺の家も、お前と似たような家系なんだよな」
「あ、そ」
「これからは鬼門家と水上家で仲良くしようぜ」
「それで、こちにメリットはあるのかよ」
鬼門法師は金銭の上でのメリットのことを言うたらしい。
やはり下郎である。
平安朝でも、法師陰陽師は貴族に金をもらえば誰であろうと呪殺できたと聞く。
まさにその鏡ではないか。
「……メリットじゃないけどさあ、やっぱり、女を危険な仕事場に行かせて、
怪我させるわけにいかねえだろ」
唯斗の頭の中で、シナリオと台詞が構築される。
こうすれば女は落ちる、こう言えば女は惚れる、経験上で得たデータが唯斗の行動を作り上げる。
つらい目に遭い続けてきた女というのは、必ず手を差し伸べた人間に縋り付く、もしくはその動きを見せる。
この鬼門法師も、てっきり、そんな類のものであると確信していた。
「二人で組めば、俺がお前を守ってやれる。
だから、俺と―――」
手を組もうぜ。
そう言い募ることはかなわず。
死んだ目で鬼門法師は小指を鼻の穴に突っ込み、ぺっ、と地に唾を吐きかけたのだった。
「あほらし、なめてんのかよ。
おめえと組んで収入が減ったら、こっちゃあ食ってけねえんだぜ」
一昨日きやがれい、と―――。
江戸っ子の言葉を汚くもじった言葉で吐き捨て、鬼門法師はことごとく、
唯斗の女遊びの記録を打ち破ったのだった。