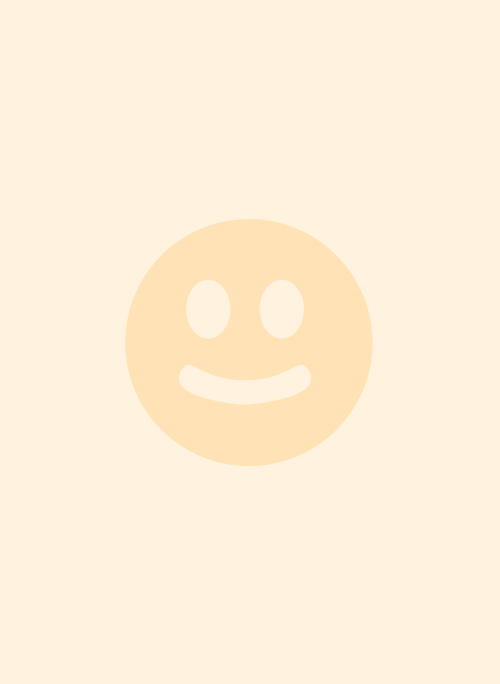陰陽師、というのが平安の都にて栄えていた。
陰陽寮は今も江戸に残っているが、人外なるものを相手にすることはほとんどなくなり、
平安の世にてはびこったとされる『民間陰陽師』の末裔である七衛門などなどの者たちが、
彼のように人の世にありし怪異を解決し、暗躍している。
彼も―-式神の蓋翁もまた、人の怪異を暴くスペシャリストでもある。
二日ぶりの客に、七衛門は面倒くささが半ば入り混じった、歓喜の声を上げるのだった。
「こりゃあたまげた。月にこんなに客が来たのは初めてでい」
そう、この店は基本的に繁盛していない。
なにせ、月に七人が精一杯である。
だから本当に稼ぎに困ったとき、七衛門は表向きの浪人として口入れ屋に足を運ぶ。
これで存外、七衛門も剣術の心得はある。
それを活かして妖かしを退けることも珍しくはない。
この男の職を抽象的に言うならば、「方術使いの妖かし斬り師」となる。
店の前にいたのは、あたかも男のように股引を穿いて着物を着、
頭に鉢巻きをまいた七衛門と同い年ほどの少女だった。
「ああ、あんたがここの主かえ」
まだ幼げな声だったが、喋り方はどこか大人びている。
ついでに言うなら、男らしさも兼ね揃えている。
「おうよ」
「じゃあ妖かしを祓ってくれるってのも、あんたかよ」
「おうよ」
《七衛門よ、そなたは『おうよ』しか言えぬのか》
朧蓋翁が口をはさむや、うるせえやい、と七衛門は小声で言うのだった。
そして心のうちで、
――久々に本業で金が入るんでえ、蓋翁よ、おめえ、ちょいと黙っててくれや。
その心の声を聴くや否や、朧蓋翁が渋い顔をする。
式神なる使い魔の類は、主の呪力によって生きていると言える。
それゆえか、主のの思うことを察するのも彼らは得意であるのだ。
《そなたのお、金のことしか頭にないのかよ》
――なあに言ってんでい。人間がどうして働くかって?決まってんだろうがい。
喰うため生きるため、養うため飾るため、遊ぶため貯めるためだってんでい。
《平気で欲深いことを言うな、そなたは金の亡者か。
前世も来世も金に飢えて生きてきたのか》
「はっはっはっはっ」
高らかに笑い出した七衛門。
もちろんどうして七衛門が笑うのか理由もその過程も知らぬ少女は、
「なに笑ってんですかい」
と、目を開閉するばかりであった。