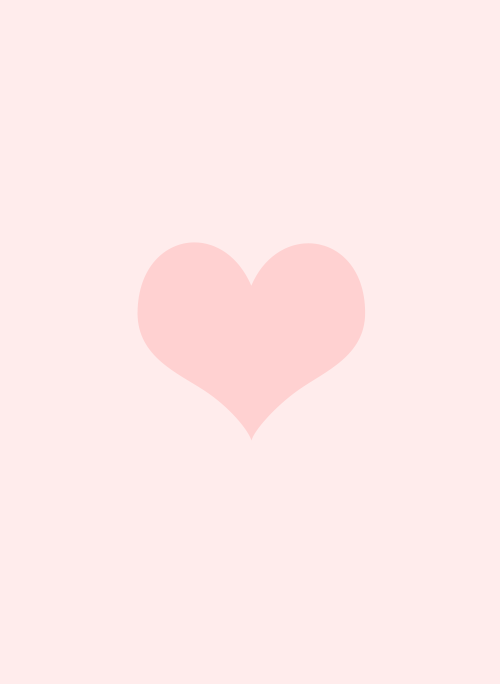恥ずかしいのと、達成感。
焦燥感と、罪悪感。
でも、自転車がかき分けていく風が、ごまかすように、その熱を、気持ちを流していく。
二見のバス停まで行ってくれると嬉しい、と、宝田は言った。
そこから家はすぐなのだと。
俺は一度返事をしただけで、宝田もそれきり、黙っていた。
せっかくなのに、何を話せばいいのかわからなかった。
宝田に握られた肩の下で、カラカラと、車輪が回る音だけが響く。
キラキラしていた。
黒い屋根や、道端の草や、焦げたみたいなアスファルトさえも。
俺たちが進む道は、雨粒をのせたように、キラキラしていて。
車が数台、俺たちを追い越していく。
本当はバスを待ってた方が、早く着いたんじゃないか、とか。クラスのほとんど話さない男子からいきなり乗れとか、もしかしたら、迷惑だったんじゃないか、今も困ってるんじゃないか、とか。
マイナスの気持ちが頭を叩くけれど、それよりも俺は。
ドキドキして、ドキドキしてもう、漕ぐだけで、姿勢を真っ直ぐ正して漕ぐだけで、それだけで、精一杯で。
一人の時よりも重いペダルと、一人の時よりも流行る気持ち。
一人の時には気になるはずの暑さ。一人じゃないから、意識的に避ける段差。
喉はカラカラで、こうしている間にも、どんどん水分は逃げていく。