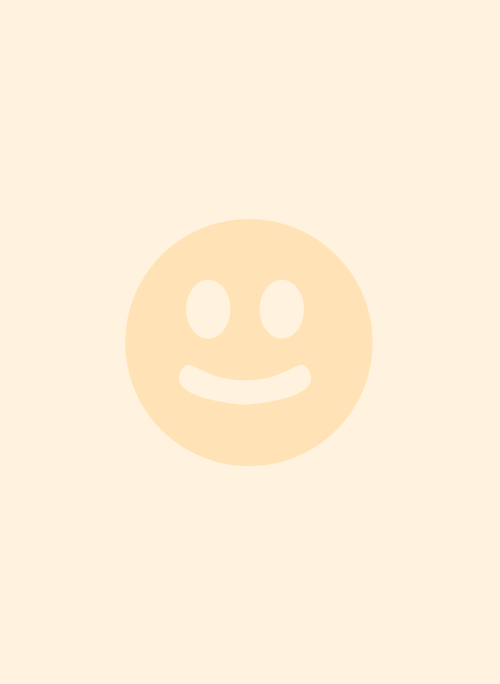「えっ」
「えっ」
清明と蓬丸は退出した折に件の姫に出会い、同時に声を上げた。
「遠子様、遠子様でございますよ、清明様」
「そんなにおかしいの?私が歩いていたら」
「いいえ、いずこかのただの弱小な姫ならば会いたくありませんでしたが、
遠子様ならお会いできて嬉しゅうございます」
蓬丸は馬鹿正直である。
時は酉の刻ばかり、退出して清明たちが家に帰るべく道祖大路に踏み入ったところ、
実に簡素な格好をした遠子が、牛車にも乗らずに髪を結って草履を履き、
道祖の道の端に寄りかかっているものだから、それはもう驚いてしまう。
「何用でございますか」
蓬丸の後ろからひょっこりと出てきた清明が、驚愕を振り払って問うた。
「また、物の怪でございますか」
「いいえ、違うわ」
遠子は頭を一つ振った。
「――死人が、都に蘇ってきてるって、本当なの?」
遠子の耳にもすでに届いていたようだ。
そして怪異と考えた遠子は清明なら何か知っているのではないかと思い、ここを訪ねてきたのである。
なぜ清明なのか。
彼が一番身近な陰陽師であり、一番話しやすい相手だったからだ。
「はい」
清明はうなづいた。
「何か、ありましたか」
冷静に問う清明に、遠子は何かを訴えんばかりの瞳を向けた。
「おかしいの」
「おかしい、と、申しますと」
「死人が蘇ってくるのでしょう、だったら」
遠子の言い方に以前のような力強さがない。
どうしたものか、と不思議に思って視線を合わせた清明だが、遠子はいそいそと視線を下にやった。
「清明様、あまり見つめてはなりませんよ」
そこで、蓬丸が言った。
「清明様が見つめると、その眼を長く見つめていられませぬ。
ついつい身じろいでしまいます」
言っている意味がよくわからなかったが、とにかく清明はかがめた足を伸ばした。