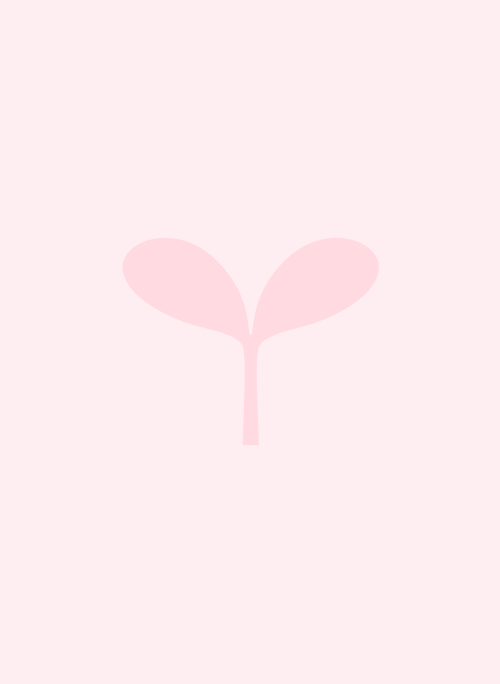ふいにおりた沈黙の中で、霎介さんはゆっくりとした足取りで私の後ろにまわって来ると、私の髪をすくように優しく撫でた。
「あれが、あの日君が泣いていた理由かい?」
躊躇いがちに頷いた私の様子を見て、何を思ったのか、ゆっくりと後ろから私の肩を抱きしめた。
「っ!?」
首筋に、霎介さんの柔らかい髪の感触と、微かな熱を帯びた吐息。
身体の芯が爆発したように熱くなる。
「殴り飛ばしてやってもよかったんだが…」
「んっ……!」
首元で話される度に、身体が反応する。
「僕の思い違いでなければ、あの日以降から君が変わった気がしてね」
「ちょ…っ……そ…介…さ……っ」
私の反応を楽しむように、彼の指先が懐を這う。
「そう思ったらなんだか釈然としないが、そんなに熱くなれなかった」
いつもの霎介さんらしくない…
いや、
きっとこれも霎介さんなんだ。
「次にもしまたそんなことがあったら、手近な物で思いっきり殴ってやると良い」
「んぁっ……はぁ…い…っ」
出した事もないような甘い声音に驚いている自分がいる。
はしたない事とわかっていても、拒めない自分がいる。
私はこの人を好きになったんだ。
と、
実感した。
「あれが、あの日君が泣いていた理由かい?」
躊躇いがちに頷いた私の様子を見て、何を思ったのか、ゆっくりと後ろから私の肩を抱きしめた。
「っ!?」
首筋に、霎介さんの柔らかい髪の感触と、微かな熱を帯びた吐息。
身体の芯が爆発したように熱くなる。
「殴り飛ばしてやってもよかったんだが…」
「んっ……!」
首元で話される度に、身体が反応する。
「僕の思い違いでなければ、あの日以降から君が変わった気がしてね」
「ちょ…っ……そ…介…さ……っ」
私の反応を楽しむように、彼の指先が懐を這う。
「そう思ったらなんだか釈然としないが、そんなに熱くなれなかった」
いつもの霎介さんらしくない…
いや、
きっとこれも霎介さんなんだ。
「次にもしまたそんなことがあったら、手近な物で思いっきり殴ってやると良い」
「んぁっ……はぁ…い…っ」
出した事もないような甘い声音に驚いている自分がいる。
はしたない事とわかっていても、拒めない自分がいる。
私はこの人を好きになったんだ。
と、
実感した。