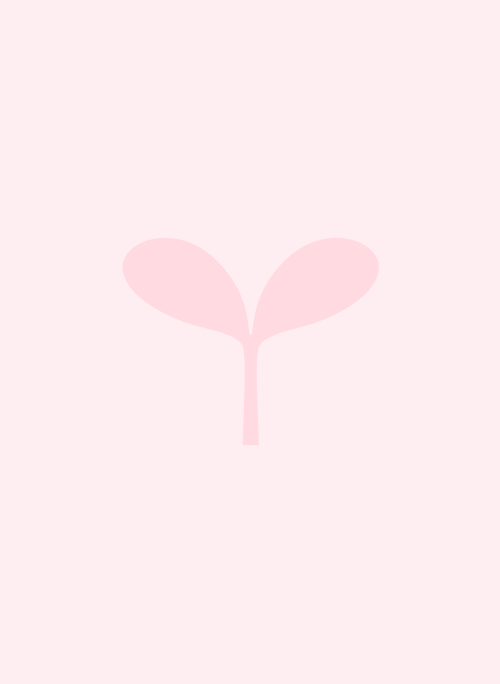カラカラと笑ったまま清太郎さんは付け加えるように言った。
「まぁ修業中の習作食ってもらって、こっちも腕を磨くのですから持ちつ持たれつです」
清太郎さんはまるで太陽のような笑顔を浮かべる人だった。
人懐こく、ころころと表情を変える。
普段あまり笑わない霎介さんも時には笑みを浮かべ、私もお腹を抱えて笑ってしまう事もあった。
「とても働きに出る家の人とは思えないなぁ」
家事をこなす私の後ろで清太郎さんがぼやいた。
霎介さんが仕事に戻り、暇になった清太郎さんは家事に戻った私をつかまえて雑談にふけっていたのだった。
「ただの口減らしですよ」
「うぅぬ」
何がひっかかっているのか彼はただ犬みたいに唸る。
「学ぶ場所に恵まれなかったにしちゃあ話術がある」
「なけなしなものですよ」
「そんなこたぁない」
本当ですよと笑みを浮かべる彼に私は計らずも鼓動が速くなるのを感じた。
「あまりにやにやするな太郎。
馬鹿だと言うのがばれるぞ」
「お?」
気が付くと、霎介さんが浴衣の袖に手を入れながら立っていた。
「まぁ修業中の習作食ってもらって、こっちも腕を磨くのですから持ちつ持たれつです」
清太郎さんはまるで太陽のような笑顔を浮かべる人だった。
人懐こく、ころころと表情を変える。
普段あまり笑わない霎介さんも時には笑みを浮かべ、私もお腹を抱えて笑ってしまう事もあった。
「とても働きに出る家の人とは思えないなぁ」
家事をこなす私の後ろで清太郎さんがぼやいた。
霎介さんが仕事に戻り、暇になった清太郎さんは家事に戻った私をつかまえて雑談にふけっていたのだった。
「ただの口減らしですよ」
「うぅぬ」
何がひっかかっているのか彼はただ犬みたいに唸る。
「学ぶ場所に恵まれなかったにしちゃあ話術がある」
「なけなしなものですよ」
「そんなこたぁない」
本当ですよと笑みを浮かべる彼に私は計らずも鼓動が速くなるのを感じた。
「あまりにやにやするな太郎。
馬鹿だと言うのがばれるぞ」
「お?」
気が付くと、霎介さんが浴衣の袖に手を入れながら立っていた。