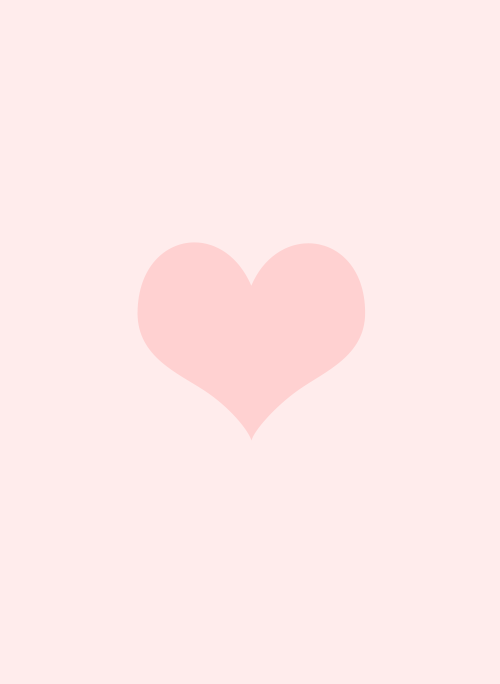「こうなるだろうとは思ったぜ」
来てよかった、と彰真は非難の意を込めた視線をよこす。
しかし、とあたしにも反論させて欲しい。確かに忘れていたのは悪いとは思う。
「でも、差出人不明の手紙を真に受ける人はいると思う?」
「う、」
今度は彰真が罰が悪そうに苦虫を数匹潰したような顔になる。
「悪戯にしか思えない」
たまたま朔夜がいってくれたからあぁ、彰真か、てなったけれど、朔夜がいなかったらあの手紙は即座にゴミ箱行き、それにあたしの頭の中には片隅にすら残らなかっただろう。
「そりゃ……」
「お互い様ならまだしも、あたしが怒られなきゃいけない理由はない」
「…………ごめんなさい」
あっさりと謝ってきた彰真に、あたしは拍子抜けだ。