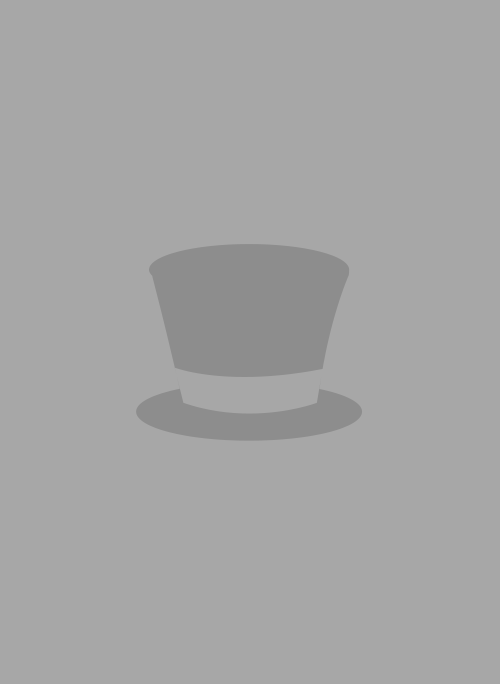「その時…自分で自分が嫌になった…何時もは、抱き合って、こう、何て言うか、あったかいものが互いに通じ合う気分になれるのに……よりによって、あの日だったんです…最後に見たジュリの顔が、何とも言えない、こう、遠くへ行っちまったような、そんな表情だった…怒った顔でも、笑った顔でもない…すごい冷たい感じだった…ゴメンって留守電入れたけど…入れたんだけど……」
久美子の指が、竜治の唇に触れた。
もう話さないでとでも言うかのような仕草だった。
竜治を抱き寄せる久美子の手に、力が加わった。
竜治は、久美子の胸の中に顔を埋めた。
なだらかな乳房に包まれ、
母親に抱かれるって、こんな感じなんだろうか……
と感じた。
訳も無く涙が流れて来た。
頬を流れ落ちた涙が、久美子の胸を濡らした。
竜治のうなじに、久美子の涙が落ちた。
「奴の顔…怒ってるとか、悲しいとか、全然そんなんじゃなくて……」
「もう、話さないで…」
「初めて見る顔だった…それが…」
「竜治さん…」
「それが最後に見た顔だなんて……」
「そうやって、何時迄も自分を責めないで…」
久美子の顔が、竜治の左頬に近付いた。
唇が触れた。
頬をつたわる涙を拭うようにキスをした。
顔を上げた竜治は、その唇に自分の唇を重ねた。
竜治は、すぐに身体を離し、無言で頭を下げ、店を出て行った。
一人ぽつんとカウンターに残された久美子は、空になったグラスにバーボンを注いだ。
竜治の唇の感触を消すかのように、一息で飲み干した。
流し込んだバーボンは、唇と舌を軽く痺れさせた。
久美子は、自分の身体を通り過ぎて行った男達の顔を思い浮かべていた。
恋をすれば、傷付くのは決まって女の方だと判っていながら、新しい恋を女は求める……。
シンデレラストーリーのように、いつかは必ず白馬の王子が現れる……そんな事は、少しも信じてなんかいない。
初めからお伽話だと判っている。
それでも夢だけは見続けていたい。
現実が余りにも悲し過ぎるかなのか……
久美子の中で、竜治の存在が少しずつ大きくなっているのが、自分でも判った。
しかし、それが、決して幸福そうな未来を想像させてくれない事も判っていた。
久美子の指が、竜治の唇に触れた。
もう話さないでとでも言うかのような仕草だった。
竜治を抱き寄せる久美子の手に、力が加わった。
竜治は、久美子の胸の中に顔を埋めた。
なだらかな乳房に包まれ、
母親に抱かれるって、こんな感じなんだろうか……
と感じた。
訳も無く涙が流れて来た。
頬を流れ落ちた涙が、久美子の胸を濡らした。
竜治のうなじに、久美子の涙が落ちた。
「奴の顔…怒ってるとか、悲しいとか、全然そんなんじゃなくて……」
「もう、話さないで…」
「初めて見る顔だった…それが…」
「竜治さん…」
「それが最後に見た顔だなんて……」
「そうやって、何時迄も自分を責めないで…」
久美子の顔が、竜治の左頬に近付いた。
唇が触れた。
頬をつたわる涙を拭うようにキスをした。
顔を上げた竜治は、その唇に自分の唇を重ねた。
竜治は、すぐに身体を離し、無言で頭を下げ、店を出て行った。
一人ぽつんとカウンターに残された久美子は、空になったグラスにバーボンを注いだ。
竜治の唇の感触を消すかのように、一息で飲み干した。
流し込んだバーボンは、唇と舌を軽く痺れさせた。
久美子は、自分の身体を通り過ぎて行った男達の顔を思い浮かべていた。
恋をすれば、傷付くのは決まって女の方だと判っていながら、新しい恋を女は求める……。
シンデレラストーリーのように、いつかは必ず白馬の王子が現れる……そんな事は、少しも信じてなんかいない。
初めからお伽話だと判っている。
それでも夢だけは見続けていたい。
現実が余りにも悲し過ぎるかなのか……
久美子の中で、竜治の存在が少しずつ大きくなっているのが、自分でも判った。
しかし、それが、決して幸福そうな未来を想像させてくれない事も判っていた。