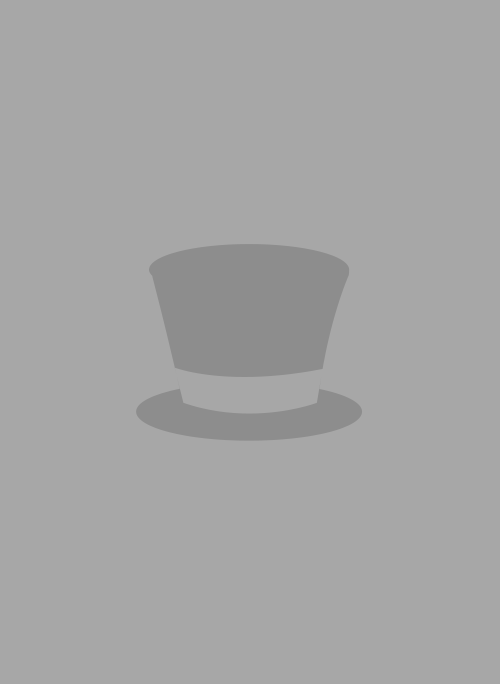心無しか久美子の身体が以前より細くなっている。
「ええ……」
「そう……お酒、飲めそうかい?」
「うん…大丈夫だと思う……」
「じゃあ、今夜は私が奢って上げる…」
久美子の前にワイングラスが置かれた。
「これ、昔の男が買ってくれたワインなんだけど、ずっと開けないでいたの…」
二つのワイングラスに、濃い赤みの液体が注がれた。
「美味しい…」
「ずっと開けないで置こうかなって思ってたんだけど…うん…まあまあだね…」
「いいの?大切にしてたんじゃない?」
「ええ、そうよ…墓場迄持って行こうかと思ってた位……」
笑いながら軽口を言うママにつられて、久美子も笑った。
「ラベル、見てご覧…1957年…それ、私の生まれた年なの…わざわざこんな物を見つけ出して来てさ…カッコ付けたつもりだったんだろうね…」
「ママがそんな年だったなんて知らなかった。」
「教えたの、久美ちゃんが初めて…こいつを開ける事は無いだろうなって思ってたんだけど……」
「いいの?」
「いいのって言われても、もう開けちゃったからね…私と、久美ちゃん…似た者同士が飲んじまうのが一番いいのかも……二年になるかい?」
「え?いえ、この間一周忌を…」
「じゃなくて、一緒にうちに来てくれたのが…」
「…うん」
「最初見た時、ちょっと怖い感じがしたんだけど、笑うと子供みたいな顔してたのが、すごく印象に残ってる……」
「そうだったかな……」
「あら、やだ。あんた自分の男だったのに…」
少し湿り気のある笑いが、二人の間を漂った。
「男ってさぁ、どうしてこう、身勝手なんだろうねぇ……」
「ほんとですね……」
「このワインをプレゼントしてくれた男も、21世紀を迎える時にこれを一緒に飲むんだ、なんてカッコ付けてたくせに……」
「別れちゃったの?」
「………」
ママが泣いていた。
「ごめんなさい、変な事聞いちゃって……」
「いいのよ、気にしないで…久美ちゃんを見てたら、何だか自分の事を思い出しちゃってさ…たまには涙位流さないと、おばさんは干からびちまうからね……その男ね…ヤクザだったの……」
そう言って、ママが微笑んだ。
「ええ……」
「そう……お酒、飲めそうかい?」
「うん…大丈夫だと思う……」
「じゃあ、今夜は私が奢って上げる…」
久美子の前にワイングラスが置かれた。
「これ、昔の男が買ってくれたワインなんだけど、ずっと開けないでいたの…」
二つのワイングラスに、濃い赤みの液体が注がれた。
「美味しい…」
「ずっと開けないで置こうかなって思ってたんだけど…うん…まあまあだね…」
「いいの?大切にしてたんじゃない?」
「ええ、そうよ…墓場迄持って行こうかと思ってた位……」
笑いながら軽口を言うママにつられて、久美子も笑った。
「ラベル、見てご覧…1957年…それ、私の生まれた年なの…わざわざこんな物を見つけ出して来てさ…カッコ付けたつもりだったんだろうね…」
「ママがそんな年だったなんて知らなかった。」
「教えたの、久美ちゃんが初めて…こいつを開ける事は無いだろうなって思ってたんだけど……」
「いいの?」
「いいのって言われても、もう開けちゃったからね…私と、久美ちゃん…似た者同士が飲んじまうのが一番いいのかも……二年になるかい?」
「え?いえ、この間一周忌を…」
「じゃなくて、一緒にうちに来てくれたのが…」
「…うん」
「最初見た時、ちょっと怖い感じがしたんだけど、笑うと子供みたいな顔してたのが、すごく印象に残ってる……」
「そうだったかな……」
「あら、やだ。あんた自分の男だったのに…」
少し湿り気のある笑いが、二人の間を漂った。
「男ってさぁ、どうしてこう、身勝手なんだろうねぇ……」
「ほんとですね……」
「このワインをプレゼントしてくれた男も、21世紀を迎える時にこれを一緒に飲むんだ、なんてカッコ付けてたくせに……」
「別れちゃったの?」
「………」
ママが泣いていた。
「ごめんなさい、変な事聞いちゃって……」
「いいのよ、気にしないで…久美ちゃんを見てたら、何だか自分の事を思い出しちゃってさ…たまには涙位流さないと、おばさんは干からびちまうからね……その男ね…ヤクザだったの……」
そう言って、ママが微笑んだ。