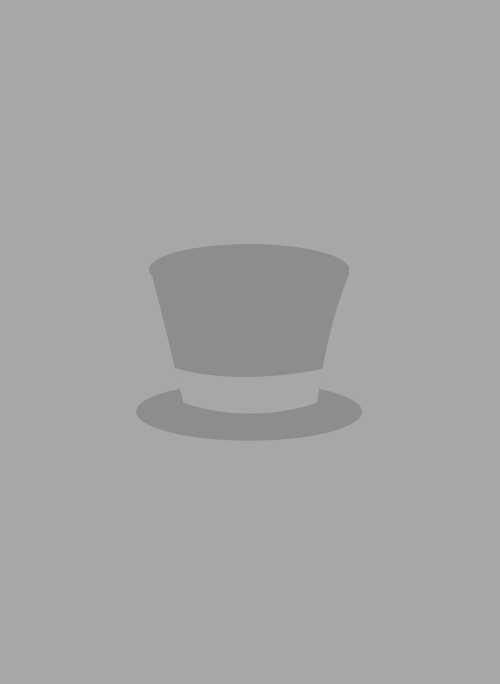「お父さん、どうせアタシの名前使って小説書くんだったら、絶対美人で可愛いキャラにしてよ」
娘の里佳子が自分の部屋の扉を閉めながら、滅多に見せない笑顔でそう言った。本当なら里佳子が使う順番だったろうに、二人とも気を遣ってくれたようだ。
今夜は家族揃って、いったいどういう風の吹き回しなのだろう。心の中で皆に感謝をしながら、私は何と無く小説の続きが書けそうな気になって来た。
「よし、やるか」
柄にもなく、そんな独り言の気合を入れ、下書きをパソコンで打ち始めた。
私は、自分が書いたそれまでのページをもう一度読み返した。
青春というテーマを与えられた今回のケータイ小説大賞。その青春というものを私なりにどう表現すべきかで、書き出しまで随分と悩んだ。
悩んだが、答えなど出なかった。小説の中で、リュウノスケが息子サンジュウゴに言った言葉は、そっくり自分へのメッセージでもあった。
加瀬三十五は、私そのものと言ってもおかしくない。
私の十代は、何かを探しながらも、その実、何も探す努力をしなかった十代であった。
不満だけを口にし、失敗は必ず何かのせいにしていた。特に若さ、というもに対して。
若いのだから、若いうちなんだから。失敗しても、簡単に次があるさと顧みる事をしなかった。努力をしてこそ、初めて
「若いんだから」
という言葉を使う資格があると、この歳になってやっと気付かされた。
娘の里佳子が自分の部屋の扉を閉めながら、滅多に見せない笑顔でそう言った。本当なら里佳子が使う順番だったろうに、二人とも気を遣ってくれたようだ。
今夜は家族揃って、いったいどういう風の吹き回しなのだろう。心の中で皆に感謝をしながら、私は何と無く小説の続きが書けそうな気になって来た。
「よし、やるか」
柄にもなく、そんな独り言の気合を入れ、下書きをパソコンで打ち始めた。
私は、自分が書いたそれまでのページをもう一度読み返した。
青春というテーマを与えられた今回のケータイ小説大賞。その青春というものを私なりにどう表現すべきかで、書き出しまで随分と悩んだ。
悩んだが、答えなど出なかった。小説の中で、リュウノスケが息子サンジュウゴに言った言葉は、そっくり自分へのメッセージでもあった。
加瀬三十五は、私そのものと言ってもおかしくない。
私の十代は、何かを探しながらも、その実、何も探す努力をしなかった十代であった。
不満だけを口にし、失敗は必ず何かのせいにしていた。特に若さ、というもに対して。
若いのだから、若いうちなんだから。失敗しても、簡単に次があるさと顧みる事をしなかった。努力をしてこそ、初めて
「若いんだから」
という言葉を使う資格があると、この歳になってやっと気付かされた。