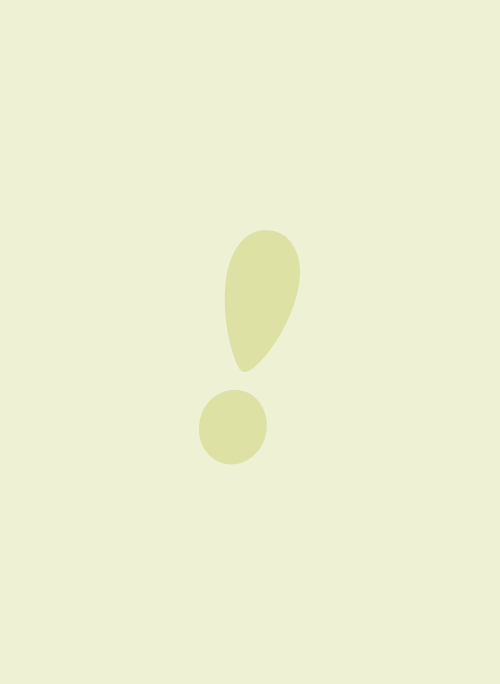錆び付いた扉をシイが開いて、私がそこを先に出た。
あぁもう、こんな扱い不慣れだ。
つくづくそう感じるが、嫌な気はしない。むしろくすぐったい。
気が付いたら離れていた手が寂しいなんて。
私は断じて思ってない。
読まれたらたまんない。勢いで死ねる。
──隣に立ったシイを横目に見た。
その気配をすぐに察したのか、ん?と彼は私を見た。
目が合った。
すると逸らせなくて、適当に口を開く。
「あ…じゃあそろそろ、帰ります」
取り敢えずなんの礼かと聞かれたら答えに悩むが、頭を下げようとした。
「送る」
その低い声に、下げようとした頭を上げる。
「お前の町の駅まででも、送る」
聞き直す暇はなかった。
ほら行くぞ、と彼がすぐに背中を見せた。
彼が向きを変えた時、また花のような甘い匂いがした。
「あ」
私はその背中に、少し足を早めてついていった。