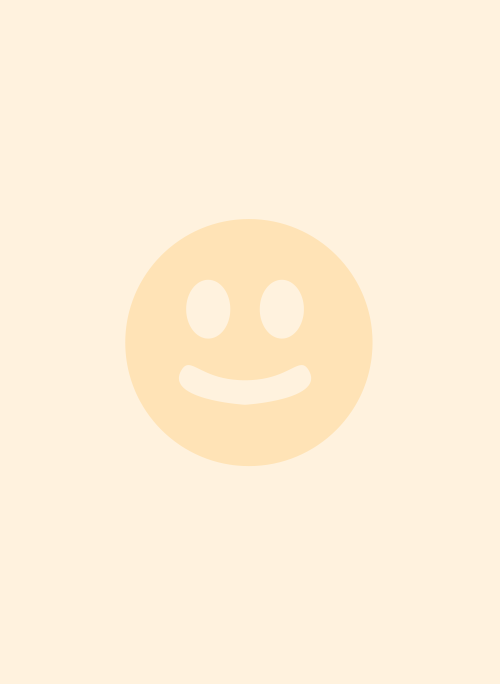「まだ心が幼かった俺には、その行為が恐怖でしかなかった。毎日、毎日。飽きもせず俺を犯しにくる女の人。精神的に、追い詰められていました」
…男の子でも、それは恐い。
傷つくのも分かりきったことだ。
「父の恋人なのに、俺に跨がって気持ち悪いくらい…ねっとりとした声をあげる女の人に、本当に俺は…俺、は…」
「畝高くんっ!!」
ギュッと、僕は彼の両手を握った。
「!!」
彼は、驚いたように目を丸くしていた。
よく見ると、彼の瞳は少し揺らいでいた。
握ったのは、彼が消えてしまいそうだったから。
か細い声で自分の過去を綴る彼に、心底胸が締め付けられたから。
僕がそれを口にしても、ただの同情としか思えないだろう。
けど、この手を握る僕の手は、本物だ。
何よりも…嘘のないぬくもりだと思うから。