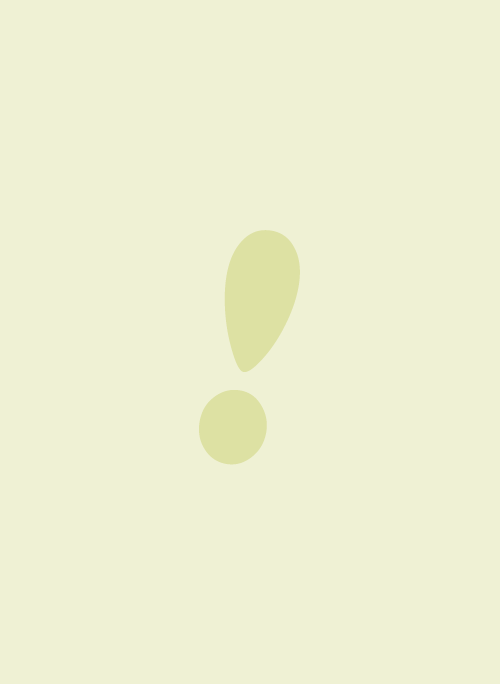あぁ、こんな意味があったのか。
「真珠の…輝き…」
私がそう呟くと、
詠輝さんは頭をかいた。
「僕の娘は確かに、真珠のように綺麗になった――」
そう、小さく呟いて
私は少し照れくさくなった。
だけれど
「アタシは確かに娘だけど、もう娘じゃない。海音珠輝として…確かに父親なら、いる」
そうなんだ。
私はそう言って胸を張る。
視線は真っ直ぐと、
自分を生んで捨てて出会った父親に向ける。
「そうか」
そう微かに微笑んだ詠輝さんは
やはり詠人に似ていた。
その詠人を、私は見た。
「…詠人?」
私はまゆを潜めた。