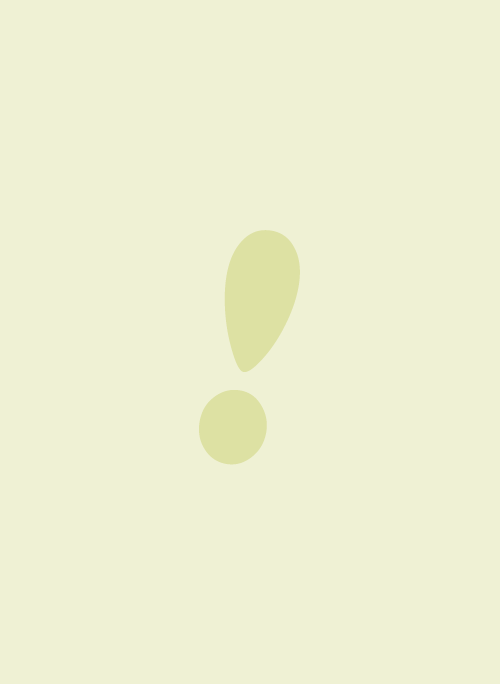私は詠人の服の裾を掴み、
少し前に出る。
「話してくれますか」
私の声は、
自分で思ったよりも
しっかりとしていた。
「さすが姉だね」
悲しそうにか、
それとも嬉しそうにか
詠輝さんは笑った。
皮肉めいた言葉だ。
右目の下にあるほくろが
涙の跡のように見えた。
「良いよ。もちろん」
自分の子どもたちが結ばれてしまったら
話さないわけにはいかない。
詠輝さんは
そう言葉を落とした。
「妻が買い物で良かった。――…僕は女たらしでね」
そこから始まる、
自分たちの父親の話に
私たち子どもは耳を傾けた。