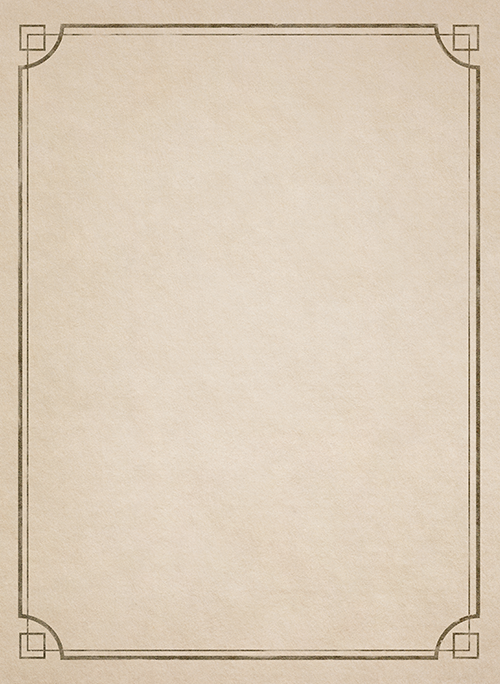放課後の学校って、なんでこんなに居心地悪いんだろ。
昼間あんなにうるさかった教室が、嘘みたいにシーンとしてる。黒板消しクリーナーから漏れたチョークの粉の匂いとか、床ワックスの薬品臭さが、鼻の奥にツンとくる。
窓から差し込む夕日は、青春映画みたいな綺麗なオレンジ色なんかじゃない。もっとドロドロとした、古くなった血みたいな赤色。それが廊下を長く伸びて、まるで「こっちにおいで」って手招きしてるみたいに見える。
私は教室のドアに手をかけた。
立て付けの悪い引き戸は、ちょっと動かしただけでガタガタと大きな音を立てる。その乾いた音が誰もいない廊下に広がって、ビクッと肩が跳ねた。
……情けない。
自分の出す音にいちいちビビってるなんて、我ながらどうかしてる。
鞄の持ち手をギュッと握りしめた。手のひらにじっとりと汗が滲んでるのがわかる。
深呼吸。肺の中の空気を全部入れ替えるつもりで、大きく吸って、吐く。
大丈夫。まだ、平気。
私はそっと廊下へ足を踏み出した。
どこにでもいる普通の女子高生。それが私の表向きの顔。
成績もそこそこ、運動神経も人並み。クラスでは目立たないグループの端っこで、愛想笑いでやり過ごす。そうやって「普通」の皮を被って生きてきた。
でも、その皮の下には、誰にも言えない秘密がある。
私は、見えてしまうのだ。
普通の人には見えないはずの、この世ならざるモノたちが。
昔からずっとそうだった。
でも、親にも先生にも、絶対言わない。言えば「変な子」扱いされて孤立するだけだって、痛いほど学習したから。
だから私は、ひとつの鉄則を自分に課している。
――無視すること。
何が見えても、何が聞こえても、絶対に反応しない。そこに「いない」ものとして扱う。
それが、私がこの世界で平穏に生き延びるための、唯一の防衛策。
誰もいない廊下を、私は早足で歩く。
コツ、コツ、と上履きの底が床を叩く音が、やけに大きく聞こえた。
放課後の学校は、奴らにとって絶好の遊び場だ。人が減ったこの時間は、奴らが我が物顔でウロウロし始める。
だから、一刻も早く家に帰りたい。自分の部屋の布団に潜り込んで、朝が来るまで世界をシャットアウトしたい。
視線を床に落としたまま歩く。壁のシミや床の汚れ、そういう現実的なものだけに意識を集中させる。
うっかり何もない空間を見ちゃダメだ。そこには、たいてい「何か」が立っているから。
渡り廊下へ続く角が見えてきた。
あそこを曲がれば階段がある。そこを駆け下りれば、昇降口まではすぐ。
あと少し。
そう思った矢先だった。
ゾワリ、と背筋が凍りついた。
振り返らなくてもわかる。
私のすぐ「背後」に、とんでもないものが立っている。
呼吸音が聞こえる距離。いや、もっと近い。
ドロドロとした闇の気配。
それが、音もなく私の後ろに張り付き、首筋に冷たい息を吹きかけているような圧迫感。
殺される。
『……』
声なき殺意が、背中から突き刺さる。
見ちゃダメだ。振り返ったら終わる。
私は弾かれたように足を動かした。逃げなきゃ。前へ。角を曲がって、特別教室棟へ。
私は前のめりに駆け出した。
けれど、角に近づくにつれて、こめかみの奥がキリキリ痛み出した。
――進んではいけない。
――そっちにも、「いる」。
本能が警報を鳴らしてる。その角の先には、別の「厄災」が待ち構えてるって。
でも、止まれない。背後からは、空間をきしませるようなミシッ、ミシッという音が迫ってきてる。後ろの得体の知れない化け物に捕まるくらいなら、前の予感を無視して突っ切るしかない。
私は半泣きで角を飛び出し、渡り廊下へと飛び込んだ。
勢いがつきすぎて止まれない。上履きがキュッと音を立てて滑り、転びそうになりながら顔を上げた、その目の前。
人影があった。
廊下の中程、夕日を背にして、セーラー服を着た女子生徒が立っている。
(あ……よかった、人がいる!)
先生でもない、ただの生徒。
本能が鳴らしてた警報は、気のせいだったのかもしれない。この異様な空間で「生きた人間」に会えた安堵感は、何よりも大きかった。
私はすがるような思いで、その背中に向かって手を伸ばす。
「ねえ、逃げて! 後ろから変なのが……!」
私の声に反応して、彼女がゆっくりと振り返る。
長い黒髪がサラリと揺れる。
その顔が見えそうになった瞬間、頭の中に、知らない映像が勝手に流れ込んできた。
――ずっと、待ってたのに。
――約束したのに。誰も来ない。夕焼けが消える。暗くなる。怖い。寂しい。許さない。
強烈な「待ちぼうけ」の記憶。
誰かを待ってたはずの純粋な思いが、腐りきって、ドロドロの怨念に変わっちゃってる。
この子は、人間じゃない。
ツン、と鼻をつんざくような悪臭がした。
生ゴミのような、あるいは夏の炎天下で放置された肉みたいな、強烈な腐敗臭。
彼女が、ニッコリと笑う。
いや、そう見えたのは一瞬だった。
メキョッ。
湿った音がして、彼女の首が真横に傾いだ。
九十度、百八十度……さらに回転して、ありえない角度までねじ切れる。
笑顔のままの口元から、ドス黒い液体がダラダラと溢れ出した。
「――っ!?」
悲鳴すら出ない。
彼女の整っていた顔の皮膚が、熱した蝋みたいにドロドロと崩れ落ちていく。
剥がれ落ちた肉の下から覗いたのは、充血して真っ赤に染まった巨大な眼球だった。
そうだ、どうして気が付かなかったんだろう。私の学校の制服はブレザーだ。
目の前にいる「あれ」が、この学校の生徒なわけない。
だったら「あれ」が、まともな人間であるはずなんかない。
「ゆ……る……さ……」
崩れた喉の奥から、ヘドロが詰まったような濁った声が漏れる。
顎の関節が外れ、口が裂けるように大きく開かれた。暗い口の奥には、歯の代わりに無数の白い蛆が蠢いている。
ボロボロと口から蛆を吐き出しながら、それ――セーラー服の化け物が、私に向かって腕を伸ばしてきた。
後ろには黒い影。前には腐った女。
完全に挟まれた。逃げ場なんてどこにもない。
腐敗した指先が、私の顔に触れそうになる。
私は反射的に目を硬く閉じて、頭を抱えてうずくまった。
(お母さん、ごめん!)
走馬灯なんて綺麗なものは見えない。ただ、どうでもいい後悔だけが頭をよぎる。
こんなことになるなら、昨日の夕飯のハンバーグ、もっと味わって食べればよかった。苦手な数学の宿題なんて、サボればよかった。
鋭い爪が、私の顔に届く寸前。
ドタドタドタッ!!
不釣り合いな音が聞こえた。
幽霊が立てるような音じゃない。誰かが廊下を全力疾走してくる、荒々しい足音だ。
え?
ザシュッ!!
空間そのものを叩き割るような、鋭い音がした。
同時に、ものすごい暴風が吹き荒れる。
恐る恐る目を開けた私の視界に、翻る黒い布地が映り込んだ。
「はぁッ、はぁッ……!」
目の前に、誰かが立っていた。
私を背中で庇うようにして、立ちふさがっている。
肩で息をしている。ものすごく走ってきたみたいに、呼吸が荒い。
古風な学ランを着た、背の高い少年だった。
彼は、飛んできたセーラー服の霊を、なんと空中で止めていた。
魔法とかバリアとか、そんな綺麗なものじゃない。
片手で、霊の顔面を鷲掴みにしている。
細くしなやかな指が、腐った肉に容赦なくめり込んでいるのだ。
グチャリ、と嫌な音がする。
霊の動きが、空中でピタリと静止している。
何か叫ぼうとして口をパクパクさせているけれど、声になっていない。
メキ、メキメキ……と、頭蓋骨にヒビが入る乾いた音が聞こえてくる。
少年は、私の方を一度も振り返らなかった。
ただ、邪魔なゴミでもポイ捨てするかのように、無造作に腕を振るった。
ブンッ! と空気が唸りを上げ、霊の体が吹き飛ぶ。
ゴムボールみたいに軽々と投げ飛ばされた霊は、コンクリートの壁に激突した。
ドゴォォォン!!
校舎全体が揺れるような衝撃。
壁に蜘蛛の巣状のヒビが入って、白い粉塵が舞い上がる。
霊は壁にめり込んだまま、ぐったりと垂れ下がっている。
……強くない?
ていうか、何この人。どこから走ってきたの?
私はポカーンと口を開けて、その光景を見つめることしかできない。
これで終わり?
いや、まだだ。
壁にめり込んだ霊から、黒い煙のようなものが立ち昇っている。まだ消えていない。再生しようとしているんだ。
少年は、乱れた呼吸を整えながら、ゆっくりと右手をかざした。
その手のひらに、ボウッ、と蒼白い炎が灯った。
ズンッ。
その瞬間、私の体が急に重くなった。
まるで献血をした直後みたいに、スーッと血の気が引いていく。
え、なに? 目眩がする。
立っているのがやっとの状態で、私は彼の手元を見つめた。
ライターもマッチもないのに、虚空から生まれた炎。
それは、見ているだけで魂が凍りつきそうなほど、美しくて冷たい色をしていた。
『……滅せよ』
初めて、彼が声を発した。
低くて、お腹の底から聞こえるようないい声。
彼が手を握り込むと同時に、霊の体を蒼い炎が包み込んだ。
ギャァァァァァ!
耳を塞ぎたくなるような、耳を貫く断末魔。
炎は一瞬で燃え上がって、霊の姿を跡形もなく焼き尽くしていく。
ほんの数秒の出来事だった。
あとには、ただ煤けた壁のシミだけが残っていた。
シーン……と、再び静寂が戻ってくる。
あの強烈な腐敗臭も、嘘みたいに消え去っている。残っているのは、オゾン臭のような、雨上がりのアスファルトのような、不思議な匂いだけ。
私は、腰が抜けてその場にへたり込んでいた。
恐怖と、さっきの謎の脱力感で、指先一つ動かせない。
助かった……の?
あの蛆虫女に殺される寸前で、この人が助けてくれたってこと?
でも、なんで?
さっきまでいなかったのに、わざわざ走ってきてまで?
少年が、ゆっくりと振り返る。
ヒッ、と喉が鳴る。
逆光ではなくなったから、その顔がはっきりと見えた。
透き通るような白い肌。やっぱり、めちゃくちゃ美形だ。テレビに出ているアイドルや俳優ですら霞んで見えるほどの整い方。
でも、その顔は汗で少し濡れていて、前髪も乱れている。
さっきの鬼のような形相は消えていて、今は……なんだろう。
困ったような、ひどく悲しそうな顔をしている。
金色の瞳が、静かに私を見下ろす。
そこには、殺意も敵意もない。あるのは、深い安堵と、切なさのような感情だった。
彼は、私に向かって一歩踏み出した。
私はビクッと体をこわばらせる。
だって怖いものは怖い。あんな圧倒的な暴力を見せられた後だし、味方だとしてもビビるってば。
彼は途中でピタリと足を止めた。
私が怯えているのに気づいたみたいだ。
触れようと伸ばしかけた手を、空中で止めた。
彼は拳をギュッと握ると、悔しそうにそれを下ろした。
『……遅れてすまない』
また声が聞こえた。
今度は頭の中から聞こえてくる声じゃなくて、ちゃんと耳に届く肉声に近い音。
でも、少し息が切れている。
その声は、恐ろしい見た目とは裏腹に、すごく掠れていて、なんだか見ていられないほど弱々しいものだった。
まるで、迷子になった子供が泣き出す寸前みたいな。
え……?
私は呆気にとられて、彼を見上げた。
彼は、苦しげに顔を歪めている。間に合わなかったこと、私を怖い目に遭わせてしまったことを、本気で悔やんでいるみたいに見える。
悪霊だと思っていた彼が、実は私を守るために必死だった?
そのギャップに、恐怖でカチコチだった心が、少しずつほぐれていくのを感じる。
彼は、そっと片膝をついて、私と目線の高さを合わせた。
地面に膝をつくなんて、服が汚れちゃうよ。
そんな場違いな心配をしてしまうくらい、彼の動きは人間そのものだった。
『怪我はないか』
短い言葉。でも、そこにはとんでもなく重い感情が込められていた。
私はコクンと頷く。声が出ないから、それが精一杯の返事。
彼は、ほっとしたように息を吐いた。
幽霊なのに、呼吸とかするんだ。
彼は、恐る恐る手を伸ばしてきた。
今度はためらわずに、私の頭に触れようとする。
私は逃げなかった。いや、不思議と逃げる気が起きなかった。
彼の大きな掌が、私の頭にポンと置かれる。
ひんやりとした感触。
でも、それは死人の不快な冷たさじゃなくて、熱が出た時におでこに貼る冷却シートみたいな、心地よい冷たさだった。
彼は、ぎこちない手つきで私の髪を優しくなでた。
よしよし、って子供をあやすみたいに。
壊れ物を扱うような、慎重で優しい手つき。
あれっ、意外と悪くない。
さっきの脱力感でクラクラしていた頭が、彼の手のひらから伝わる冷気で少しシャキッとする。
……私、おかしくなってる?
幽霊に頭を撫でられて安心するとか、正気じゃない。
窓の外では、陽が完全に落ちて、空が群青色に変わろうとしていた。
校舎の中はもう真っ暗だ。
けれど、私の目の前には、蒼白い炎の余韻を帯びた彼がいる。
なんだか、私たちの周りだけ淡い光に包まれていて、すごく幻想的だ。
私はゆっくりと、彼の手のひらに自分の手を重ねてみた。
彼は一瞬「えっ」という顔をして、それから、どこか照れくさそうに視線を外した。
その横顔を見て、私は確信した。
彼は、敵じゃない。
少なくとも、私を傷つける存在じゃない。
でも、まだ分からないことだらけだ。
「あの……」
ようやく、まともな声が出た。
彼がこちらを見る。金色の瞳が、真っ直ぐ私を見つめる。
「あなた、誰?」
当たり前の質問。でも、今一番聞きたいこと。
彼は、少し困ったような表情を浮かべている。
『レイ。俺の名は、レイだ』
レイ。
彼の名前。私を守ってくれた、この不思議な存在の名前。
「レイ……」
口に出してみると、なんだか不思議としっくりくる響きだった。
初めて呼んだはずなのに、何度も呼んだことがあるような、そんな錯覚。
『お前は?』
彼が、初めて私に質問してきた。
「一ノ瀬ヒナ。高校二年生」
私は、できるだけしっかりした声で答えた。
レイは、ゆっくりと頷いた。
その目が、優しく細められる。
『ヒナ……』
私の名前を、大切そうに繰り返す。
なにこれ。どういうこと。
助けてもらったのは嬉しいけど、まだ状況が全然飲み込めていない。
それに、なんだかすごく眠いような。いや、体が重い。
彼が炎を使ったあの時から、急に体力が底をついたみたいだ。
この人は何者なの?
全くよく分からないけれど。
とりあえず、私は助かったんだ。
私はレイの手を握ったまま、考えることを捨てた。
今はただ、このひんやりとした心地よさに身を任せて、まったりとしていたかったから。
昼間あんなにうるさかった教室が、嘘みたいにシーンとしてる。黒板消しクリーナーから漏れたチョークの粉の匂いとか、床ワックスの薬品臭さが、鼻の奥にツンとくる。
窓から差し込む夕日は、青春映画みたいな綺麗なオレンジ色なんかじゃない。もっとドロドロとした、古くなった血みたいな赤色。それが廊下を長く伸びて、まるで「こっちにおいで」って手招きしてるみたいに見える。
私は教室のドアに手をかけた。
立て付けの悪い引き戸は、ちょっと動かしただけでガタガタと大きな音を立てる。その乾いた音が誰もいない廊下に広がって、ビクッと肩が跳ねた。
……情けない。
自分の出す音にいちいちビビってるなんて、我ながらどうかしてる。
鞄の持ち手をギュッと握りしめた。手のひらにじっとりと汗が滲んでるのがわかる。
深呼吸。肺の中の空気を全部入れ替えるつもりで、大きく吸って、吐く。
大丈夫。まだ、平気。
私はそっと廊下へ足を踏み出した。
どこにでもいる普通の女子高生。それが私の表向きの顔。
成績もそこそこ、運動神経も人並み。クラスでは目立たないグループの端っこで、愛想笑いでやり過ごす。そうやって「普通」の皮を被って生きてきた。
でも、その皮の下には、誰にも言えない秘密がある。
私は、見えてしまうのだ。
普通の人には見えないはずの、この世ならざるモノたちが。
昔からずっとそうだった。
でも、親にも先生にも、絶対言わない。言えば「変な子」扱いされて孤立するだけだって、痛いほど学習したから。
だから私は、ひとつの鉄則を自分に課している。
――無視すること。
何が見えても、何が聞こえても、絶対に反応しない。そこに「いない」ものとして扱う。
それが、私がこの世界で平穏に生き延びるための、唯一の防衛策。
誰もいない廊下を、私は早足で歩く。
コツ、コツ、と上履きの底が床を叩く音が、やけに大きく聞こえた。
放課後の学校は、奴らにとって絶好の遊び場だ。人が減ったこの時間は、奴らが我が物顔でウロウロし始める。
だから、一刻も早く家に帰りたい。自分の部屋の布団に潜り込んで、朝が来るまで世界をシャットアウトしたい。
視線を床に落としたまま歩く。壁のシミや床の汚れ、そういう現実的なものだけに意識を集中させる。
うっかり何もない空間を見ちゃダメだ。そこには、たいてい「何か」が立っているから。
渡り廊下へ続く角が見えてきた。
あそこを曲がれば階段がある。そこを駆け下りれば、昇降口まではすぐ。
あと少し。
そう思った矢先だった。
ゾワリ、と背筋が凍りついた。
振り返らなくてもわかる。
私のすぐ「背後」に、とんでもないものが立っている。
呼吸音が聞こえる距離。いや、もっと近い。
ドロドロとした闇の気配。
それが、音もなく私の後ろに張り付き、首筋に冷たい息を吹きかけているような圧迫感。
殺される。
『……』
声なき殺意が、背中から突き刺さる。
見ちゃダメだ。振り返ったら終わる。
私は弾かれたように足を動かした。逃げなきゃ。前へ。角を曲がって、特別教室棟へ。
私は前のめりに駆け出した。
けれど、角に近づくにつれて、こめかみの奥がキリキリ痛み出した。
――進んではいけない。
――そっちにも、「いる」。
本能が警報を鳴らしてる。その角の先には、別の「厄災」が待ち構えてるって。
でも、止まれない。背後からは、空間をきしませるようなミシッ、ミシッという音が迫ってきてる。後ろの得体の知れない化け物に捕まるくらいなら、前の予感を無視して突っ切るしかない。
私は半泣きで角を飛び出し、渡り廊下へと飛び込んだ。
勢いがつきすぎて止まれない。上履きがキュッと音を立てて滑り、転びそうになりながら顔を上げた、その目の前。
人影があった。
廊下の中程、夕日を背にして、セーラー服を着た女子生徒が立っている。
(あ……よかった、人がいる!)
先生でもない、ただの生徒。
本能が鳴らしてた警報は、気のせいだったのかもしれない。この異様な空間で「生きた人間」に会えた安堵感は、何よりも大きかった。
私はすがるような思いで、その背中に向かって手を伸ばす。
「ねえ、逃げて! 後ろから変なのが……!」
私の声に反応して、彼女がゆっくりと振り返る。
長い黒髪がサラリと揺れる。
その顔が見えそうになった瞬間、頭の中に、知らない映像が勝手に流れ込んできた。
――ずっと、待ってたのに。
――約束したのに。誰も来ない。夕焼けが消える。暗くなる。怖い。寂しい。許さない。
強烈な「待ちぼうけ」の記憶。
誰かを待ってたはずの純粋な思いが、腐りきって、ドロドロの怨念に変わっちゃってる。
この子は、人間じゃない。
ツン、と鼻をつんざくような悪臭がした。
生ゴミのような、あるいは夏の炎天下で放置された肉みたいな、強烈な腐敗臭。
彼女が、ニッコリと笑う。
いや、そう見えたのは一瞬だった。
メキョッ。
湿った音がして、彼女の首が真横に傾いだ。
九十度、百八十度……さらに回転して、ありえない角度までねじ切れる。
笑顔のままの口元から、ドス黒い液体がダラダラと溢れ出した。
「――っ!?」
悲鳴すら出ない。
彼女の整っていた顔の皮膚が、熱した蝋みたいにドロドロと崩れ落ちていく。
剥がれ落ちた肉の下から覗いたのは、充血して真っ赤に染まった巨大な眼球だった。
そうだ、どうして気が付かなかったんだろう。私の学校の制服はブレザーだ。
目の前にいる「あれ」が、この学校の生徒なわけない。
だったら「あれ」が、まともな人間であるはずなんかない。
「ゆ……る……さ……」
崩れた喉の奥から、ヘドロが詰まったような濁った声が漏れる。
顎の関節が外れ、口が裂けるように大きく開かれた。暗い口の奥には、歯の代わりに無数の白い蛆が蠢いている。
ボロボロと口から蛆を吐き出しながら、それ――セーラー服の化け物が、私に向かって腕を伸ばしてきた。
後ろには黒い影。前には腐った女。
完全に挟まれた。逃げ場なんてどこにもない。
腐敗した指先が、私の顔に触れそうになる。
私は反射的に目を硬く閉じて、頭を抱えてうずくまった。
(お母さん、ごめん!)
走馬灯なんて綺麗なものは見えない。ただ、どうでもいい後悔だけが頭をよぎる。
こんなことになるなら、昨日の夕飯のハンバーグ、もっと味わって食べればよかった。苦手な数学の宿題なんて、サボればよかった。
鋭い爪が、私の顔に届く寸前。
ドタドタドタッ!!
不釣り合いな音が聞こえた。
幽霊が立てるような音じゃない。誰かが廊下を全力疾走してくる、荒々しい足音だ。
え?
ザシュッ!!
空間そのものを叩き割るような、鋭い音がした。
同時に、ものすごい暴風が吹き荒れる。
恐る恐る目を開けた私の視界に、翻る黒い布地が映り込んだ。
「はぁッ、はぁッ……!」
目の前に、誰かが立っていた。
私を背中で庇うようにして、立ちふさがっている。
肩で息をしている。ものすごく走ってきたみたいに、呼吸が荒い。
古風な学ランを着た、背の高い少年だった。
彼は、飛んできたセーラー服の霊を、なんと空中で止めていた。
魔法とかバリアとか、そんな綺麗なものじゃない。
片手で、霊の顔面を鷲掴みにしている。
細くしなやかな指が、腐った肉に容赦なくめり込んでいるのだ。
グチャリ、と嫌な音がする。
霊の動きが、空中でピタリと静止している。
何か叫ぼうとして口をパクパクさせているけれど、声になっていない。
メキ、メキメキ……と、頭蓋骨にヒビが入る乾いた音が聞こえてくる。
少年は、私の方を一度も振り返らなかった。
ただ、邪魔なゴミでもポイ捨てするかのように、無造作に腕を振るった。
ブンッ! と空気が唸りを上げ、霊の体が吹き飛ぶ。
ゴムボールみたいに軽々と投げ飛ばされた霊は、コンクリートの壁に激突した。
ドゴォォォン!!
校舎全体が揺れるような衝撃。
壁に蜘蛛の巣状のヒビが入って、白い粉塵が舞い上がる。
霊は壁にめり込んだまま、ぐったりと垂れ下がっている。
……強くない?
ていうか、何この人。どこから走ってきたの?
私はポカーンと口を開けて、その光景を見つめることしかできない。
これで終わり?
いや、まだだ。
壁にめり込んだ霊から、黒い煙のようなものが立ち昇っている。まだ消えていない。再生しようとしているんだ。
少年は、乱れた呼吸を整えながら、ゆっくりと右手をかざした。
その手のひらに、ボウッ、と蒼白い炎が灯った。
ズンッ。
その瞬間、私の体が急に重くなった。
まるで献血をした直後みたいに、スーッと血の気が引いていく。
え、なに? 目眩がする。
立っているのがやっとの状態で、私は彼の手元を見つめた。
ライターもマッチもないのに、虚空から生まれた炎。
それは、見ているだけで魂が凍りつきそうなほど、美しくて冷たい色をしていた。
『……滅せよ』
初めて、彼が声を発した。
低くて、お腹の底から聞こえるようないい声。
彼が手を握り込むと同時に、霊の体を蒼い炎が包み込んだ。
ギャァァァァァ!
耳を塞ぎたくなるような、耳を貫く断末魔。
炎は一瞬で燃え上がって、霊の姿を跡形もなく焼き尽くしていく。
ほんの数秒の出来事だった。
あとには、ただ煤けた壁のシミだけが残っていた。
シーン……と、再び静寂が戻ってくる。
あの強烈な腐敗臭も、嘘みたいに消え去っている。残っているのは、オゾン臭のような、雨上がりのアスファルトのような、不思議な匂いだけ。
私は、腰が抜けてその場にへたり込んでいた。
恐怖と、さっきの謎の脱力感で、指先一つ動かせない。
助かった……の?
あの蛆虫女に殺される寸前で、この人が助けてくれたってこと?
でも、なんで?
さっきまでいなかったのに、わざわざ走ってきてまで?
少年が、ゆっくりと振り返る。
ヒッ、と喉が鳴る。
逆光ではなくなったから、その顔がはっきりと見えた。
透き通るような白い肌。やっぱり、めちゃくちゃ美形だ。テレビに出ているアイドルや俳優ですら霞んで見えるほどの整い方。
でも、その顔は汗で少し濡れていて、前髪も乱れている。
さっきの鬼のような形相は消えていて、今は……なんだろう。
困ったような、ひどく悲しそうな顔をしている。
金色の瞳が、静かに私を見下ろす。
そこには、殺意も敵意もない。あるのは、深い安堵と、切なさのような感情だった。
彼は、私に向かって一歩踏み出した。
私はビクッと体をこわばらせる。
だって怖いものは怖い。あんな圧倒的な暴力を見せられた後だし、味方だとしてもビビるってば。
彼は途中でピタリと足を止めた。
私が怯えているのに気づいたみたいだ。
触れようと伸ばしかけた手を、空中で止めた。
彼は拳をギュッと握ると、悔しそうにそれを下ろした。
『……遅れてすまない』
また声が聞こえた。
今度は頭の中から聞こえてくる声じゃなくて、ちゃんと耳に届く肉声に近い音。
でも、少し息が切れている。
その声は、恐ろしい見た目とは裏腹に、すごく掠れていて、なんだか見ていられないほど弱々しいものだった。
まるで、迷子になった子供が泣き出す寸前みたいな。
え……?
私は呆気にとられて、彼を見上げた。
彼は、苦しげに顔を歪めている。間に合わなかったこと、私を怖い目に遭わせてしまったことを、本気で悔やんでいるみたいに見える。
悪霊だと思っていた彼が、実は私を守るために必死だった?
そのギャップに、恐怖でカチコチだった心が、少しずつほぐれていくのを感じる。
彼は、そっと片膝をついて、私と目線の高さを合わせた。
地面に膝をつくなんて、服が汚れちゃうよ。
そんな場違いな心配をしてしまうくらい、彼の動きは人間そのものだった。
『怪我はないか』
短い言葉。でも、そこにはとんでもなく重い感情が込められていた。
私はコクンと頷く。声が出ないから、それが精一杯の返事。
彼は、ほっとしたように息を吐いた。
幽霊なのに、呼吸とかするんだ。
彼は、恐る恐る手を伸ばしてきた。
今度はためらわずに、私の頭に触れようとする。
私は逃げなかった。いや、不思議と逃げる気が起きなかった。
彼の大きな掌が、私の頭にポンと置かれる。
ひんやりとした感触。
でも、それは死人の不快な冷たさじゃなくて、熱が出た時におでこに貼る冷却シートみたいな、心地よい冷たさだった。
彼は、ぎこちない手つきで私の髪を優しくなでた。
よしよし、って子供をあやすみたいに。
壊れ物を扱うような、慎重で優しい手つき。
あれっ、意外と悪くない。
さっきの脱力感でクラクラしていた頭が、彼の手のひらから伝わる冷気で少しシャキッとする。
……私、おかしくなってる?
幽霊に頭を撫でられて安心するとか、正気じゃない。
窓の外では、陽が完全に落ちて、空が群青色に変わろうとしていた。
校舎の中はもう真っ暗だ。
けれど、私の目の前には、蒼白い炎の余韻を帯びた彼がいる。
なんだか、私たちの周りだけ淡い光に包まれていて、すごく幻想的だ。
私はゆっくりと、彼の手のひらに自分の手を重ねてみた。
彼は一瞬「えっ」という顔をして、それから、どこか照れくさそうに視線を外した。
その横顔を見て、私は確信した。
彼は、敵じゃない。
少なくとも、私を傷つける存在じゃない。
でも、まだ分からないことだらけだ。
「あの……」
ようやく、まともな声が出た。
彼がこちらを見る。金色の瞳が、真っ直ぐ私を見つめる。
「あなた、誰?」
当たり前の質問。でも、今一番聞きたいこと。
彼は、少し困ったような表情を浮かべている。
『レイ。俺の名は、レイだ』
レイ。
彼の名前。私を守ってくれた、この不思議な存在の名前。
「レイ……」
口に出してみると、なんだか不思議としっくりくる響きだった。
初めて呼んだはずなのに、何度も呼んだことがあるような、そんな錯覚。
『お前は?』
彼が、初めて私に質問してきた。
「一ノ瀬ヒナ。高校二年生」
私は、できるだけしっかりした声で答えた。
レイは、ゆっくりと頷いた。
その目が、優しく細められる。
『ヒナ……』
私の名前を、大切そうに繰り返す。
なにこれ。どういうこと。
助けてもらったのは嬉しいけど、まだ状況が全然飲み込めていない。
それに、なんだかすごく眠いような。いや、体が重い。
彼が炎を使ったあの時から、急に体力が底をついたみたいだ。
この人は何者なの?
全くよく分からないけれど。
とりあえず、私は助かったんだ。
私はレイの手を握ったまま、考えることを捨てた。
今はただ、このひんやりとした心地よさに身を任せて、まったりとしていたかったから。