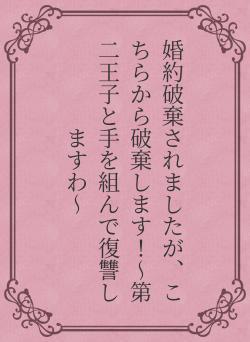翌朝。
霞のような淡い光が朱宮の庭園を覆う。
花は小部屋の襖を開け、薄曇りの空を眺めた。
空気は冷たく、かすかに湿っている。
庭園の苔が露に光り、石畳を滑るように小さな雫が落ちる。
鳥の囀りもなく、ただ静寂が広がっていた。
後宮においては、この静けさが何よりも恐ろしい。
誰もが表面は穏やかに振る舞うが、目の奥には必ず計略が潜んでいる。
そして、花はその渦中に飛び込んでしまったのだ。
昨夜、朱皇の視線が自分を捉えた瞬間、胸が強く高鳴った。
しかし、同時に理解していた。
この静けさの背後には、侍女や姫君たちの嫉妬、陰謀、そして宮中全体の監視が存在することを。
「……どうすればよいのだろう」
花はつぶやき、かんざしを握りしめた。
母の形見は、まだほんのわずかに温度を持っている。
それは、まるで母の意思が自分を守ろうとしているかのように感じられた。
部屋の襖が静かに開き、侍女長が姿を現した。
長い黒髪は整然と後ろに束ねられ、表情は凛としている。
「香凛……ではなく花殿。帝よりの命により、今日から宮中の作法を学ぶことになる」
侍女長の声は柔らかくも鋭く、言葉の端々に試すような響きがあった。
花は深くうなずき、震える手でかんざしを押さえた。
庭を抜け、長廊下を進む。
花は足音を立てぬよう慎重に歩いた。
だが、何度も周囲の視線を感じる。
眼差しの中には好奇心だけでなく、敵意すら混じっていた。
侍女長は、途中で花に問いかけた。
「花殿、昨夜、帝に何を申したのか覚えておるか?」
「……はい。私は、帝のことも宮のことも知らないと答えました」
その返答に侍女長は小さく笑った。
しかし、その目は油断ならぬものだった。
「なるほど……無垢なる心で答えたか。だが、宮中では無垢が時に刃となることを知るべき」
花は胸を詰まらせ、視線を落とした。
侍女長の言葉は、警告であり、教えであり、同時に試練の合図でもあった。
廊下を抜け、広間に通されると、すでに複数の姫君たちが整列していた。
彼女たちは花を見て、微かに顔をしかめる。
しかし表面は優雅な微笑を保っている。
それが、後宮の常であった。
侍女長が命じる。
「今日からは、宮中作法の基礎、服装、礼儀、そして帝への応対を学ぶ。
特に帝への振る舞いは、命の重さを伴うものと心得よ」
花は深くうなずき、心を引き締めた。
朱皇はまだ姿を現さなかった。
しかしその存在は、空気に満ちていた。
花は、目立たぬよう、しかし全身で息を潜めて立った。
訓練は厳しく、細やかな指導が続く。
着物の袖の角度、歩く速度、呼吸のタイミングまで――。
すべてが後宮での生死を左右する試練であった。
花は必死に学ぶ。
しかし、他の姫君たちは彼女を嘲るような視線を向け、些細な失敗すら見逃さなかった。
その視線の鋭さは、刃を向けられたかのように心を締め付けた。
昼を過ぎる頃、侍女長は花を呼び寄せ、ひそやかに告げた。
「花殿、気を付けるべきは帝だけではない。
後宮には、己の位置を守ろうとする者たちが多い。
彼女らの嫉妬や策略は、時に刃よりも鋭い」
花はその言葉を噛み締めた。
母の形見のかんざしを胸元で握り、己を奮い立たせる。
そして、日が暮れ始めると、朱皇が姿を現した。
衣は紅と黒の織り糸が入り混じり、光を受けて鮮やかに映える。
その瞳は夜を切り裂くように冷たく、しかし花の方を見たときだけ、温度を帯びていた。
「花、今日の心得を申せ」
花は言葉を選び、恐る恐る口を開いた。
「はい。帝にお仕えする者として、礼儀を欠かさず、心を慎むことと存じます」
朱皇は短く頷き、目を細めた。
「礼儀は知っている。だが、真心はどうか。心を欺かぬよう、己を試すがよい」
その言葉には、帝からの警告だけでなく、期待も混じっていた。
その後、後宮での生活は次第に慣れない緊張と、細やかな謀略に満ちていた。
姫君たちは花の動きを観察し、侍女たちは隙を見つけては注意を促す。
花は息を潜めつつ、しかし母の形見のかんざしと共に、少しずつ己を強くしていった。
ある夜、花は庭園にひっそりと足を運んだ。
月光が苔に落ち、銀色の光が揺れる。
花はひとり、かんざしを掌に置き、心を落ち着ける。
「母上……私、どうすればよいのですか」
声はかすかに震えるが、誰にも届かない。
ただ月の光と、遠くの宮殿の壁が応答してくれるだけだった。
そのとき、背後から静かな足音が近づいた。
「……花か」
振り返ると、そこには朱皇が立っていた。
目は柔らかく、しかしその存在感は圧倒的だった。
「ここで何をしておる」
「……月を見ておりました」
花はうつむいたまま答えた。
帝はひと息つき、静かに言葉を重ねる。
「お前は、何も知らぬまま宮に入った。それが良いとも、危ういとも言えぬ。だが、覚えておけ。お前の存在は、宮中の水面に石を投じたのと同じこと。波紋は避けられぬ」
花は息を詰めた。
その言葉は、命令でもあり、予告でもあった。
朱皇はさらに近づき、花の肩に手を置いた。
「たとえ灰より出でようとも……お前を守る」
その手の温もりが、花の心に小さな光を灯した。
しかし同時に、後宮の暗闇が一層深く広がることも、彼女はまだ知らない。
翌朝、朱宮の空は雲が薄く広がり、淡い光が庭園の石畳に射していた。
花は薄暗い小部屋の襖を開け、庭園を見下ろす。
後宮の朝は早く、まだ鳥の声も届かぬ時間帯から、侍女や女官たちの足音が廊下に響く。
花は息を潜め、背筋を伸ばした。
昨夜、帝の視線を受けた胸の高鳴りがまだ残っている。
だがそれは、恐怖と同じくらいの重みを伴っていた。
母の形見であるかんざしが微かに熱を帯び、掌に触れるたびに心臓が跳ねる。
小さな光が胸に灯ったような感覚。
しかし、その光は一瞬で、宮中の暗闇に呑み込まれそうになる。
侍女長が部屋に現れ、花に告げた。
「花殿。今日から、後宮での正式な作法指導を開始する」
「……はい」
花は緊張で声が震えながらも、深くうなずく。
侍女長は表情を変えず、淡々と続けた。
「ただし、この指導は見せかけのものではない。
失敗すれば、噂としてすぐに宮中に広まり、帝の耳に届く」
その言葉に、花の背筋が凍る。
後宮の噂は、刀の切っ先のように鋭い。
その噂は命取りにもなりうる。
花は胸の奥で、母の言葉を思い出す。
「かんざしは、決して外すな」
母はそれを守ることで、自分の存在意義を託したのだ。
廊下を進む花の足音は、細く、しかし確実に石畳に落ちる。
周囲の視線が熱を帯びている。
侍女や姫君たちは、花の動きを細かく観察している。
誰もが、影の薄い花を軽んじてはいない。
表面は静かだが、内心では刺し違える覚悟で睨みを利かせている。
やがて広間に到着。
そこでは、他の姫君たちが整列して待っていた。
豪華な衣装に彩られた姫君たちは、花を見る目に嫉妬や疑念を混ぜ、薄笑いを浮かべている。
花は息を整え、影のように立つ。
だがその姿を、帝は既に注視していることを、花は知らなかった。
作法指導が始まる。
まずは歩き方。
歩幅、膝の角度、着物の裾の運び方。
ひとつ間違えば、笑い者になるか、後宮の策略に利用される。
侍女長の視線が厳しく刺さる。
花は背筋を伸ばし、呼吸を整えながら歩を進めた。
手に汗を握り、かんざしを胸に押し当てる。
石畳を踏むごとに、心臓が跳ねる。
次は座り方。
膝の角度、背筋の高さ、手の置き方。
花は何度も試みる。
しかし、袖が広すぎて指先が揺れ、他の姫君の笑い声が聞こえる。
そのたびに花は心の中で言い聞かせる。
「落ち着け……ここで誇りを失ってはならない」
侍女長は厳しい目を光らせる。
「香凛……ではなく花殿。貴様は、影のような存在であれど、目立つな。
帝の目は鋭く、ほんの些細な動作も見逃さぬ」
花は深くうなずいた。
その目は、敵意と忠告と、計算が入り混じっていた。
後宮は、安心できる場所などひとつもなかった。
昼を過ぎ、庭園で休息の時間。
花はひとり、池のほとりに座った。
水面に映る自分の姿は、まだ薄汚れた奉公人の面影を残している。
その手にあるかんざしが、微かに光を放つ。
光は自らの意思のように、花の胸の奥に何かを伝えようとしていた。
遠くで、侍女たちがささやき合う声が聞こえる。
「香凛様……いや、あの娘。
本当に帝に目を留められたのかしら?」
「まさか、下働きの娘が……」
花は知らず涙をこぼしそうになり、かんざしを握りしめる。
そのとき、背後に静かな気配。
振り返ると、朱皇が立っていた。
帝は夜を裂くような冷たさを湛えながらも、花の存在にだけは温度を感じさせる。
「花」
その呼びかけに、花の胸が高鳴る。
「昨夜、そして今日、宮中で何を学んだか」
「……礼儀、作法、そして……心を慎むこと」
「よい。しかし、それだけでは不十分だ」
帝は目を細め、花の肩に手を置いた。
「心を欺かぬこと。己を守ること。後宮の水面に石を落とす者たちは、必ず波紋を生む。
波紋に流されぬよう、己を鍛えよ」
花は深くうなずいた。
その手の温もりに、母の温もりが重なるように感じられた。
その後、後宮での訓練は日を追うごとに厳しくなる。
姫君たちは陰謀を巡らせ、花の失敗を待つ。
侍女長は時折、花の肩を叩き、注意を与える。
花は少しずつ、影のように振る舞う術を覚え、帝の目に留まることの意味を理解し始める。
だが、後宮の闇は深い。
ある夜、花は庭園でひっそりと月を眺めていた。
月光が苔に落ち、銀色の雫が揺れる。
そこに帝が現れる。
彼の瞳は柔らかく、しかし存在感は圧倒的。
「花。覚えておけ。お前の存在は、後宮全体に波紋を広げた。 波紋は避けられぬ。だが私はお前を守る」
花は胸の奥で小さな光を感じる。
そして、後宮の暗闇の中、花の決意は固まった。
「……逃げません」
その言葉に、帝の瞳がわずかに揺れた。
波紋の中、花は新たな一歩を踏み出した。
夜の帳が朱宮を覆い、庭園の苔や石畳を銀色に染めていた。
花は小部屋を抜け出し、庭園の片隅に立つ。
ここは誰も見ないはずの場所――しかし、後宮において誰も見ない場所など存在しない。
月光に照らされる苔の上、花はかんざしを握りしめる。
微かに脈打つ紅玉の輝きが、心臓と呼応するかのように震えていた。
昨日、朱皇に呼ばれた時の視線が蘇る。
「名も無き花よ」
あの短い言葉の中に、世界を支配する力と、守られるという温もりが同時にあった。
花はその温度を胸に刻み、深く息を吸い込む。
その瞬間、背後で枝葉が揺れる音。
振り返ると、漆黒の衣をまとった影があった。
「……夜の散歩か」
低く響く声。朱皇だ。
花は小さく震え、かんざしを握り直す。
「はい……静かに考えたくて」
朱皇はゆっくりと歩み寄り、花の肩の上に手を置いた。
「考えるだけでは意味がない。行動せよ」
その一言は、単なる命令ではなく、未来への指針のようでもあった。
花はうなずき、影のように立ち尽くす。
その後、後宮では日ごとに緊張が増していった。
姫君たちは花を観察し、ささやき合う。
「香凛様……いや、あの娘、帝に目を留められたとは……」
その声には嫉妬と恐怖が入り混じり、花は静かに息を飲む。
翌日、花は正式な作法指導を受けることになった。
広間には複数の姫君が集まり、花を見下ろす視線を隠さない。
侍女長は厳しい目で、花のすべての動きを監視した。
歩き方、座り方、手の位置、視線の角度――
すべてが帝の目に留まる可能性がある。
花は深く息を吸い、母の形見を胸に押さえながら、ひとつずつ動作を慎重に行った。
しかし、後宮の嫉妬の波は止まらない。
一人の姫君が袖で笑いを押さえ、別の姫は小声で侍女に耳打ちする。
花の心臓は跳ね、呼吸が荒くなる。
侍女長が近づき、低くささやいた。
「影であれ、花殿。だが帝の目を引くな。波紋を生む者たちは、必ず刃となる」
花はうなずき、さらに姿勢を正す。
その日の夜、花は庭園を歩きながら考えた。
後宮の影は、ただの噂話ではない。
帝に選ばれたことで、彼女は生き残るために、知恵と勇気を使わねばならない。
母のかんざしは、ただの形見ではなく、なぜか帝の血脈と呼応する力を秘めていた。
その秘密を知らぬまま、花は宮中の渦に巻き込まれていく。
ある夜、後宮の奥深くで、花はひそかに聞いた声に凍りついた。
「帝が……あの娘に心を寄せるとは、我々の立場が危うい」
低い声は侍女長ではない。
影のような、計算された恐怖を孕む存在。
花は息を殺し、茂みの陰に身を隠す。
その声は後宮の陰謀の始まりを告げていた。
翌朝、朱皇が直接、花に面会した。
「花。今日から帝に仕える心得を改めて教える」
その言葉は命令であり、保護であり、同時に試練でもあった。
帝は花の手に軽く触れ、かんざしを確認する。
微かに光る紅玉が、帝の視線に反応して煌めく。
「……この反応、偶然ではないな」
帝の言葉に、花は背筋を凍らせる。
母のかんざしは、ただの装飾品ではなかった。
朱皇の血脈に関わる秘密を抱えていたのだ。
後宮での生活は日ごとに厳しくなる。
姫君たちは策略を練り、侍女たちは監視を強める。
花は息を潜めつつも、少しずつ己を鍛え、帝に気に入られることの意味を学ぶ。
ある日、後宮の舞踏室で事件が起きる。
他の姫君がわざと花の着物の裾を踏み、転びそうになる。
しかし花は、かんざしと母の教えを胸に、瞬時にバランスを取り直す。
帝の目はその瞬間に注がれていた。
「よく耐えたな」
帝の言葉に、花は小さく息をつく。
しかしその背後で、嫉妬と策略の影がさらに濃く広がっていた。
夜、花は月光に照らされながら庭園で独り考えた。
「母上……私、どうすればこの後宮で生きられるのですか」
その問いに答える者はいない。
ただ、風がかんざしを揺らし、紅玉が微かに光る。
母の意思が、光として伝わっているのかもしれない。
帝が再び現れる。
「花」
低く響く声に、花の胸が震える。
「後宮の渦は深い。お前はその中心に立つことになる」
花はうなずき、かんざしを握り直す。
「……逃げません」
帝の瞳がわずかに揺れる。
後宮の闇と波紋は、まだ序章に過ぎない。
母の形見、帝の選択、姫君たちの陰謀。
全てが絡み合い、花を大きな渦の中心へと引き寄せる。
その時、花の心には、恐怖よりも決意が強く宿っていた。
「私……この後宮で咲きます」
夜の静寂に、花の小さな声が響いた。
帝の手は、かすかに花の肩を押さえ、未来の約束を伝えるようにあった。
そして、後宮の闇の奥、嫉妬や策略の影がさらに蠢き始める。
夜の帳が深々と降り、朱宮の屋根瓦は月光を受けて青白く光っていた。
都の中心にそびえ立つ後宮は、表向きは絢爛豪華だが、夜になるとその影は獣のように形を変え、そこに暮らす女たちの野心や嫉妬をむさぼるようにうごめく。
その闇を、いま花はひとり、石畳の冷たさを足裏で感じながら歩いていた。
母が遺したかんざしを握りしめ、胸に寄せる。
月に照らされた紅玉は、まるで内側から呼吸しているかのように淡く脈打つ。
その光を見つめるたび、花は胸の底にある不安と勇気の、両方の感情を思い出す。
——母上。私は間違った道を歩いていませんか。
誰に問うわけでもない問いが、胸の中で渦を巻く。
昨日、帝・朱皇から向けられた視線が頭から離れない。あの瞳は冷徹でありながら、同時に温かく、花の存在をまるで最初から知っていたかのように見つめていた。
花は思わず胸に触れ、深い呼吸を繰り返す。
そのとき——。
背後の竹林がさわり、と小さく揺れた。
「……また夜に彷徨っているのか」
聞き慣れてしまった低い声。
振り返ると、月明かりに輪郭だけを浮かび上がらせた朱皇が立っていた。漆黒の外套が風に流れ、彼の存在そのものが夜を切り裂くようだった。
「す、朱皇さま……!」
「名を呼べと言っただろう。私はお前を特別扱いしているらしいからな」
さらりと恐ろしいことを口にする。
後宮の女たちが聞いたら卒倒しかねない言葉だ。
花は慌てて視線を伏せ、震える声を押し殺す。
「静かに考えたくて……少し、空気を吸いに出ただけでございます」
「空気など、後宮にはろくにないがな」
朱皇はゆっくりと歩み寄り、花の肩に軽く手を置いた。その手は驚くほど温かく、花は息を飲む。
「行きたい場所があれば言え。守るのは容易い」
「……恐れ多いことでございます」
「恐れなどいらぬ。お前の目は、恐れよりも……決意の色の方が濃い」
花の胸は大きく跳ねた。
朱皇が花にかける言葉は、いつも核心を突く。
見透かされてしまいそうで、逃げ出したくなるのに……逃げたくない。
「では、もう戻れ。夜の朱宮には、人の気配以上のものが潜む」
その言葉は警告のようでも、支えのようでもあった。
朱皇が去ったあと、花はしばらくその場に立ち尽くした。
月の下で、かんざしがひときわ強く光った。
翌日。
後宮は静謐を装いながらも、空気は張りつめていた。
花が帝に呼ばれたという噂は、すでに宮中の端々まで広がっている。
花が稽古場に向かうと、複数の姫君たちがこちらを振り返り、あからさまな視線を送ってきた。
「……あれが、灰の花。」
「帝に拾われた、と言うけれど。」
「拾われる価値がどこにあるのかしら。」
笑い声はひそやかで、刃のように冷たい。
花は胸奥の痛みをごまかしながら、慎重に呼吸を整えた。
しかし、歩くたびに視線が刺さる。まるで後宮全体が敵意に満ちているようだった。
「花殿、こちらへ」
侍女長が現れ、厳しい眼で花を見据えた。
その瞳には警戒と、かすかな保護の色がある。
「本日から、帝に仕えるにふさわしい作法を学んでいただきます。……覚悟は?」
「ございます」
「ならばよい。では始めましょう」
それは厳しい訓練だった。
歩き方ひとつとっても、足の指の揃え方、膝の角度、顎の高さまで細かく監視される。
扇の持ち方、座る瞬間の衣の流し方、声の出し方、笑みのつくり方……いずれも帝に見られても恥じぬ形でなければならない。
姫君たちは、花の一挙一動を嘲り笑いながら眺めている。
しかし花は反論せず、ただ黙々と学んだ。
侍女長は、ふたりきりになった瞬間にだけ、低くつぶやく。
「良いか、花殿。不自然に目立ってはならぬ。しかし……目を離すことも許されぬ。後宮とはそういう場所なのです」
「……はい」
「何よりも、背後に影があります。あなたを消すことが、帝のためになると信じる者もいるでしょう」
花は息を呑んだ。
「それでも――生きてください」
その言葉には、侍女長自身がどれほど荒波を越えてきたかが滲んでいた。
花は深く頭を下げる。
その日の稽古が終わったあと、花は疲労で足元がおぼつかなくなり、廊下で立ち止まった。
しかし、背後で衣擦れの音がした瞬間、緊張が全身に走った。
振り向くと、一人の姫君が艶やかな笑みを浮かべて立っている。
「ごきげんよう、名も無き花。今日も帝の前で震えずに立てたのかしら?」
その声音には甘さひとかけらもない。
花は軽く礼をし、黙って通り過ぎようとする。
だが姫君は行く手を塞いだ。
「あなたがどれほど取り繕おうと、所詮は替え玉の小娘。帝が飽きればすぐに捨てられる。……そのことを、よく覚えておきなさい」
花は何も言わず、深く頭を下げてその場を離れた。
だが、姫君の言葉は胸にひどく重くのしかかる。
その夜。
花は庭園の端で、ふと人の声を耳にする。
「帝が……あの娘に心寄せるとはな」
「あれでは、我らの計画に支障が出る」
「早めに処理するべきだ」
背筋に氷の刃が走った。
聞き慣れぬ男の声――後宮の者ではない。皇宮の深部に仕える、影の役目を持つ者たちか。
花は竹の陰に身を潜め、息を殺す。
「……あのかんざしも気になる。あれは……」
「帝の血に反応する。封印されたはずの……」
「声を落とせ!」
会話はそこで途切れたが、花の心臓は乱れたままだった。
母の形見が、帝の血に反応する?
封印――?
花は震える手でかんざしに触れた。
紅玉は、今までよりも強い光を帯びている。
——母上、いったい私は何を受け継いでしまったの?
答えはない。
しかし、確かに何かが動き出している。
翌朝。
朱皇が花を呼びつけた。
「花。……手を出せ」
「え?」
戸惑いながら差し出した手に、朱皇はそっと触れた。
その瞬間、かんざしの紅玉が強く光り、広間に淡い赤光が広がった。
「……やはりか」
朱皇の声は低く、重かった。
「そのかんざしは、ただの装飾ではない。……お前が持つべき理由がある」
「朱皇さま……?」
「怖れるな。理由はすぐにわかる」
朱皇は花の手に触れたまま離さなかった。
花は胸の奥が熱くなるのを感じた。
だが、二人のこうした関わりが、後宮全体の怒りを買わないはずもない。
昼の稽古中、また事件が起きた。
大広間で行われる礼法訓練、姫君たちが円を描くように歩く最中――。
誰かが、花の着物の裾をわざと引っかけた。
花の身体が前のめりに崩れる。
空気がざわりと揺れ、周囲の視線が集まる。
——転ぶ。
そう思った瞬間、花の頭に母の声のような響きがよぎった。
『落ちるときは、足よりも先に心を支えなさい』
瞬間、花は体をひねり、腕を伸ばし、崩れ落ちる寸前で片膝をついて姿勢を整えた。
衣は美しく波を描き、むしろ優雅でさえあった。
広間が静まり返る。
侍女長が驚愕の息を飲む。
「……見事です、花殿」
花は小さく礼をした。
姫君たちは悔しげに唇を噛む。
だが、その瞬間——。
「何事だ?」
帝が現れた。
ざわめきが広間を震わせる。
花は顔を上げられない。
朱皇は花の側へ歩み寄り、手を差し伸べた。
「よく耐えたな」
その言葉は、花の胸を強く揺らした。
しかし同時に、姫君たちの嫉妬は炎となって燃え上がる。
朱皇はその炎など意に介さない様子で、花を立たせた。
「……今後、花のそばには二人の護衛を付ける。後宮の治安が乱れている」
その言葉は明らかに、誰かの悪意を指していた。
夜、花は朱皇に呼ばれ、静かな庭で向かい合った。
「花、お前は後宮の中心に立つ。望まぬとしても、だ」
「……私なんて、ただの——」
「違う。お前は特別だ。……理由は、私にもまだわからぬが」
朱皇の瞳が揺れるのを初めて見た。
花は胸が締めつけられる。
「だが約束しよう。お前を守る。どれほど闇が迫ろうとも、私がすべてを払う」
花は息を呑む。
「朱皇さま……」
「名を呼べと言った」
「す、す……朱皇……さま?」
「ふ、まだ硬いな」
朱皇は微かに笑い、花の肩に手を置いた。
その手が伝える温度は、花の恐れを溶かし、決意を育てていく。
そして——。
後宮の奥深くで、花を陥れる策が密かに形を取り始めていた。
花はまだ知らない。
その陰謀こそが、彼女の出生の秘密に触れ、朱皇との運命をさらに大きく揺さぶることになると。
朱宮の夜は、静かに、しかし確実に、血と真実の香りを濃くしていった。
花は、己の胸の内を押し殺すように深く息を吸った。
後宮の回廊を歩くたび、周囲の視線が肌を刺すように絡みついてくる。
嫉妬、敵意、好奇、嘲笑、計算――それらが重なり合い、一歩進むたびに空気が濁るようだった。
従者として働いていた頃、向けられる視線といえば無関心か、厄介者を見るようなものばかり。
だが今は違う。
花という一個の存在が、後宮の均衡そのものを揺さぶるものとして数えられ始めているのだ。
朱皇に特別扱いされる――それだけで十分、彼女は標的となる。
彼のたった一言が、後宮中の女たちを不安と焦燥で煮立たせる。
帝にとって花が何なのか、誰もわからない。だがだからこそ、誰もが恐れていた。
宰相家の娘でも、名門貴族でもなく、どこの出なのかも明かさぬ灰かぶり。
そんな者がただ選ばれただけで序列が覆るのだとしたら――?
「……あの者が?」
「帝のあのまなざし……ありえぬ……」
「身分を偽っているに違いないわ。あの粗末な衣……」
「調べるべきでしょうね。徹底的に」
花が歩く後ろで、ささやきが黒い霧のように漂う。
彼女は耳に入らぬふりをしたが、胸の奥の痛みは拭えない。
だが、後宮が花を脅威と見なした理由はそれだけではなかった。
あの後――帝の私的な書庫へ呼び出されたことが、噂をさらに加速させたのだ。
誰一人立ち入れぬ場所に、帝が花一人を招いた。
その意味は、どれほど探らずとも想像できる。
後宮の女たちが血の気を上げるのも無理はなかった。
*
書庫での出来事を思い出すと、花の胸は熱くなり、同時にざわついた。
朱皇のあの言葉。
――「名を奪われ、身分を失っても、『花』という名だけは手放すな」
――「そのかんざしは、お前の守りだ」
優しすぎる声が、何度も脳裏に蘇る。
だが、優しさは人を惑わす。
自分は偽りの身でここへ来た。
帝の前に立つ資格など、どこにもない。
(遠ざからなければ……また誰かが傷つく)
奉公先の老婆に「行け」と言われた日。
身代わりとして宴に出されることが決まった日。
彼女の人生は勝手に動かされてきた。
だが今、後宮で動き出した陰謀の渦の中心にいるのは、他でもない彼女自身だ。
今度は、自分が誰かを巻き込む番――。
そう思うと、足がすくんだ。
「……どうすればいいの……」
一人呟いた声は、広い回廊に吸い込まれていく。
そのときだった。
「花さま……?」
控えめな声が背後から聞こえ、振り向くと、書庫で出会った女官・玲瓏が立っていた。
彼女は花より少し年上に見える。
後宮に珍しいほど静けさをまとい、必要以上に感情を見せない。
「顔色が優れません。少し、お休みになっては」
「……平気、です。少し……疲れただけで」
「疲れは、弱さではありません」
玲瓏は花の手を取るようにして言った。
「弱ってはいけないのは、この後宮そのもの。あなたは、弱ってもいい」
不思議な言葉だった。
花は思わず目を瞬いた。
玲瓏は薄く微笑むだけで、それ以上語らなかったが、彼女の瞳には同情とも忠誠とも違う、独特のものが浮かんでいた。
まるで、帝と花の間にある何かを既に知っているような――。
*
その翌日。
後宮は突然、ざわめきに包まれた。
柱廊を行き交う女官たちの足取りがいつになく急ぎ、貴妃たちが色めき立つ。
「どうしてこんな時期に……?」
「選妃の宴が終わって間もないのに……」
「わざわざ帝直筆の詔まで出されるなんて……」
花は呼び出しを受け、広場のような庭へ向かった。
そこには、後宮中の女官と妃嬪が集まっている。
皆が不安げに視線を交わし、そして中央に立つ帝の姿を見つめていた。
朱皇が静かに手を上げると、ざわめきは嘘のように止んだ。
「今日、この場に集まらせたのは他でもない」
帝の声は、かすかに冷たく響いた。
「後宮にある噂が流れていると聞いた」
花の背筋が凍る。
帝は続ける。
「名も地位も偽って宮中に入り込み、私の寵を得た者がいる――と⋯⋯」
広場が一瞬でざわめきに包まれた。
誰もが互いの顔を見合う。
だが、突き刺さる視線の半数は、花に向けられていた。
(どうしよう……)
息が詰まり、手が震え始める。
帝はゆっくりと視線を巡らせた。
ひどく冷静で、ひどく残酷に見える。
「ならば、問おう」
朱皇の視線が、集まった女官・妃嬪を一人ひとり貫く。
「この中で、自ら身分が偽りであると証明されたい者は、前へ出よ」
暴風の前触れのように、空気がぴたりと静まった。
花の胸が痛いほど鳴る。
足がすくむ。
ここで名乗り出れば、自分はすべてを失う。
奉公先の家も、ここでの立場も、命さえ危うい。
だが――。
帝がこんなことをするはずがない。
花を追い詰めるような真似を、なぜ。
そのとき。
「……出る人など、いるはずがありません」
貴妃の一人がそう言った。
「帝のご寵愛を受けたいがために、誰かの虚言が広まっただけでしょう」
「虚言、か」
朱皇は苦く笑い、視線を群衆の右端へ向けた。
そこには――。
先日、花に水を浴びせた妃がいた。
彼女は青ざめた顔で震えている。
「ひ、陛下……!わ、私は……」
「身に覚えがないのなら、震える理由はないだろう」
帝の声は冷え切っていた。
「だが、お前が“探っていた”ことは知っている。花について、彼女の出自についてな」
広場全体が息を飲む音がした。
花の心臓が跳ねた。
帝は……知っていたの?
妃は泣き崩れた。
「ち、違います!! 私はただ……!彼女の身なりが怪しいと思って、それで……!」
「怪しい、か」
朱皇は花を一瞥した。
「私の目が、偽りを見抜けぬと言うのか?」
「い、いえっ……!!そ、そんなつもりは……!」
妃の声は涙で濁っていく。
帝は彼女を見下ろし、淡々と告げた。
「お前の罪は、偽りを暴くことではない。身分の低い者を侮り、私の判断をも侮ったことだ。ゆえに、相応の処罰を与える」
妃の顔色が真っ青になった。
花は思わず震えた。
だが――次の帝の言葉は、それ以上に彼女を震わせた。
「そして、花を――二度と侮るな」
広場に満ちた空気が、がらりと変わった。
これまで灰かぶりと嘲られてきた少女の周囲が、一瞬にして強固な結界のような威圧に包まれる。
朱皇が一歩、花の方へ歩み寄った。
彼の瞳が、すぐ目の前にある。
どこまでもまっすぐに、彼女の心を見抜くように。
「花」
低く、やわらかい声が響く。
「何を恐れている?」
「……わ、私は……」
言葉が喉につかえる。
「お前を偽物だという者は、私が許さぬ」
「お前を傷つける者も、私が許さぬ」
「お前を奪う者が現れたら――世界のどこであれ、私はそれを焼き払う」
花は息を呑んだ。
朱皇は手を伸ばし、彼女のかんざしに触れた。
まるで、それが宝物であるかのように。
「これは、お前がお前である証だ。奪われることも、失われることも、もう無い」
その言葉は、花の心の奥深くに、静かに落ちていった。
(……どうして、そこまで……?)
聞きたいのに、言葉にできない。
だが、朱皇の瞳を見ていると、不思議と胸が痛くなくなった。
帝は背を向け、後宮中へ響くように声を放った。
「よいか。花は私が選んだ者だ。その目を曇らせれば、後宮そのものが崩れると思え」
その宣言は、後宮に新たな秩序を刻みつけるものだった。
同時に――陰で暗躍していた者たちの心に、危険な火をともすことにもなった。
帝がここまで庇うのなら。
花はただの灰かぶりではない。
帝の心を動かす何かを持つ、特別な存在――いや。
(……皇統に関わる秘密を、持っているのではないか?)
そんな疑念が、静かに芽を出し始めたのだ。
霞のような淡い光が朱宮の庭園を覆う。
花は小部屋の襖を開け、薄曇りの空を眺めた。
空気は冷たく、かすかに湿っている。
庭園の苔が露に光り、石畳を滑るように小さな雫が落ちる。
鳥の囀りもなく、ただ静寂が広がっていた。
後宮においては、この静けさが何よりも恐ろしい。
誰もが表面は穏やかに振る舞うが、目の奥には必ず計略が潜んでいる。
そして、花はその渦中に飛び込んでしまったのだ。
昨夜、朱皇の視線が自分を捉えた瞬間、胸が強く高鳴った。
しかし、同時に理解していた。
この静けさの背後には、侍女や姫君たちの嫉妬、陰謀、そして宮中全体の監視が存在することを。
「……どうすればよいのだろう」
花はつぶやき、かんざしを握りしめた。
母の形見は、まだほんのわずかに温度を持っている。
それは、まるで母の意思が自分を守ろうとしているかのように感じられた。
部屋の襖が静かに開き、侍女長が姿を現した。
長い黒髪は整然と後ろに束ねられ、表情は凛としている。
「香凛……ではなく花殿。帝よりの命により、今日から宮中の作法を学ぶことになる」
侍女長の声は柔らかくも鋭く、言葉の端々に試すような響きがあった。
花は深くうなずき、震える手でかんざしを押さえた。
庭を抜け、長廊下を進む。
花は足音を立てぬよう慎重に歩いた。
だが、何度も周囲の視線を感じる。
眼差しの中には好奇心だけでなく、敵意すら混じっていた。
侍女長は、途中で花に問いかけた。
「花殿、昨夜、帝に何を申したのか覚えておるか?」
「……はい。私は、帝のことも宮のことも知らないと答えました」
その返答に侍女長は小さく笑った。
しかし、その目は油断ならぬものだった。
「なるほど……無垢なる心で答えたか。だが、宮中では無垢が時に刃となることを知るべき」
花は胸を詰まらせ、視線を落とした。
侍女長の言葉は、警告であり、教えであり、同時に試練の合図でもあった。
廊下を抜け、広間に通されると、すでに複数の姫君たちが整列していた。
彼女たちは花を見て、微かに顔をしかめる。
しかし表面は優雅な微笑を保っている。
それが、後宮の常であった。
侍女長が命じる。
「今日からは、宮中作法の基礎、服装、礼儀、そして帝への応対を学ぶ。
特に帝への振る舞いは、命の重さを伴うものと心得よ」
花は深くうなずき、心を引き締めた。
朱皇はまだ姿を現さなかった。
しかしその存在は、空気に満ちていた。
花は、目立たぬよう、しかし全身で息を潜めて立った。
訓練は厳しく、細やかな指導が続く。
着物の袖の角度、歩く速度、呼吸のタイミングまで――。
すべてが後宮での生死を左右する試練であった。
花は必死に学ぶ。
しかし、他の姫君たちは彼女を嘲るような視線を向け、些細な失敗すら見逃さなかった。
その視線の鋭さは、刃を向けられたかのように心を締め付けた。
昼を過ぎる頃、侍女長は花を呼び寄せ、ひそやかに告げた。
「花殿、気を付けるべきは帝だけではない。
後宮には、己の位置を守ろうとする者たちが多い。
彼女らの嫉妬や策略は、時に刃よりも鋭い」
花はその言葉を噛み締めた。
母の形見のかんざしを胸元で握り、己を奮い立たせる。
そして、日が暮れ始めると、朱皇が姿を現した。
衣は紅と黒の織り糸が入り混じり、光を受けて鮮やかに映える。
その瞳は夜を切り裂くように冷たく、しかし花の方を見たときだけ、温度を帯びていた。
「花、今日の心得を申せ」
花は言葉を選び、恐る恐る口を開いた。
「はい。帝にお仕えする者として、礼儀を欠かさず、心を慎むことと存じます」
朱皇は短く頷き、目を細めた。
「礼儀は知っている。だが、真心はどうか。心を欺かぬよう、己を試すがよい」
その言葉には、帝からの警告だけでなく、期待も混じっていた。
その後、後宮での生活は次第に慣れない緊張と、細やかな謀略に満ちていた。
姫君たちは花の動きを観察し、侍女たちは隙を見つけては注意を促す。
花は息を潜めつつ、しかし母の形見のかんざしと共に、少しずつ己を強くしていった。
ある夜、花は庭園にひっそりと足を運んだ。
月光が苔に落ち、銀色の光が揺れる。
花はひとり、かんざしを掌に置き、心を落ち着ける。
「母上……私、どうすればよいのですか」
声はかすかに震えるが、誰にも届かない。
ただ月の光と、遠くの宮殿の壁が応答してくれるだけだった。
そのとき、背後から静かな足音が近づいた。
「……花か」
振り返ると、そこには朱皇が立っていた。
目は柔らかく、しかしその存在感は圧倒的だった。
「ここで何をしておる」
「……月を見ておりました」
花はうつむいたまま答えた。
帝はひと息つき、静かに言葉を重ねる。
「お前は、何も知らぬまま宮に入った。それが良いとも、危ういとも言えぬ。だが、覚えておけ。お前の存在は、宮中の水面に石を投じたのと同じこと。波紋は避けられぬ」
花は息を詰めた。
その言葉は、命令でもあり、予告でもあった。
朱皇はさらに近づき、花の肩に手を置いた。
「たとえ灰より出でようとも……お前を守る」
その手の温もりが、花の心に小さな光を灯した。
しかし同時に、後宮の暗闇が一層深く広がることも、彼女はまだ知らない。
翌朝、朱宮の空は雲が薄く広がり、淡い光が庭園の石畳に射していた。
花は薄暗い小部屋の襖を開け、庭園を見下ろす。
後宮の朝は早く、まだ鳥の声も届かぬ時間帯から、侍女や女官たちの足音が廊下に響く。
花は息を潜め、背筋を伸ばした。
昨夜、帝の視線を受けた胸の高鳴りがまだ残っている。
だがそれは、恐怖と同じくらいの重みを伴っていた。
母の形見であるかんざしが微かに熱を帯び、掌に触れるたびに心臓が跳ねる。
小さな光が胸に灯ったような感覚。
しかし、その光は一瞬で、宮中の暗闇に呑み込まれそうになる。
侍女長が部屋に現れ、花に告げた。
「花殿。今日から、後宮での正式な作法指導を開始する」
「……はい」
花は緊張で声が震えながらも、深くうなずく。
侍女長は表情を変えず、淡々と続けた。
「ただし、この指導は見せかけのものではない。
失敗すれば、噂としてすぐに宮中に広まり、帝の耳に届く」
その言葉に、花の背筋が凍る。
後宮の噂は、刀の切っ先のように鋭い。
その噂は命取りにもなりうる。
花は胸の奥で、母の言葉を思い出す。
「かんざしは、決して外すな」
母はそれを守ることで、自分の存在意義を託したのだ。
廊下を進む花の足音は、細く、しかし確実に石畳に落ちる。
周囲の視線が熱を帯びている。
侍女や姫君たちは、花の動きを細かく観察している。
誰もが、影の薄い花を軽んじてはいない。
表面は静かだが、内心では刺し違える覚悟で睨みを利かせている。
やがて広間に到着。
そこでは、他の姫君たちが整列して待っていた。
豪華な衣装に彩られた姫君たちは、花を見る目に嫉妬や疑念を混ぜ、薄笑いを浮かべている。
花は息を整え、影のように立つ。
だがその姿を、帝は既に注視していることを、花は知らなかった。
作法指導が始まる。
まずは歩き方。
歩幅、膝の角度、着物の裾の運び方。
ひとつ間違えば、笑い者になるか、後宮の策略に利用される。
侍女長の視線が厳しく刺さる。
花は背筋を伸ばし、呼吸を整えながら歩を進めた。
手に汗を握り、かんざしを胸に押し当てる。
石畳を踏むごとに、心臓が跳ねる。
次は座り方。
膝の角度、背筋の高さ、手の置き方。
花は何度も試みる。
しかし、袖が広すぎて指先が揺れ、他の姫君の笑い声が聞こえる。
そのたびに花は心の中で言い聞かせる。
「落ち着け……ここで誇りを失ってはならない」
侍女長は厳しい目を光らせる。
「香凛……ではなく花殿。貴様は、影のような存在であれど、目立つな。
帝の目は鋭く、ほんの些細な動作も見逃さぬ」
花は深くうなずいた。
その目は、敵意と忠告と、計算が入り混じっていた。
後宮は、安心できる場所などひとつもなかった。
昼を過ぎ、庭園で休息の時間。
花はひとり、池のほとりに座った。
水面に映る自分の姿は、まだ薄汚れた奉公人の面影を残している。
その手にあるかんざしが、微かに光を放つ。
光は自らの意思のように、花の胸の奥に何かを伝えようとしていた。
遠くで、侍女たちがささやき合う声が聞こえる。
「香凛様……いや、あの娘。
本当に帝に目を留められたのかしら?」
「まさか、下働きの娘が……」
花は知らず涙をこぼしそうになり、かんざしを握りしめる。
そのとき、背後に静かな気配。
振り返ると、朱皇が立っていた。
帝は夜を裂くような冷たさを湛えながらも、花の存在にだけは温度を感じさせる。
「花」
その呼びかけに、花の胸が高鳴る。
「昨夜、そして今日、宮中で何を学んだか」
「……礼儀、作法、そして……心を慎むこと」
「よい。しかし、それだけでは不十分だ」
帝は目を細め、花の肩に手を置いた。
「心を欺かぬこと。己を守ること。後宮の水面に石を落とす者たちは、必ず波紋を生む。
波紋に流されぬよう、己を鍛えよ」
花は深くうなずいた。
その手の温もりに、母の温もりが重なるように感じられた。
その後、後宮での訓練は日を追うごとに厳しくなる。
姫君たちは陰謀を巡らせ、花の失敗を待つ。
侍女長は時折、花の肩を叩き、注意を与える。
花は少しずつ、影のように振る舞う術を覚え、帝の目に留まることの意味を理解し始める。
だが、後宮の闇は深い。
ある夜、花は庭園でひっそりと月を眺めていた。
月光が苔に落ち、銀色の雫が揺れる。
そこに帝が現れる。
彼の瞳は柔らかく、しかし存在感は圧倒的。
「花。覚えておけ。お前の存在は、後宮全体に波紋を広げた。 波紋は避けられぬ。だが私はお前を守る」
花は胸の奥で小さな光を感じる。
そして、後宮の暗闇の中、花の決意は固まった。
「……逃げません」
その言葉に、帝の瞳がわずかに揺れた。
波紋の中、花は新たな一歩を踏み出した。
夜の帳が朱宮を覆い、庭園の苔や石畳を銀色に染めていた。
花は小部屋を抜け出し、庭園の片隅に立つ。
ここは誰も見ないはずの場所――しかし、後宮において誰も見ない場所など存在しない。
月光に照らされる苔の上、花はかんざしを握りしめる。
微かに脈打つ紅玉の輝きが、心臓と呼応するかのように震えていた。
昨日、朱皇に呼ばれた時の視線が蘇る。
「名も無き花よ」
あの短い言葉の中に、世界を支配する力と、守られるという温もりが同時にあった。
花はその温度を胸に刻み、深く息を吸い込む。
その瞬間、背後で枝葉が揺れる音。
振り返ると、漆黒の衣をまとった影があった。
「……夜の散歩か」
低く響く声。朱皇だ。
花は小さく震え、かんざしを握り直す。
「はい……静かに考えたくて」
朱皇はゆっくりと歩み寄り、花の肩の上に手を置いた。
「考えるだけでは意味がない。行動せよ」
その一言は、単なる命令ではなく、未来への指針のようでもあった。
花はうなずき、影のように立ち尽くす。
その後、後宮では日ごとに緊張が増していった。
姫君たちは花を観察し、ささやき合う。
「香凛様……いや、あの娘、帝に目を留められたとは……」
その声には嫉妬と恐怖が入り混じり、花は静かに息を飲む。
翌日、花は正式な作法指導を受けることになった。
広間には複数の姫君が集まり、花を見下ろす視線を隠さない。
侍女長は厳しい目で、花のすべての動きを監視した。
歩き方、座り方、手の位置、視線の角度――
すべてが帝の目に留まる可能性がある。
花は深く息を吸い、母の形見を胸に押さえながら、ひとつずつ動作を慎重に行った。
しかし、後宮の嫉妬の波は止まらない。
一人の姫君が袖で笑いを押さえ、別の姫は小声で侍女に耳打ちする。
花の心臓は跳ね、呼吸が荒くなる。
侍女長が近づき、低くささやいた。
「影であれ、花殿。だが帝の目を引くな。波紋を生む者たちは、必ず刃となる」
花はうなずき、さらに姿勢を正す。
その日の夜、花は庭園を歩きながら考えた。
後宮の影は、ただの噂話ではない。
帝に選ばれたことで、彼女は生き残るために、知恵と勇気を使わねばならない。
母のかんざしは、ただの形見ではなく、なぜか帝の血脈と呼応する力を秘めていた。
その秘密を知らぬまま、花は宮中の渦に巻き込まれていく。
ある夜、後宮の奥深くで、花はひそかに聞いた声に凍りついた。
「帝が……あの娘に心を寄せるとは、我々の立場が危うい」
低い声は侍女長ではない。
影のような、計算された恐怖を孕む存在。
花は息を殺し、茂みの陰に身を隠す。
その声は後宮の陰謀の始まりを告げていた。
翌朝、朱皇が直接、花に面会した。
「花。今日から帝に仕える心得を改めて教える」
その言葉は命令であり、保護であり、同時に試練でもあった。
帝は花の手に軽く触れ、かんざしを確認する。
微かに光る紅玉が、帝の視線に反応して煌めく。
「……この反応、偶然ではないな」
帝の言葉に、花は背筋を凍らせる。
母のかんざしは、ただの装飾品ではなかった。
朱皇の血脈に関わる秘密を抱えていたのだ。
後宮での生活は日ごとに厳しくなる。
姫君たちは策略を練り、侍女たちは監視を強める。
花は息を潜めつつも、少しずつ己を鍛え、帝に気に入られることの意味を学ぶ。
ある日、後宮の舞踏室で事件が起きる。
他の姫君がわざと花の着物の裾を踏み、転びそうになる。
しかし花は、かんざしと母の教えを胸に、瞬時にバランスを取り直す。
帝の目はその瞬間に注がれていた。
「よく耐えたな」
帝の言葉に、花は小さく息をつく。
しかしその背後で、嫉妬と策略の影がさらに濃く広がっていた。
夜、花は月光に照らされながら庭園で独り考えた。
「母上……私、どうすればこの後宮で生きられるのですか」
その問いに答える者はいない。
ただ、風がかんざしを揺らし、紅玉が微かに光る。
母の意思が、光として伝わっているのかもしれない。
帝が再び現れる。
「花」
低く響く声に、花の胸が震える。
「後宮の渦は深い。お前はその中心に立つことになる」
花はうなずき、かんざしを握り直す。
「……逃げません」
帝の瞳がわずかに揺れる。
後宮の闇と波紋は、まだ序章に過ぎない。
母の形見、帝の選択、姫君たちの陰謀。
全てが絡み合い、花を大きな渦の中心へと引き寄せる。
その時、花の心には、恐怖よりも決意が強く宿っていた。
「私……この後宮で咲きます」
夜の静寂に、花の小さな声が響いた。
帝の手は、かすかに花の肩を押さえ、未来の約束を伝えるようにあった。
そして、後宮の闇の奥、嫉妬や策略の影がさらに蠢き始める。
夜の帳が深々と降り、朱宮の屋根瓦は月光を受けて青白く光っていた。
都の中心にそびえ立つ後宮は、表向きは絢爛豪華だが、夜になるとその影は獣のように形を変え、そこに暮らす女たちの野心や嫉妬をむさぼるようにうごめく。
その闇を、いま花はひとり、石畳の冷たさを足裏で感じながら歩いていた。
母が遺したかんざしを握りしめ、胸に寄せる。
月に照らされた紅玉は、まるで内側から呼吸しているかのように淡く脈打つ。
その光を見つめるたび、花は胸の底にある不安と勇気の、両方の感情を思い出す。
——母上。私は間違った道を歩いていませんか。
誰に問うわけでもない問いが、胸の中で渦を巻く。
昨日、帝・朱皇から向けられた視線が頭から離れない。あの瞳は冷徹でありながら、同時に温かく、花の存在をまるで最初から知っていたかのように見つめていた。
花は思わず胸に触れ、深い呼吸を繰り返す。
そのとき——。
背後の竹林がさわり、と小さく揺れた。
「……また夜に彷徨っているのか」
聞き慣れてしまった低い声。
振り返ると、月明かりに輪郭だけを浮かび上がらせた朱皇が立っていた。漆黒の外套が風に流れ、彼の存在そのものが夜を切り裂くようだった。
「す、朱皇さま……!」
「名を呼べと言っただろう。私はお前を特別扱いしているらしいからな」
さらりと恐ろしいことを口にする。
後宮の女たちが聞いたら卒倒しかねない言葉だ。
花は慌てて視線を伏せ、震える声を押し殺す。
「静かに考えたくて……少し、空気を吸いに出ただけでございます」
「空気など、後宮にはろくにないがな」
朱皇はゆっくりと歩み寄り、花の肩に軽く手を置いた。その手は驚くほど温かく、花は息を飲む。
「行きたい場所があれば言え。守るのは容易い」
「……恐れ多いことでございます」
「恐れなどいらぬ。お前の目は、恐れよりも……決意の色の方が濃い」
花の胸は大きく跳ねた。
朱皇が花にかける言葉は、いつも核心を突く。
見透かされてしまいそうで、逃げ出したくなるのに……逃げたくない。
「では、もう戻れ。夜の朱宮には、人の気配以上のものが潜む」
その言葉は警告のようでも、支えのようでもあった。
朱皇が去ったあと、花はしばらくその場に立ち尽くした。
月の下で、かんざしがひときわ強く光った。
翌日。
後宮は静謐を装いながらも、空気は張りつめていた。
花が帝に呼ばれたという噂は、すでに宮中の端々まで広がっている。
花が稽古場に向かうと、複数の姫君たちがこちらを振り返り、あからさまな視線を送ってきた。
「……あれが、灰の花。」
「帝に拾われた、と言うけれど。」
「拾われる価値がどこにあるのかしら。」
笑い声はひそやかで、刃のように冷たい。
花は胸奥の痛みをごまかしながら、慎重に呼吸を整えた。
しかし、歩くたびに視線が刺さる。まるで後宮全体が敵意に満ちているようだった。
「花殿、こちらへ」
侍女長が現れ、厳しい眼で花を見据えた。
その瞳には警戒と、かすかな保護の色がある。
「本日から、帝に仕えるにふさわしい作法を学んでいただきます。……覚悟は?」
「ございます」
「ならばよい。では始めましょう」
それは厳しい訓練だった。
歩き方ひとつとっても、足の指の揃え方、膝の角度、顎の高さまで細かく監視される。
扇の持ち方、座る瞬間の衣の流し方、声の出し方、笑みのつくり方……いずれも帝に見られても恥じぬ形でなければならない。
姫君たちは、花の一挙一動を嘲り笑いながら眺めている。
しかし花は反論せず、ただ黙々と学んだ。
侍女長は、ふたりきりになった瞬間にだけ、低くつぶやく。
「良いか、花殿。不自然に目立ってはならぬ。しかし……目を離すことも許されぬ。後宮とはそういう場所なのです」
「……はい」
「何よりも、背後に影があります。あなたを消すことが、帝のためになると信じる者もいるでしょう」
花は息を呑んだ。
「それでも――生きてください」
その言葉には、侍女長自身がどれほど荒波を越えてきたかが滲んでいた。
花は深く頭を下げる。
その日の稽古が終わったあと、花は疲労で足元がおぼつかなくなり、廊下で立ち止まった。
しかし、背後で衣擦れの音がした瞬間、緊張が全身に走った。
振り向くと、一人の姫君が艶やかな笑みを浮かべて立っている。
「ごきげんよう、名も無き花。今日も帝の前で震えずに立てたのかしら?」
その声音には甘さひとかけらもない。
花は軽く礼をし、黙って通り過ぎようとする。
だが姫君は行く手を塞いだ。
「あなたがどれほど取り繕おうと、所詮は替え玉の小娘。帝が飽きればすぐに捨てられる。……そのことを、よく覚えておきなさい」
花は何も言わず、深く頭を下げてその場を離れた。
だが、姫君の言葉は胸にひどく重くのしかかる。
その夜。
花は庭園の端で、ふと人の声を耳にする。
「帝が……あの娘に心寄せるとはな」
「あれでは、我らの計画に支障が出る」
「早めに処理するべきだ」
背筋に氷の刃が走った。
聞き慣れぬ男の声――後宮の者ではない。皇宮の深部に仕える、影の役目を持つ者たちか。
花は竹の陰に身を潜め、息を殺す。
「……あのかんざしも気になる。あれは……」
「帝の血に反応する。封印されたはずの……」
「声を落とせ!」
会話はそこで途切れたが、花の心臓は乱れたままだった。
母の形見が、帝の血に反応する?
封印――?
花は震える手でかんざしに触れた。
紅玉は、今までよりも強い光を帯びている。
——母上、いったい私は何を受け継いでしまったの?
答えはない。
しかし、確かに何かが動き出している。
翌朝。
朱皇が花を呼びつけた。
「花。……手を出せ」
「え?」
戸惑いながら差し出した手に、朱皇はそっと触れた。
その瞬間、かんざしの紅玉が強く光り、広間に淡い赤光が広がった。
「……やはりか」
朱皇の声は低く、重かった。
「そのかんざしは、ただの装飾ではない。……お前が持つべき理由がある」
「朱皇さま……?」
「怖れるな。理由はすぐにわかる」
朱皇は花の手に触れたまま離さなかった。
花は胸の奥が熱くなるのを感じた。
だが、二人のこうした関わりが、後宮全体の怒りを買わないはずもない。
昼の稽古中、また事件が起きた。
大広間で行われる礼法訓練、姫君たちが円を描くように歩く最中――。
誰かが、花の着物の裾をわざと引っかけた。
花の身体が前のめりに崩れる。
空気がざわりと揺れ、周囲の視線が集まる。
——転ぶ。
そう思った瞬間、花の頭に母の声のような響きがよぎった。
『落ちるときは、足よりも先に心を支えなさい』
瞬間、花は体をひねり、腕を伸ばし、崩れ落ちる寸前で片膝をついて姿勢を整えた。
衣は美しく波を描き、むしろ優雅でさえあった。
広間が静まり返る。
侍女長が驚愕の息を飲む。
「……見事です、花殿」
花は小さく礼をした。
姫君たちは悔しげに唇を噛む。
だが、その瞬間——。
「何事だ?」
帝が現れた。
ざわめきが広間を震わせる。
花は顔を上げられない。
朱皇は花の側へ歩み寄り、手を差し伸べた。
「よく耐えたな」
その言葉は、花の胸を強く揺らした。
しかし同時に、姫君たちの嫉妬は炎となって燃え上がる。
朱皇はその炎など意に介さない様子で、花を立たせた。
「……今後、花のそばには二人の護衛を付ける。後宮の治安が乱れている」
その言葉は明らかに、誰かの悪意を指していた。
夜、花は朱皇に呼ばれ、静かな庭で向かい合った。
「花、お前は後宮の中心に立つ。望まぬとしても、だ」
「……私なんて、ただの——」
「違う。お前は特別だ。……理由は、私にもまだわからぬが」
朱皇の瞳が揺れるのを初めて見た。
花は胸が締めつけられる。
「だが約束しよう。お前を守る。どれほど闇が迫ろうとも、私がすべてを払う」
花は息を呑む。
「朱皇さま……」
「名を呼べと言った」
「す、す……朱皇……さま?」
「ふ、まだ硬いな」
朱皇は微かに笑い、花の肩に手を置いた。
その手が伝える温度は、花の恐れを溶かし、決意を育てていく。
そして——。
後宮の奥深くで、花を陥れる策が密かに形を取り始めていた。
花はまだ知らない。
その陰謀こそが、彼女の出生の秘密に触れ、朱皇との運命をさらに大きく揺さぶることになると。
朱宮の夜は、静かに、しかし確実に、血と真実の香りを濃くしていった。
花は、己の胸の内を押し殺すように深く息を吸った。
後宮の回廊を歩くたび、周囲の視線が肌を刺すように絡みついてくる。
嫉妬、敵意、好奇、嘲笑、計算――それらが重なり合い、一歩進むたびに空気が濁るようだった。
従者として働いていた頃、向けられる視線といえば無関心か、厄介者を見るようなものばかり。
だが今は違う。
花という一個の存在が、後宮の均衡そのものを揺さぶるものとして数えられ始めているのだ。
朱皇に特別扱いされる――それだけで十分、彼女は標的となる。
彼のたった一言が、後宮中の女たちを不安と焦燥で煮立たせる。
帝にとって花が何なのか、誰もわからない。だがだからこそ、誰もが恐れていた。
宰相家の娘でも、名門貴族でもなく、どこの出なのかも明かさぬ灰かぶり。
そんな者がただ選ばれただけで序列が覆るのだとしたら――?
「……あの者が?」
「帝のあのまなざし……ありえぬ……」
「身分を偽っているに違いないわ。あの粗末な衣……」
「調べるべきでしょうね。徹底的に」
花が歩く後ろで、ささやきが黒い霧のように漂う。
彼女は耳に入らぬふりをしたが、胸の奥の痛みは拭えない。
だが、後宮が花を脅威と見なした理由はそれだけではなかった。
あの後――帝の私的な書庫へ呼び出されたことが、噂をさらに加速させたのだ。
誰一人立ち入れぬ場所に、帝が花一人を招いた。
その意味は、どれほど探らずとも想像できる。
後宮の女たちが血の気を上げるのも無理はなかった。
*
書庫での出来事を思い出すと、花の胸は熱くなり、同時にざわついた。
朱皇のあの言葉。
――「名を奪われ、身分を失っても、『花』という名だけは手放すな」
――「そのかんざしは、お前の守りだ」
優しすぎる声が、何度も脳裏に蘇る。
だが、優しさは人を惑わす。
自分は偽りの身でここへ来た。
帝の前に立つ資格など、どこにもない。
(遠ざからなければ……また誰かが傷つく)
奉公先の老婆に「行け」と言われた日。
身代わりとして宴に出されることが決まった日。
彼女の人生は勝手に動かされてきた。
だが今、後宮で動き出した陰謀の渦の中心にいるのは、他でもない彼女自身だ。
今度は、自分が誰かを巻き込む番――。
そう思うと、足がすくんだ。
「……どうすればいいの……」
一人呟いた声は、広い回廊に吸い込まれていく。
そのときだった。
「花さま……?」
控えめな声が背後から聞こえ、振り向くと、書庫で出会った女官・玲瓏が立っていた。
彼女は花より少し年上に見える。
後宮に珍しいほど静けさをまとい、必要以上に感情を見せない。
「顔色が優れません。少し、お休みになっては」
「……平気、です。少し……疲れただけで」
「疲れは、弱さではありません」
玲瓏は花の手を取るようにして言った。
「弱ってはいけないのは、この後宮そのもの。あなたは、弱ってもいい」
不思議な言葉だった。
花は思わず目を瞬いた。
玲瓏は薄く微笑むだけで、それ以上語らなかったが、彼女の瞳には同情とも忠誠とも違う、独特のものが浮かんでいた。
まるで、帝と花の間にある何かを既に知っているような――。
*
その翌日。
後宮は突然、ざわめきに包まれた。
柱廊を行き交う女官たちの足取りがいつになく急ぎ、貴妃たちが色めき立つ。
「どうしてこんな時期に……?」
「選妃の宴が終わって間もないのに……」
「わざわざ帝直筆の詔まで出されるなんて……」
花は呼び出しを受け、広場のような庭へ向かった。
そこには、後宮中の女官と妃嬪が集まっている。
皆が不安げに視線を交わし、そして中央に立つ帝の姿を見つめていた。
朱皇が静かに手を上げると、ざわめきは嘘のように止んだ。
「今日、この場に集まらせたのは他でもない」
帝の声は、かすかに冷たく響いた。
「後宮にある噂が流れていると聞いた」
花の背筋が凍る。
帝は続ける。
「名も地位も偽って宮中に入り込み、私の寵を得た者がいる――と⋯⋯」
広場が一瞬でざわめきに包まれた。
誰もが互いの顔を見合う。
だが、突き刺さる視線の半数は、花に向けられていた。
(どうしよう……)
息が詰まり、手が震え始める。
帝はゆっくりと視線を巡らせた。
ひどく冷静で、ひどく残酷に見える。
「ならば、問おう」
朱皇の視線が、集まった女官・妃嬪を一人ひとり貫く。
「この中で、自ら身分が偽りであると証明されたい者は、前へ出よ」
暴風の前触れのように、空気がぴたりと静まった。
花の胸が痛いほど鳴る。
足がすくむ。
ここで名乗り出れば、自分はすべてを失う。
奉公先の家も、ここでの立場も、命さえ危うい。
だが――。
帝がこんなことをするはずがない。
花を追い詰めるような真似を、なぜ。
そのとき。
「……出る人など、いるはずがありません」
貴妃の一人がそう言った。
「帝のご寵愛を受けたいがために、誰かの虚言が広まっただけでしょう」
「虚言、か」
朱皇は苦く笑い、視線を群衆の右端へ向けた。
そこには――。
先日、花に水を浴びせた妃がいた。
彼女は青ざめた顔で震えている。
「ひ、陛下……!わ、私は……」
「身に覚えがないのなら、震える理由はないだろう」
帝の声は冷え切っていた。
「だが、お前が“探っていた”ことは知っている。花について、彼女の出自についてな」
広場全体が息を飲む音がした。
花の心臓が跳ねた。
帝は……知っていたの?
妃は泣き崩れた。
「ち、違います!! 私はただ……!彼女の身なりが怪しいと思って、それで……!」
「怪しい、か」
朱皇は花を一瞥した。
「私の目が、偽りを見抜けぬと言うのか?」
「い、いえっ……!!そ、そんなつもりは……!」
妃の声は涙で濁っていく。
帝は彼女を見下ろし、淡々と告げた。
「お前の罪は、偽りを暴くことではない。身分の低い者を侮り、私の判断をも侮ったことだ。ゆえに、相応の処罰を与える」
妃の顔色が真っ青になった。
花は思わず震えた。
だが――次の帝の言葉は、それ以上に彼女を震わせた。
「そして、花を――二度と侮るな」
広場に満ちた空気が、がらりと変わった。
これまで灰かぶりと嘲られてきた少女の周囲が、一瞬にして強固な結界のような威圧に包まれる。
朱皇が一歩、花の方へ歩み寄った。
彼の瞳が、すぐ目の前にある。
どこまでもまっすぐに、彼女の心を見抜くように。
「花」
低く、やわらかい声が響く。
「何を恐れている?」
「……わ、私は……」
言葉が喉につかえる。
「お前を偽物だという者は、私が許さぬ」
「お前を傷つける者も、私が許さぬ」
「お前を奪う者が現れたら――世界のどこであれ、私はそれを焼き払う」
花は息を呑んだ。
朱皇は手を伸ばし、彼女のかんざしに触れた。
まるで、それが宝物であるかのように。
「これは、お前がお前である証だ。奪われることも、失われることも、もう無い」
その言葉は、花の心の奥深くに、静かに落ちていった。
(……どうして、そこまで……?)
聞きたいのに、言葉にできない。
だが、朱皇の瞳を見ていると、不思議と胸が痛くなくなった。
帝は背を向け、後宮中へ響くように声を放った。
「よいか。花は私が選んだ者だ。その目を曇らせれば、後宮そのものが崩れると思え」
その宣言は、後宮に新たな秩序を刻みつけるものだった。
同時に――陰で暗躍していた者たちの心に、危険な火をともすことにもなった。
帝がここまで庇うのなら。
花はただの灰かぶりではない。
帝の心を動かす何かを持つ、特別な存在――いや。
(……皇統に関わる秘密を、持っているのではないか?)
そんな疑念が、静かに芽を出し始めたのだ。