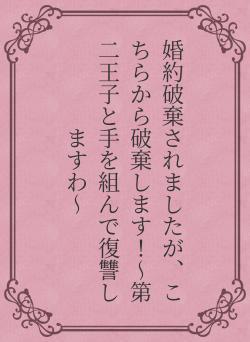夜はまだ明けない。
それでも、宮の奥では何かが音もなく崩れ始めていた。
静華の間での戦いから数刻。
花と朱皇は後宮の奥の離宮へと運ばれ、侍医たちが慌ただしく行き交っている。
朱皇の傷は深かったが、あの場で見せた強靭さのとおり、命に別状はないと告げられた。
けれども——。
花の胸の奥は、奇妙な震えで満たされていた。
恐怖ではない。
何か呼ばれているような感覚だった。
朱皇が眠りに落ちた部屋の隅で、花は膝を抱え、灯火の揺れに視線を落としていた。
律と露も近くにいるのに、その気配すら遠く感じる。
呼ばれている。
どこへ?
誰に?
その時、外の風が一瞬だけ鋭く吹き込んだ。
灯りが細く揺らぎ、影が床に流れ込むように伸びる。
胸が、きゅう、と締めつけられた。
——来い。
声がしたわけじゃない。
けれど、確かに呼びかけがあった。
花の血の底、もっと深いところで。
「……っ」
堪えきれず、花は立ち上がった。
律が気づき、急いで振り返る。
「花様?どうされました……」
露も歩み寄るが、花は首を振る。
「……ごめん、ちょっと……息を吸いたくなったの。すぐ戻るから」
「外はまだ危険です!せめて誰かを——」
「大丈夫、ひとりで行きたいの。行かなくちゃいけない気がするの」
自分でも理由にならないことを言っている。
だが、止められたら二度と戻れない気がした。
律と露は迷ったが、あの戦いを見ていた彼女らには、花の瞳の決意が普通ではないことも分かったのだろう。
二人は視線を交わし、小さく頷き、花を送り出した。
花は廊下を歩く。
足元が自然と道を選ぶ。
まるで何かに導かれているように。
ふと気づくと、後宮の北側——。
通常は宮女でも近づけぬ、古の一角へと来ていた。
そこには翠色の玉石で封じられた扉があり、ずっと昔から閉ざされたままだったはずだ。
近寄る者はいない。
好奇心で覗こうとする者すらいない。
それほど、その扉は異様な気配をまとう。
なのに——。
扉の前に、ひとりの影が立っていた。
蒼璃だった。
薄闇の中でも、その瞳の鋭さが分かる。
剣は抜かれていない。
けれど、その佇まいには戦場の気配があった。
「……やはり、来たな。花」
花は息を呑む。
「どうして……ここに」
「理由は単純だ。お前の血が、この扉を開けるからだ」
胸が痛むほど強く脈打ち、指先が冷える。
「……私の……血……?」
「そうだ。ずっと封じられてきた史書から消された血筋。帝家の中でも最も深く、危険とされた系譜。それがお前の母——紫苑の一族だ」
紫苑。
その名を聞くだけで胸の奥がひりつく。
蒼璃はゆっくりと続ける。
声は冷たいが、その奥にあるのは憎しみではない。
むしろ、真実を告げるための覚悟だった。
「朱皇兄上は知らぬ。父帝も隠した。だが……お前は帝の花などと優しく呼ばれる存在ではない。お前は本来、帝を選ぶ側の血だ」
花は理解できなかった。
いや、拒んでいたのかもしれない。
「……違う。私は……灰被りで……奉公娘で……そんな、大層な……」
「違わぬ。むしろ、お前だからこそ、あの扉が呼んでいる」
蒼璃は後ろへ一歩引いた。
扉が花に向かって、わずかに震えたのだ。
本当に呼んでいる。
花を。
蒼璃が静かに言う。
「開けろ。お前の出生を知りたくば、ここを越えるしかない。朱皇の血と、お前の血が、どんな運命を背負っているのかをな」
花は扉に手を伸ばし——触れた瞬間。
翠玉の封印がひとりでに砕け落ち、白い光が外へあふれ出した。
その光に飲み込まれながら、花は振り返る。
蒼璃が、微かに笑ったように見えた。
「行け。真実を知り、それでも兄上を選ぶのか……見届けてやる」
花は光へと吸い込まれた。
足元を失い、風のない空間を落ちていくような感覚に包まれる。
そして——。
白の殿に、ひとり立っていた。
高い天井、無数の古い巻物、万年の時を超えて閉ざされた記録の山。
その中央に、ひとつの石台があった。
花が近づくと、不思議なことに巻物がひとりでに開いた。
そこに記された名——。
「紫苑。禁裏・帝家守護の系譜」
花の胸が震える。
目の奥が熱くなる。
覚えている。
母の、あの穏やかな声。
毎晩聞かせてくれた、優しい子守歌。
あれはただの歌ではなかったのだ。
――帝家を護る、古の呪歌。
巻物の次の頁がひらりと捲れた。
そこに記された、血の系譜。
紫苑。
そして、花。
名が、確かに刻まれていた。
「……私……帝を……守るために、生まれた……?」
答える者はいない。
けれど胸の奥が熱を帯び、光が脈打つ。
目を閉じると、朱皇の姿が浮かんだ。
あの人が、倒れた瞬間。
血が滲んだ衣。
それでも花を見つめた、優しい瞳。
守りたい——。
その気持ちは、ずっと前からあった。
でも今、その想いは血に刻まれた本能のように深く響いている。
「私は……朱皇陛下を……守りたい」
「それが……私の、選ぶ道……」
石台が光を放つ。
巻物が全ての頁を開き、白い布のような光が花の胸に吸い込まれていく。
花は瞳を開き、強く息を吸う。
縛られていた何かが、ほどけたような感覚。
けれど、重い使命の影も感じる。
——戻らなければ。
朱皇のもとへ。
そう思った瞬間、白い殿が淡く揺れ、花の身体は元の世界へと弾き出された。
光が収まった時、花は扉の前に立っていた。
蒼璃が静かに問う。
「真実を得た顔だな。花、選んだのか?」
花は迷いなく頷く。
「はい……私は……陛下を守るために生まれました。なら、私はこの力を……陛下のために使います」
蒼璃の瞳がわずかに揺れる。
彼は花の答えが気に入らないはずなのに、どこか安堵したようでもあった。
「……愚かにも、強い。兄上が……惹かれるわけだ」
その言葉に花は息をのむ。
蒼璃は背を向け、低く言い残した。
「戻れ。兄上は……お前の名を呼び続けている」
花は走った。
朱皇のもとへ。
自分の選んだ場所へ。
帝の許嫁としてではない。
帝を護る者として。
朱皇の腹を貫いた刀は、柄の奥まで深く沈み込んでいた。
その一撃は、互角を保っていた戦いの均衡を一気に崩し、朱皇の身体からは温かい赤が静かに流れ落ちてゆく。
ただ、朱皇は叫ばなかった。苦しみに顔を歪めることすらせず、相手に一瞬の勝利の味を覚えさせることさえ拒むように、ただまっすぐ立ち続けた。
刀を握る敵、黒縄の呼吸の使い手。その目には勝利の色が宿りかけていたが、朱皇の沈黙がその感情を鈍らせる。
「……倒れろよ。腹を貫かれて立つ奴なんざ、見たことねぇんだよ」
羅刹は吐き捨てるように言いながら、刀を引き抜こうとした――が。
朱皇の左手が、ぎり、と刀の刃を掴んだ。血が流れるのも構わず、朱皇はその刀を自らの腹へ押し込ませないよう押さえ込んでいた。
羅刹の指先に、微かな震えが走る。
「……人間じゃねぇのか、お前……」
朱皇はようやく口を開いた。
「……人間だよ。ただ――守りたいものを持ってるだけだ」
その声音は、かすれていて、それでも不思議と凛としていた。
刀を握ったまま、朱皇は一歩踏み込む。
身体の奥を灼く痛みがあった。視界がぼやけかける。しかし、止まれなかった。
――花を、守る。
それだけが、倒れない理由だった。
羅刹は嘲るように笑ったが、その笑みには焦りが混じっていた。
「まだ戦えるつもりか……!貫かれてるんだぞ!」
朱皇は返さない。ただ足を踏み出し続ける。
その姿は、もはや闘技の域ではなかった。
静かで、まるで祈りのような歩みだった。
羅刹は攻撃を続ける。しかし朱皇はかわす。
腹を押さえた片手で、もう片方の手だけで、しなやかに、そして鋭く。
羅刹の攻撃は当たりそうで当たらない。
戦いの場の空気が変わり始めていた。
まるで朱皇の意志が空間ごとねじ伏せてゆくように、風が止まり、時間さえ引き延ばされているように感じられる。
「やめろよ……なんなんだよ……お前……」
朱皇が歩み寄るたびに、羅刹は後退した。
怒りも、恐怖も、混ざっている。
その瞳に映る朱皇は、人ではなく揺るぎない灼光そのものだった。
腹の傷からは、赤が流れ続ける。
命が刻まれるように、足元に点々と滴る。
それでも朱皇の眼は揺れなかった。
――花の泣く顔を、二度と見たくない。
その一念だけで、朱皇は戦っていた。
羅刹は奥歯を噛み、残る力を全て刀に込めた。
「なら――これで終わりだァ!」
全身をひねり、黒縄の呼吸の奥義を叩き込む。
その軌跡は闇の縄のように蠢き、触れれば生きた肉を断つ確実な刃。
だが朱皇は、ほんのわずか……指先ほどの幅で横にずれた。
息をしているのかもわからない動きだった。
痛みと出血で限界を超えているはずの身体が、まるで幽霊のように軽く動いた。
羅刹の目が絶望で見開かれた。
「な……っ……!」
朱皇がようやく口を開く。
「……これで終わりだ。花が待ってる」
次の瞬間、朱皇は刀を抜かれた腹から溢れた赤を無視し、一気に踏み込んだ。
拳が、まっすぐ羅刹の胸へ突き刺さる。
轟音はない。
ただ、羅刹の身体が大きくのけぞり、壁へ激突し、崩れ落ちた。
立ち上がれない。
決着だった。
勝利の余韻を感じる暇もなく、朱皇は膝をついた。
腹の傷から血が溢れ続け、息が浅く、指先の震えが止まらない。
そこへ駆け寄ってくる足音――花だった。
「朱皇っ……!!」
花は勢いよく膝をつき、朱皇の肩を抱いた。
その手が震え、瞳から涙があふれそうになっている。
「なんで……そんな無茶して……!死にますよ……」
朱皇はかすかに笑った。
「……死ねない。花との約束、まだ守れてない」
「約束……?」
「……もう二度と泣かせないって」
花は堪えきれず、朱皇の胸に顔をうずめた。
そして震える声で言う。
「泣くよ……!あなたが傷ついたら……泣くに決まってるじゃないですか……!」
朱皇は、花の髪をゆっくり撫でた。
「……ごめん。でも、守りたかったんだ。俺は……花が見てる未来に、ちゃんと立っていたい」
その言葉に、花は顔を上げる。
朱皇の瞳には、痛みよりも強く、揺るぎない光が宿っていた。
「朱皇様……」
「花が、俺の救いだから」
花の頬を、一筋の涙が伝う。
けれどその表情は、泣き顔の中に確かな笑みも宿していた。
「だったら……生きてよ。必ず。 私を守りたいって思うなら、私にも……あなたを守らせて」
朱皇は頷く。
「……これからは、二人で生きる」
戦いの最後の音が、世界から消えた。
風が止まり、土埃がゆっくりと落ちていく。
朱皇の拳に残っているのは、わずかな痛みだけ。
対峙していた羅刹は、壁際で完全に沈黙し、動く気配は一切ない。
すべての戦いが……ようやく終わったのだ。
朱皇は大きく息を吐き、腹に手を当てる。
刀が貫いた部分はまだ赤く濡れていたが、彼の体は信じられないほど安定していた。
痛む。しかし、折れない。
花との約束が、そのまま身体を支えているようだった。
地面には、夜の激闘の名残が点々と横たわっている。
焦げた土、ひび割れた地面、斬り口、無数の傷跡。
だが、さっきまで暴れていた影の一つとして動くものはもうない。
長い夜だった。
あまりに長すぎて、今がどこにいるのか、時間の感覚すら失いかけていた。
朱皇は、静寂に満ちた大地の真ん中で、ゆっくり目を閉じる。
——終わったんだ。
その事実だけが、胸の奥を温かく満たしていく。
花の肩は震えていた。
泣いているのか、安心して力が抜けたのか……多分どちらもだ。
東の空が、わずかに薄い青を帯びていく。
まだ夜の名残は濃いのに、確かに朝が来ようとしていた。
朱皇と花はゆっくり立ち上がった。
羅刹の姿も、倒れたものたちの姿も、もう二度と動き出すことはない。
この地で繰り広げられた激闘のすべては、夜の底へ沈んでいき、朝だけが静かに訪れようとしている。
朱皇は花の手を取った。
その指は温かく、柔らかく、震えていたが……強かった。
花が囁く。
「……朱皇様。こんな場所に、あなたを置いておきたくない」
「……ああ。行こう。これからは……戦いじゃなくて、生きる方へ」
二人は並んで歩き始める。
ゆっくり、確かに、一歩ずつ。
夜の名残を踏みしめ、朝の光を目指して。
歩くたびに、戦いの痕跡が背後へ遠ざかっていく。
轟く叫びも、振るわれた刀の軌跡も、拳の重みも、すべてが朝の手前で消えていった。
朱皇は花の横顔を見る。
花も朱皇を見返し、柔らかく微笑んだ。
それだけで、胸が満たされる。
戦いの痛みも、夜の恐怖も、すべてが今ここにいるという実感に変わっていく。
東の空が静かに明るくなる。
淡い金色が空へ伸び、影だった世界を溶かしていった。
「なぁ、花」
「はい?」
「……生きててよかった。一緒に、この朝を見られてよかった」
花は朱皇の手をぎゅっと握る。
「うん。私も……心からそう思う」
夜が終わった。
朱皇の長い戦いも終わった。
守りたいすべてを抱えたまま、朝へ進む道がはっきりと見える。
もう誰も、二人を傷つけるものはいない。
もう誰も、朱皇の光を奪えない。
そして――。
静かな朝の中、朱皇と花はゆっくりと歩き続けた。
まるで物語が静かに幕を閉じていくのを知っているかのように。
もう次の戦いなど存在しないと、世界が優しく教えてくれるかのように。
__番外編__
戦いの夜が明けて数日。
朝の光は柔らかく、風はやさしく、宮中はようやく落ち着きを取り戻していた。
だが二人には、少しだけ慣れない時間が訪れていた。
それは、何の敵も、陰謀も、危険も存在しない自由な朝。
朱皇にとっては久しく味わったことのないものだったし、花にとっても、奉公でも後宮のしがらみでもない、ただの朝というのは不思議なくらい静かだった。
「朱皇さま、今日は……本当に、お休みでいいのですか?」
花が控えめに確認すると、朱皇は苦笑した。
「俺が休むと言ったら、周囲が勝手に動いてしまったんだ。これ以上倒れられては困るとか、朝まで戦う帝は初めて見ただとか……」
花は思わず笑ってしまった。
「まぁ、あれだけ戦って……腹まで貫かれて……それで歩いて帰ってきたら、驚かない人はいませんよ」
「だからこそ、今日は俺も休んでくれと言われた。なので、花。今日は一日、お前と過ごす」
「えっ……そ、そんな、私なんかで……」
「私なんかは禁止だ」
朱皇は花の額に軽く指を置いた。
「お前は俺が選んだ。理由が欲しいなら、いくらでも言ってやる」
花は顔を真っ赤にしてうつむく。
その姿すらいとおしいと思ってしまう自分が、朱皇には少しおかしく思えた。
その日の宮中は、珍しいほど静かだった。
朱皇と花が歩けば、侍女たちは遠巻きに道を開け、文官たちは息をひそめ、まるで二人の邪魔だけはするまいと言わんばかりに距離を取った。
「なんだか……気を遣わせてしまってませんか?」
「気を遣わせているんじゃない。俺がお前と過ごすと言ったから、皆が勝手にそっとしてるだけだ」
「そんなことまで……」
「帝だからな。利点くらいは使わないと」
そう言って朱皇は肩をすくめたが、 花にはそれが少し気恥ずかしい優しさに見えた。
ふと、庭の向こうで、春の花が風に揺れた。
「……あ」
「どうした?」
「この花、母が好きだったんです。香りがやわらかくて……それで、かんざしの模様にもなっていて……」
「紫苑の花か」
「はい。だから、なんだか懐かしくて」
朱皇はその花を一輪折り、花の髪にそっと挿した。
「似合う」
「えっ……そ、そんな……」
「本当だよ。お前は、自然の花に負けないくらい……綺麗だ」
花の頬がまた赤く染まる。
「朱皇さまは、たまに……ずるいです」
「お前が照れる顔を見るのが好きなだけだ」
二人はそのまま庭をゆっくり歩いた。
戦いも、血の気も、憎しみも、陰謀もない時間。
ただ、穏やかで、静かで、少し照れくさいだけの空気が流れていく。
「そういえば、花」
「はい?」
「以前、お前を初めて見たとき」
花は歩みを止める。
朱皇はその瞳をまっすぐ見つめた。
「あのときのあんな目で見るなという言葉……覚えてるか?」
「……はい。怒られると思って、心臓が止まりそうでした」
「怒ったんじゃない。俺は……あの目に、救われたんだ」
「救われた……?」
「あの夜、后選びの宴。周囲の姫君は皆、俺に縋りつくように視線を向けていた。だが、お前だけは……『怖いけれど、ちゃんと見ます』という目をしていた」
「そんなつもりじゃ……」
「わかってる。でもあの視線が、俺にはとてつもなく嬉しかった」
花は胸に手を当てる。
心臓が熱く、くすぐったい。
「花。俺は帝である前に……一人の男だ。誰かに真っ直ぐ見つめられたかった。お前が、それをしてくれた」
「朱皇さま……」
「だから、今こうしてお前と歩けることが……嬉しい」
花は言葉を失い、ただ朱皇の袖をそっと掴んだ。
掴んだまま離せなかった。
「花、一つ聞いていいか?」
「はい……?」
「戦が終わった今。これから先、何がしたい?」
花は少し考えた。
帝と過ごす未来など、想像したことすらなかったからだ。
「……誰かの役に立ちたいです。灰をかぶっていた頃の私でも、誰かの支えになれるなら……」
「それでいい」
「え……?」
「お前は、そういう人だ。だから、俺は……お前を手放したくない」
花は息を呑んだ。
朱皇は手を伸ばし、彼女の指をそっと絡める。
「花。お前が許すなら……これからも、俺の隣にいてほしい」
花は静かに頷いた。
涙が溢れたが、それは悲しみではなく、温かさからだった。
「……はい。私でよければ、いつまでも」
朱皇はその手を引き、庭の出口へ歩き出す。
「どこへ……?」
「散歩の続きだ。朝日がきれいな場所がある。お前に見せたい」
「そんなところが……」
「今日が自由な一日の初めての朝だ。なら、お前と朝日を見ないと始まらないだろう?」
花は微笑んだ。
朱皇も、その微笑みに安心したように笑う。
戦いの夜を越えて、
二人はようやく、本当の朝を迎える。
その朝は、戦の匂いも陰謀の影もない、ただ穏やかで、風がやさしくて、人が人として息をできる⋯⋯そんな朝だった。
朱皇は花の手を握ったまま歩き、花もまた、その手を握り返す。
どちらも離さない。
離れる必要がなかったから。
夜が終わり、朝がある。
二人の物語は大団円を迎えたけれど、
⋯⋯⋯⋯この普通の一日からまた、ゆっくりと続いていく。
完
それでも、宮の奥では何かが音もなく崩れ始めていた。
静華の間での戦いから数刻。
花と朱皇は後宮の奥の離宮へと運ばれ、侍医たちが慌ただしく行き交っている。
朱皇の傷は深かったが、あの場で見せた強靭さのとおり、命に別状はないと告げられた。
けれども——。
花の胸の奥は、奇妙な震えで満たされていた。
恐怖ではない。
何か呼ばれているような感覚だった。
朱皇が眠りに落ちた部屋の隅で、花は膝を抱え、灯火の揺れに視線を落としていた。
律と露も近くにいるのに、その気配すら遠く感じる。
呼ばれている。
どこへ?
誰に?
その時、外の風が一瞬だけ鋭く吹き込んだ。
灯りが細く揺らぎ、影が床に流れ込むように伸びる。
胸が、きゅう、と締めつけられた。
——来い。
声がしたわけじゃない。
けれど、確かに呼びかけがあった。
花の血の底、もっと深いところで。
「……っ」
堪えきれず、花は立ち上がった。
律が気づき、急いで振り返る。
「花様?どうされました……」
露も歩み寄るが、花は首を振る。
「……ごめん、ちょっと……息を吸いたくなったの。すぐ戻るから」
「外はまだ危険です!せめて誰かを——」
「大丈夫、ひとりで行きたいの。行かなくちゃいけない気がするの」
自分でも理由にならないことを言っている。
だが、止められたら二度と戻れない気がした。
律と露は迷ったが、あの戦いを見ていた彼女らには、花の瞳の決意が普通ではないことも分かったのだろう。
二人は視線を交わし、小さく頷き、花を送り出した。
花は廊下を歩く。
足元が自然と道を選ぶ。
まるで何かに導かれているように。
ふと気づくと、後宮の北側——。
通常は宮女でも近づけぬ、古の一角へと来ていた。
そこには翠色の玉石で封じられた扉があり、ずっと昔から閉ざされたままだったはずだ。
近寄る者はいない。
好奇心で覗こうとする者すらいない。
それほど、その扉は異様な気配をまとう。
なのに——。
扉の前に、ひとりの影が立っていた。
蒼璃だった。
薄闇の中でも、その瞳の鋭さが分かる。
剣は抜かれていない。
けれど、その佇まいには戦場の気配があった。
「……やはり、来たな。花」
花は息を呑む。
「どうして……ここに」
「理由は単純だ。お前の血が、この扉を開けるからだ」
胸が痛むほど強く脈打ち、指先が冷える。
「……私の……血……?」
「そうだ。ずっと封じられてきた史書から消された血筋。帝家の中でも最も深く、危険とされた系譜。それがお前の母——紫苑の一族だ」
紫苑。
その名を聞くだけで胸の奥がひりつく。
蒼璃はゆっくりと続ける。
声は冷たいが、その奥にあるのは憎しみではない。
むしろ、真実を告げるための覚悟だった。
「朱皇兄上は知らぬ。父帝も隠した。だが……お前は帝の花などと優しく呼ばれる存在ではない。お前は本来、帝を選ぶ側の血だ」
花は理解できなかった。
いや、拒んでいたのかもしれない。
「……違う。私は……灰被りで……奉公娘で……そんな、大層な……」
「違わぬ。むしろ、お前だからこそ、あの扉が呼んでいる」
蒼璃は後ろへ一歩引いた。
扉が花に向かって、わずかに震えたのだ。
本当に呼んでいる。
花を。
蒼璃が静かに言う。
「開けろ。お前の出生を知りたくば、ここを越えるしかない。朱皇の血と、お前の血が、どんな運命を背負っているのかをな」
花は扉に手を伸ばし——触れた瞬間。
翠玉の封印がひとりでに砕け落ち、白い光が外へあふれ出した。
その光に飲み込まれながら、花は振り返る。
蒼璃が、微かに笑ったように見えた。
「行け。真実を知り、それでも兄上を選ぶのか……見届けてやる」
花は光へと吸い込まれた。
足元を失い、風のない空間を落ちていくような感覚に包まれる。
そして——。
白の殿に、ひとり立っていた。
高い天井、無数の古い巻物、万年の時を超えて閉ざされた記録の山。
その中央に、ひとつの石台があった。
花が近づくと、不思議なことに巻物がひとりでに開いた。
そこに記された名——。
「紫苑。禁裏・帝家守護の系譜」
花の胸が震える。
目の奥が熱くなる。
覚えている。
母の、あの穏やかな声。
毎晩聞かせてくれた、優しい子守歌。
あれはただの歌ではなかったのだ。
――帝家を護る、古の呪歌。
巻物の次の頁がひらりと捲れた。
そこに記された、血の系譜。
紫苑。
そして、花。
名が、確かに刻まれていた。
「……私……帝を……守るために、生まれた……?」
答える者はいない。
けれど胸の奥が熱を帯び、光が脈打つ。
目を閉じると、朱皇の姿が浮かんだ。
あの人が、倒れた瞬間。
血が滲んだ衣。
それでも花を見つめた、優しい瞳。
守りたい——。
その気持ちは、ずっと前からあった。
でも今、その想いは血に刻まれた本能のように深く響いている。
「私は……朱皇陛下を……守りたい」
「それが……私の、選ぶ道……」
石台が光を放つ。
巻物が全ての頁を開き、白い布のような光が花の胸に吸い込まれていく。
花は瞳を開き、強く息を吸う。
縛られていた何かが、ほどけたような感覚。
けれど、重い使命の影も感じる。
——戻らなければ。
朱皇のもとへ。
そう思った瞬間、白い殿が淡く揺れ、花の身体は元の世界へと弾き出された。
光が収まった時、花は扉の前に立っていた。
蒼璃が静かに問う。
「真実を得た顔だな。花、選んだのか?」
花は迷いなく頷く。
「はい……私は……陛下を守るために生まれました。なら、私はこの力を……陛下のために使います」
蒼璃の瞳がわずかに揺れる。
彼は花の答えが気に入らないはずなのに、どこか安堵したようでもあった。
「……愚かにも、強い。兄上が……惹かれるわけだ」
その言葉に花は息をのむ。
蒼璃は背を向け、低く言い残した。
「戻れ。兄上は……お前の名を呼び続けている」
花は走った。
朱皇のもとへ。
自分の選んだ場所へ。
帝の許嫁としてではない。
帝を護る者として。
朱皇の腹を貫いた刀は、柄の奥まで深く沈み込んでいた。
その一撃は、互角を保っていた戦いの均衡を一気に崩し、朱皇の身体からは温かい赤が静かに流れ落ちてゆく。
ただ、朱皇は叫ばなかった。苦しみに顔を歪めることすらせず、相手に一瞬の勝利の味を覚えさせることさえ拒むように、ただまっすぐ立ち続けた。
刀を握る敵、黒縄の呼吸の使い手。その目には勝利の色が宿りかけていたが、朱皇の沈黙がその感情を鈍らせる。
「……倒れろよ。腹を貫かれて立つ奴なんざ、見たことねぇんだよ」
羅刹は吐き捨てるように言いながら、刀を引き抜こうとした――が。
朱皇の左手が、ぎり、と刀の刃を掴んだ。血が流れるのも構わず、朱皇はその刀を自らの腹へ押し込ませないよう押さえ込んでいた。
羅刹の指先に、微かな震えが走る。
「……人間じゃねぇのか、お前……」
朱皇はようやく口を開いた。
「……人間だよ。ただ――守りたいものを持ってるだけだ」
その声音は、かすれていて、それでも不思議と凛としていた。
刀を握ったまま、朱皇は一歩踏み込む。
身体の奥を灼く痛みがあった。視界がぼやけかける。しかし、止まれなかった。
――花を、守る。
それだけが、倒れない理由だった。
羅刹は嘲るように笑ったが、その笑みには焦りが混じっていた。
「まだ戦えるつもりか……!貫かれてるんだぞ!」
朱皇は返さない。ただ足を踏み出し続ける。
その姿は、もはや闘技の域ではなかった。
静かで、まるで祈りのような歩みだった。
羅刹は攻撃を続ける。しかし朱皇はかわす。
腹を押さえた片手で、もう片方の手だけで、しなやかに、そして鋭く。
羅刹の攻撃は当たりそうで当たらない。
戦いの場の空気が変わり始めていた。
まるで朱皇の意志が空間ごとねじ伏せてゆくように、風が止まり、時間さえ引き延ばされているように感じられる。
「やめろよ……なんなんだよ……お前……」
朱皇が歩み寄るたびに、羅刹は後退した。
怒りも、恐怖も、混ざっている。
その瞳に映る朱皇は、人ではなく揺るぎない灼光そのものだった。
腹の傷からは、赤が流れ続ける。
命が刻まれるように、足元に点々と滴る。
それでも朱皇の眼は揺れなかった。
――花の泣く顔を、二度と見たくない。
その一念だけで、朱皇は戦っていた。
羅刹は奥歯を噛み、残る力を全て刀に込めた。
「なら――これで終わりだァ!」
全身をひねり、黒縄の呼吸の奥義を叩き込む。
その軌跡は闇の縄のように蠢き、触れれば生きた肉を断つ確実な刃。
だが朱皇は、ほんのわずか……指先ほどの幅で横にずれた。
息をしているのかもわからない動きだった。
痛みと出血で限界を超えているはずの身体が、まるで幽霊のように軽く動いた。
羅刹の目が絶望で見開かれた。
「な……っ……!」
朱皇がようやく口を開く。
「……これで終わりだ。花が待ってる」
次の瞬間、朱皇は刀を抜かれた腹から溢れた赤を無視し、一気に踏み込んだ。
拳が、まっすぐ羅刹の胸へ突き刺さる。
轟音はない。
ただ、羅刹の身体が大きくのけぞり、壁へ激突し、崩れ落ちた。
立ち上がれない。
決着だった。
勝利の余韻を感じる暇もなく、朱皇は膝をついた。
腹の傷から血が溢れ続け、息が浅く、指先の震えが止まらない。
そこへ駆け寄ってくる足音――花だった。
「朱皇っ……!!」
花は勢いよく膝をつき、朱皇の肩を抱いた。
その手が震え、瞳から涙があふれそうになっている。
「なんで……そんな無茶して……!死にますよ……」
朱皇はかすかに笑った。
「……死ねない。花との約束、まだ守れてない」
「約束……?」
「……もう二度と泣かせないって」
花は堪えきれず、朱皇の胸に顔をうずめた。
そして震える声で言う。
「泣くよ……!あなたが傷ついたら……泣くに決まってるじゃないですか……!」
朱皇は、花の髪をゆっくり撫でた。
「……ごめん。でも、守りたかったんだ。俺は……花が見てる未来に、ちゃんと立っていたい」
その言葉に、花は顔を上げる。
朱皇の瞳には、痛みよりも強く、揺るぎない光が宿っていた。
「朱皇様……」
「花が、俺の救いだから」
花の頬を、一筋の涙が伝う。
けれどその表情は、泣き顔の中に確かな笑みも宿していた。
「だったら……生きてよ。必ず。 私を守りたいって思うなら、私にも……あなたを守らせて」
朱皇は頷く。
「……これからは、二人で生きる」
戦いの最後の音が、世界から消えた。
風が止まり、土埃がゆっくりと落ちていく。
朱皇の拳に残っているのは、わずかな痛みだけ。
対峙していた羅刹は、壁際で完全に沈黙し、動く気配は一切ない。
すべての戦いが……ようやく終わったのだ。
朱皇は大きく息を吐き、腹に手を当てる。
刀が貫いた部分はまだ赤く濡れていたが、彼の体は信じられないほど安定していた。
痛む。しかし、折れない。
花との約束が、そのまま身体を支えているようだった。
地面には、夜の激闘の名残が点々と横たわっている。
焦げた土、ひび割れた地面、斬り口、無数の傷跡。
だが、さっきまで暴れていた影の一つとして動くものはもうない。
長い夜だった。
あまりに長すぎて、今がどこにいるのか、時間の感覚すら失いかけていた。
朱皇は、静寂に満ちた大地の真ん中で、ゆっくり目を閉じる。
——終わったんだ。
その事実だけが、胸の奥を温かく満たしていく。
花の肩は震えていた。
泣いているのか、安心して力が抜けたのか……多分どちらもだ。
東の空が、わずかに薄い青を帯びていく。
まだ夜の名残は濃いのに、確かに朝が来ようとしていた。
朱皇と花はゆっくり立ち上がった。
羅刹の姿も、倒れたものたちの姿も、もう二度と動き出すことはない。
この地で繰り広げられた激闘のすべては、夜の底へ沈んでいき、朝だけが静かに訪れようとしている。
朱皇は花の手を取った。
その指は温かく、柔らかく、震えていたが……強かった。
花が囁く。
「……朱皇様。こんな場所に、あなたを置いておきたくない」
「……ああ。行こう。これからは……戦いじゃなくて、生きる方へ」
二人は並んで歩き始める。
ゆっくり、確かに、一歩ずつ。
夜の名残を踏みしめ、朝の光を目指して。
歩くたびに、戦いの痕跡が背後へ遠ざかっていく。
轟く叫びも、振るわれた刀の軌跡も、拳の重みも、すべてが朝の手前で消えていった。
朱皇は花の横顔を見る。
花も朱皇を見返し、柔らかく微笑んだ。
それだけで、胸が満たされる。
戦いの痛みも、夜の恐怖も、すべてが今ここにいるという実感に変わっていく。
東の空が静かに明るくなる。
淡い金色が空へ伸び、影だった世界を溶かしていった。
「なぁ、花」
「はい?」
「……生きててよかった。一緒に、この朝を見られてよかった」
花は朱皇の手をぎゅっと握る。
「うん。私も……心からそう思う」
夜が終わった。
朱皇の長い戦いも終わった。
守りたいすべてを抱えたまま、朝へ進む道がはっきりと見える。
もう誰も、二人を傷つけるものはいない。
もう誰も、朱皇の光を奪えない。
そして――。
静かな朝の中、朱皇と花はゆっくりと歩き続けた。
まるで物語が静かに幕を閉じていくのを知っているかのように。
もう次の戦いなど存在しないと、世界が優しく教えてくれるかのように。
__番外編__
戦いの夜が明けて数日。
朝の光は柔らかく、風はやさしく、宮中はようやく落ち着きを取り戻していた。
だが二人には、少しだけ慣れない時間が訪れていた。
それは、何の敵も、陰謀も、危険も存在しない自由な朝。
朱皇にとっては久しく味わったことのないものだったし、花にとっても、奉公でも後宮のしがらみでもない、ただの朝というのは不思議なくらい静かだった。
「朱皇さま、今日は……本当に、お休みでいいのですか?」
花が控えめに確認すると、朱皇は苦笑した。
「俺が休むと言ったら、周囲が勝手に動いてしまったんだ。これ以上倒れられては困るとか、朝まで戦う帝は初めて見ただとか……」
花は思わず笑ってしまった。
「まぁ、あれだけ戦って……腹まで貫かれて……それで歩いて帰ってきたら、驚かない人はいませんよ」
「だからこそ、今日は俺も休んでくれと言われた。なので、花。今日は一日、お前と過ごす」
「えっ……そ、そんな、私なんかで……」
「私なんかは禁止だ」
朱皇は花の額に軽く指を置いた。
「お前は俺が選んだ。理由が欲しいなら、いくらでも言ってやる」
花は顔を真っ赤にしてうつむく。
その姿すらいとおしいと思ってしまう自分が、朱皇には少しおかしく思えた。
その日の宮中は、珍しいほど静かだった。
朱皇と花が歩けば、侍女たちは遠巻きに道を開け、文官たちは息をひそめ、まるで二人の邪魔だけはするまいと言わんばかりに距離を取った。
「なんだか……気を遣わせてしまってませんか?」
「気を遣わせているんじゃない。俺がお前と過ごすと言ったから、皆が勝手にそっとしてるだけだ」
「そんなことまで……」
「帝だからな。利点くらいは使わないと」
そう言って朱皇は肩をすくめたが、 花にはそれが少し気恥ずかしい優しさに見えた。
ふと、庭の向こうで、春の花が風に揺れた。
「……あ」
「どうした?」
「この花、母が好きだったんです。香りがやわらかくて……それで、かんざしの模様にもなっていて……」
「紫苑の花か」
「はい。だから、なんだか懐かしくて」
朱皇はその花を一輪折り、花の髪にそっと挿した。
「似合う」
「えっ……そ、そんな……」
「本当だよ。お前は、自然の花に負けないくらい……綺麗だ」
花の頬がまた赤く染まる。
「朱皇さまは、たまに……ずるいです」
「お前が照れる顔を見るのが好きなだけだ」
二人はそのまま庭をゆっくり歩いた。
戦いも、血の気も、憎しみも、陰謀もない時間。
ただ、穏やかで、静かで、少し照れくさいだけの空気が流れていく。
「そういえば、花」
「はい?」
「以前、お前を初めて見たとき」
花は歩みを止める。
朱皇はその瞳をまっすぐ見つめた。
「あのときのあんな目で見るなという言葉……覚えてるか?」
「……はい。怒られると思って、心臓が止まりそうでした」
「怒ったんじゃない。俺は……あの目に、救われたんだ」
「救われた……?」
「あの夜、后選びの宴。周囲の姫君は皆、俺に縋りつくように視線を向けていた。だが、お前だけは……『怖いけれど、ちゃんと見ます』という目をしていた」
「そんなつもりじゃ……」
「わかってる。でもあの視線が、俺にはとてつもなく嬉しかった」
花は胸に手を当てる。
心臓が熱く、くすぐったい。
「花。俺は帝である前に……一人の男だ。誰かに真っ直ぐ見つめられたかった。お前が、それをしてくれた」
「朱皇さま……」
「だから、今こうしてお前と歩けることが……嬉しい」
花は言葉を失い、ただ朱皇の袖をそっと掴んだ。
掴んだまま離せなかった。
「花、一つ聞いていいか?」
「はい……?」
「戦が終わった今。これから先、何がしたい?」
花は少し考えた。
帝と過ごす未来など、想像したことすらなかったからだ。
「……誰かの役に立ちたいです。灰をかぶっていた頃の私でも、誰かの支えになれるなら……」
「それでいい」
「え……?」
「お前は、そういう人だ。だから、俺は……お前を手放したくない」
花は息を呑んだ。
朱皇は手を伸ばし、彼女の指をそっと絡める。
「花。お前が許すなら……これからも、俺の隣にいてほしい」
花は静かに頷いた。
涙が溢れたが、それは悲しみではなく、温かさからだった。
「……はい。私でよければ、いつまでも」
朱皇はその手を引き、庭の出口へ歩き出す。
「どこへ……?」
「散歩の続きだ。朝日がきれいな場所がある。お前に見せたい」
「そんなところが……」
「今日が自由な一日の初めての朝だ。なら、お前と朝日を見ないと始まらないだろう?」
花は微笑んだ。
朱皇も、その微笑みに安心したように笑う。
戦いの夜を越えて、
二人はようやく、本当の朝を迎える。
その朝は、戦の匂いも陰謀の影もない、ただ穏やかで、風がやさしくて、人が人として息をできる⋯⋯そんな朝だった。
朱皇は花の手を握ったまま歩き、花もまた、その手を握り返す。
どちらも離さない。
離れる必要がなかったから。
夜が終わり、朝がある。
二人の物語は大団円を迎えたけれど、
⋯⋯⋯⋯この普通の一日からまた、ゆっくりと続いていく。
完