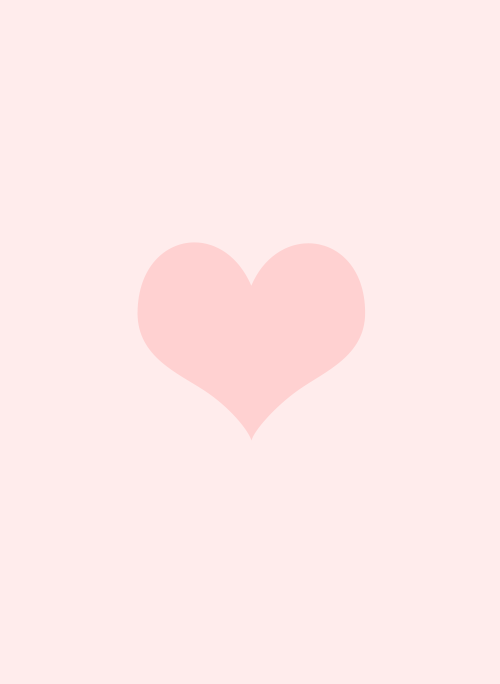雨が降り始めたのは、仕事帰りのバス停に着いた瞬間だった。
細かい雨粒が街灯に照らされ、糸みたいに落ちていく。
折りたたみ傘を出す気にもなれなくて、私はただぼんやりと空を見上げた。
湿った風に乗って、どこか懐かしい匂いがした。
夏の終わりの、あの時の匂い。
胸の奥が、何年ぶりかにじくりと痛む。
こんな感覚、もうとっくに忘れたと思っていたのに。
私は左手の薬指に視線を落とす。
光沢を抑えた細い指輪。
温かくて、優しい人と一緒に選んだ、大切な証。
なのに、
“違う誰か”の名前が、ゆっくりと、じわりと心の奥に浮かび上がる。
――会いたい。
――でも、会いたくない。
そんな矛盾が、胸の中でずっとくすぶっていた。
ふと、
バス停の向こう側に、人影がひとつ。
傘も差さず、街灯の下で立ち止まっている。
背の高さ、姿勢、首の傾け方。
全部、忘れたはずなのに、忘れられなかった形。
心臓が、ひとつ大きく跳ねた。
まさか。
こんな偶然、あるはずがない。
そう思うのに、目が離せなかった。
その人影がゆっくりとこちらを向く。
街灯の光が、彼の横顔を薄く照らす。
息が止まった。
間違いようがなかった。
私が初めて“恋”というものを知って、
そして初めて“失う痛み”を覚えた相手。
あの夏に離れたきり、
一度も会わなかった人。
…いや、会わないようにしていた人。
彼は少しだけ驚いたように目を細め、
でもすぐに、懐かしさを隠すように微笑んだ。
「……久しぶりだね」
その声を聞いた瞬間、
時間が、恐ろしいほど静かに巻き戻った。
高校の渡り廊下も、夜のバス停も、
笑った顔も、泣きそうな横顔も、
全部一気に胸に流れ込んでくる。
こんな再会なんて、望んでなかったはずなのに。
彼の左手にも、指輪が光っていた。
胸の奥が、ずしん、と沈む。
それでも――
それでも、どうしてか呼吸が楽になる。
「……うん。久しぶり」
やっとの思いで返すと、彼はふっと目を伏せた。
その表情が、何年経っても変わらなくて、
ほんの少しだけ優しすぎて、
涙が出そうになる。
あの頃みたいに、
二人の間に言葉はいらなかった。
ただ、雨の音だけが静かに降り続ける。
ほんの一瞬、
指輪の冷たさよりも、
心の奥に残った彼の温度のほうが強くなる。
――再会なんて、しないほうがよかった。
――それでも、会えてよかった。
相反する気持ちが胸の中で交差し、
私はただ雨に濡れながら立ち尽くす。
過去でもなく、未来でもなく、
今だけが、二人をそっと繋ぎとめていた。
そんな、
“終わった恋”の始まりみたいな夜だった。
細かい雨粒が街灯に照らされ、糸みたいに落ちていく。
折りたたみ傘を出す気にもなれなくて、私はただぼんやりと空を見上げた。
湿った風に乗って、どこか懐かしい匂いがした。
夏の終わりの、あの時の匂い。
胸の奥が、何年ぶりかにじくりと痛む。
こんな感覚、もうとっくに忘れたと思っていたのに。
私は左手の薬指に視線を落とす。
光沢を抑えた細い指輪。
温かくて、優しい人と一緒に選んだ、大切な証。
なのに、
“違う誰か”の名前が、ゆっくりと、じわりと心の奥に浮かび上がる。
――会いたい。
――でも、会いたくない。
そんな矛盾が、胸の中でずっとくすぶっていた。
ふと、
バス停の向こう側に、人影がひとつ。
傘も差さず、街灯の下で立ち止まっている。
背の高さ、姿勢、首の傾け方。
全部、忘れたはずなのに、忘れられなかった形。
心臓が、ひとつ大きく跳ねた。
まさか。
こんな偶然、あるはずがない。
そう思うのに、目が離せなかった。
その人影がゆっくりとこちらを向く。
街灯の光が、彼の横顔を薄く照らす。
息が止まった。
間違いようがなかった。
私が初めて“恋”というものを知って、
そして初めて“失う痛み”を覚えた相手。
あの夏に離れたきり、
一度も会わなかった人。
…いや、会わないようにしていた人。
彼は少しだけ驚いたように目を細め、
でもすぐに、懐かしさを隠すように微笑んだ。
「……久しぶりだね」
その声を聞いた瞬間、
時間が、恐ろしいほど静かに巻き戻った。
高校の渡り廊下も、夜のバス停も、
笑った顔も、泣きそうな横顔も、
全部一気に胸に流れ込んでくる。
こんな再会なんて、望んでなかったはずなのに。
彼の左手にも、指輪が光っていた。
胸の奥が、ずしん、と沈む。
それでも――
それでも、どうしてか呼吸が楽になる。
「……うん。久しぶり」
やっとの思いで返すと、彼はふっと目を伏せた。
その表情が、何年経っても変わらなくて、
ほんの少しだけ優しすぎて、
涙が出そうになる。
あの頃みたいに、
二人の間に言葉はいらなかった。
ただ、雨の音だけが静かに降り続ける。
ほんの一瞬、
指輪の冷たさよりも、
心の奥に残った彼の温度のほうが強くなる。
――再会なんて、しないほうがよかった。
――それでも、会えてよかった。
相反する気持ちが胸の中で交差し、
私はただ雨に濡れながら立ち尽くす。
過去でもなく、未来でもなく、
今だけが、二人をそっと繋ぎとめていた。
そんな、
“終わった恋”の始まりみたいな夜だった。