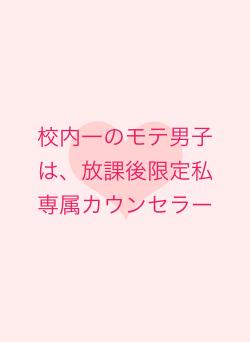いちじくのパフェが運ばれてきた後も、私と護くんは小学校時代の話に花が咲いたままだった。
「え、道ちゃんってパティシエになっているの!?」
「そうそう。しかも人気のパティスリーで働いている」
「凄すぎない!? 小学校の時の夢を叶えて……格好良すぎるよ〜」
きっと護くんは昔の知り合いの現在で知っている話の中でも、思い出話の中でも、明るい話題を選んでくれていたんだと思う。
だからこそ楽しい気持ちのままパフェを食べ進めることが出来た。
パフェが食べ終わって、コーヒーも飲み終わって、会話も一段落した頃……私たちはカフェを出た。
「護くん、本当に奢ってもらって良かったの……?」
「お礼なんだから良いって。貴重な休日に付き合ってもらっているんだから」
護くんは私は気づかぬうちに会計を終わらせていたようで、気づいたら財布を出す隙もなかった。
「え、道ちゃんってパティシエになっているの!?」
「そうそう。しかも人気のパティスリーで働いている」
「凄すぎない!? 小学校の時の夢を叶えて……格好良すぎるよ〜」
きっと護くんは昔の知り合いの現在で知っている話の中でも、思い出話の中でも、明るい話題を選んでくれていたんだと思う。
だからこそ楽しい気持ちのままパフェを食べ進めることが出来た。
パフェが食べ終わって、コーヒーも飲み終わって、会話も一段落した頃……私たちはカフェを出た。
「護くん、本当に奢ってもらって良かったの……?」
「お礼なんだから良いって。貴重な休日に付き合ってもらっているんだから」
護くんは私は気づかぬうちに会計を終わらせていたようで、気づいたら財布を出す隙もなかった。